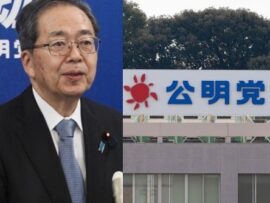2025年上半期の日本経済において、人手不足に起因する倒産が深刻化している。特に従業員や経営幹部の退職が直接的・間接的な原因となる「従業員退職型倒産」は急増しており、その動向は日本社会の根底にある労働力不足と賃金問題の深刻さを浮き彫りにしている。この傾向は、中小企業を中心に事業継続の困難さを増しており、日本の産業構造に大きな影響を与えつつある。
従業員退職型倒産の急増とその背景
帝国データバンクの調査によると、2025年1月から7月までに判明した人手不足倒産251件のうち、「従業員退職型倒産」は74件に上った。これは前年同期(46件)から約6割の大幅増であり、このペースが続けば、集計開始以来最多だった2024年の90件を大きく上回り、年間で初めて100件に達する見込みだ。この由々しき事態は、単なる人手不足だけでなく、特定の業種において人材流出が経営を直接的に破綻させる段階へと進んでいることを示唆している。
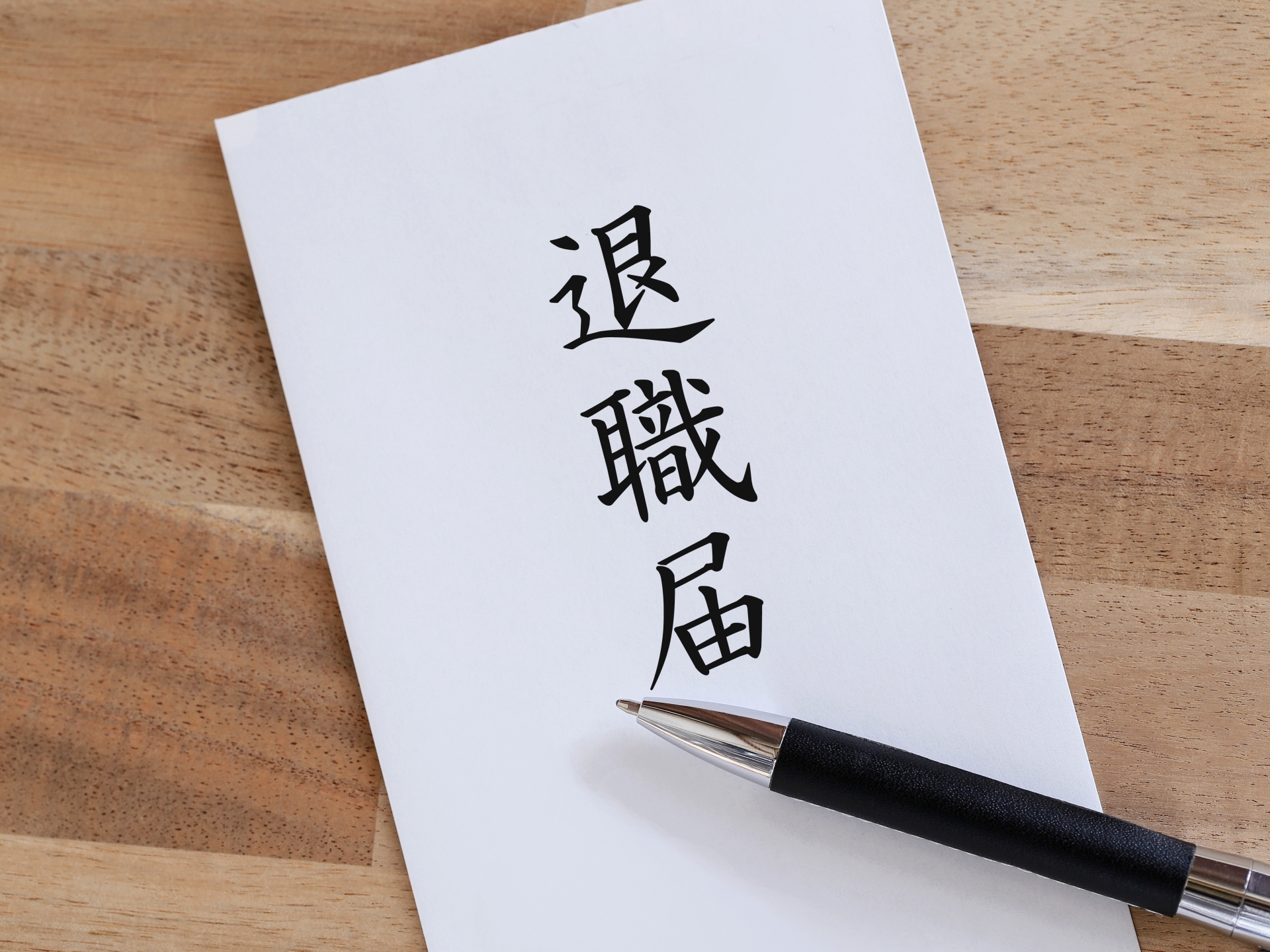 退職する従業員と経営難に陥る会社のイメージ
退職する従業員と経営難に陥る会社のイメージ
業種別に見ると、最も件数が多いのは「サービス業」(19件、全体の25.7%)で、ソフトウェア開発などのIT産業や映像制作業界での退職が特に目立つ。例えば、システム開発を手がけていたピーシーネット(2025年1月、破産)は、エンジニアの引き抜きや人材流出、それに伴う外注費の増加によって収益性が悪化し、事業継続を断念した。次いで「建設業」(17件)でも、設計者や施工監理者といった業務遂行に不可欠な資格を持つ現場作業員、さらには営業担当役員など幹部社員の相次ぐ退職により、事業運営が困難になるケースが頻発している。佐賀の建売住宅販売会社クレセントホーム(2025年5月、破産)は、新代表就任後に幹部社員が相次いで退職し、営業力や施工力が低下したことが致命傷となった。このほか、「製造業」「卸売業」「運輸・通信業」でも2025年1-7月累計で過去最多を記録するなど、従業員の退職が引き金となって経営が行き詰まる事態が幅広い業種に拡大している。
賃上げ圧力と中小企業の課題
こうした「従業員退職型倒産」の背景には、「賃上げ難」という新たな問題も顕在化している。業績悪化を理由に給与を引き下げた結果、従業員の退職が続き事業継続が困難となる「賃上げ難倒産」も発生しており、不動産仲介のウィルプライズ(東京、2025年4月、破産)がその一例だ。
 2013年から2025年までの従業員退職型倒産件数の推移を示すグラフ
2013年から2025年までの従業員退職型倒産件数の推移を示すグラフ
優秀な人材を高給で確保する動きが広がる中で、十分な待遇改善ができない中小企業では人材流出のリスクが加速度的に高まっている。業績悪化などで賃上げの余力がない中小・零細企業の淘汰が、今後も「従業員退職型倒産」という形で表面化する可能性が指摘されており、これは日本経済全体の構造的な課題となっている。
結論
2025年における従業員退職型倒産の急増は、単なる経済指標に留まらず、日本社会が直面する労働力不足と賃金構造の歪みを明確に示している。特に中小企業においては、人材の確保と定着が喫緊の経営課題であり、待遇改善を含む抜本的な対策が講じられなければ、事業継続自体が困難になるという厳しい現実が突きつけられている。今後、企業は従業員のエンゲージメントを高め、魅力的な労働環境を整備することが、競争力を維持し生き残るための鍵となるだろう。