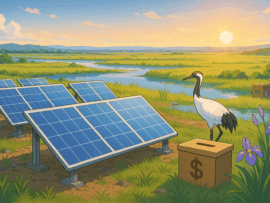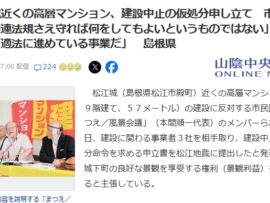文部科学省が経営難に陥る私立大学に対し、余力があるうちからの撤退準備を促す方針を打ち出しました。これは、少子化による18歳人口の減少に伴い、社会からの需要が失われつつある大学が増加している現状に対応するものです。実際、私立大学を運営する学校法人の2割が経営困難に直面し、自力再生が困難な状況にあると私学事業団は報告しています。こうした状況は、大学教員のポスト減少に直結し、結果として大学院博士課程修了者の進路に深刻な影響を与えています。
大学教員ポスト減少と博士課程の現状
大学院は、学校教育法第99条に「学術の理論及び応用を教授研究し、その深奥をきわめ、又は高度の専門性が求められる職業を担うための深い学識及び卓越した能力を培い、文化の進展に寄与すること」を目的としています。本来、高度な専門職業人を育成する機関であるにもかかわらず、日本の博士課程は未だに研究者養成が主軸となっています。特に文系の場合、大学教員以外の進路が極めて限られているのが現状です。
需要と供給の歴史的乖離
日本の大学教員市場は、かつての「売り手市場」から「買い手市場」へと大きく変貌しました。高度経済成長期の1965年には、大学教員の年間需要が約3000人であるのに対し、博士課程修了者は約2000人にとどまり、需要が供給を上回っていました。しかし、2024年現在では、需要が100と仮定すると供給は2400にも達するという、著しい乖離が見られます。これは、一つのポストを24人が争う構造であり、博士号取得者全員が大学教員を志望するわけではないとしても、実際の競争率は全体で約15倍、文系に限れば30倍から50倍にもなると推測されます。
「大学院重点化政策」と「高学歴ワーキングプア」問題
1990年代以降、博士号取得者が急増した背景には、国が推進した「大学院重点化政策」があります。これは、民間企業からの博士への需要増加を見込んだものでしたが、期待されたほどの需要は生まれず、結果として「行き場のないオーバードクター」が社会問題化しました。2007年には水月昭道氏の著書『高学歴ワーキングプア 「フリーター生産工場」としての大学院』が刊行され、この問題が広く認知されることとなり、以降、博士課程への入学者は横ばい(微減)傾向にあります。
2024年春:学部卒との進路比較と不安定化
大学教員市場の閉塞感は、博士課程修了者の多様な進路を厳しくしています。2024年春のデータによると、学部卒業生に無期雇用(正社員など)就職者が多いのに対し、博士課程修了者では非正規雇用就職や、進学でも就職でもない者の割合が顕著に高くなっています。これら不安定な進路は、博士課程修了者全体の約半分を占め、社会科学専攻に限るとその割合は4分の3にも達しているのが実態です。
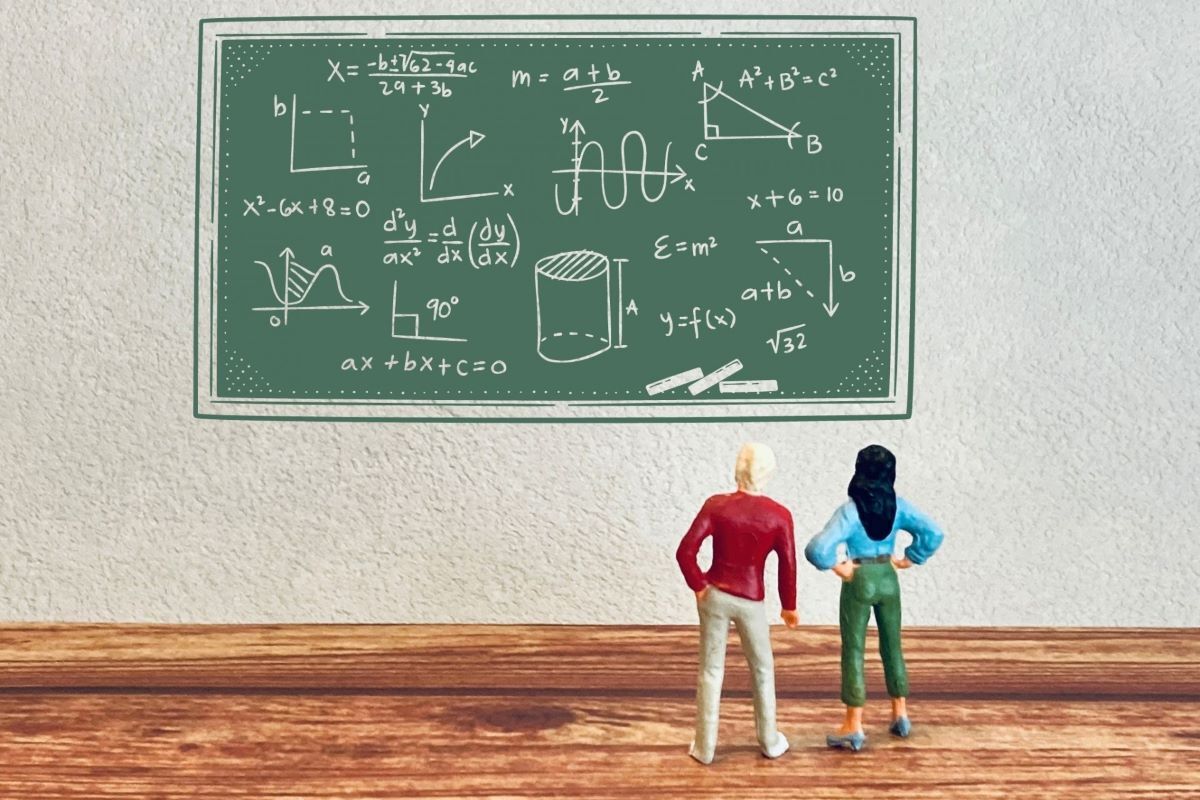 大学院博士課程修了者の厳しい就職状況、特に非正規雇用と不安定な進路を示す研究者像
大学院博士課程修了者の厳しい就職状況、特に非正規雇用と不安定な進路を示す研究者像
公的資金と「知の源泉」の活用
大学院教育には多額の公的資金が投じられています。その投資に見合うリターンが得られない現状は、「1億円かけてフリーターになる」といった批判を生み、「博士課程の学生募集を当面停止すべき」との意見が出るのも無理からぬことです。かつては、職のない博士を雇用した企業に謝礼金を支払う政策も存在しましたが、これは「1億円かけて博士を育て、その雇用に500万円払う」という、本質的な解決には至らない皮肉な状況を示していました。
しかし、博士課程の「顧客層」には変化も見られます。修士課程からのストレートな進学者は減少傾向にある一方、社会人入学者が増加しています。中には、高齢者が人生の目標として学位取得を目指すケースも少なくありません。また、秋田県のように、博士号取得者を高校教員として採用し、その高度な専門性に裏打ちされた分かりやすい授業が好評を得ている事例もあります。
大学院は社会の「知の源泉」であり、その機能を枯渇させるべきではありません。博士課程を取り巻く暗いイメージは、「顧客は20代の若者、機能は研究者養成」という伝統的な固定観念に囚われていることに起因します。社会状況の変化を考慮すれば、博士課程に期待される役割は依然として大きく、高度な専門性を持つ人材をいかに社会全体で活用していくかという視点が、今後の日本の未来を切り拓く上で不可欠です。
資料
- 文部科学省『学校基本調査』
執筆者
- 舞田敏彦(教育社会学者)