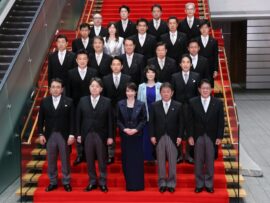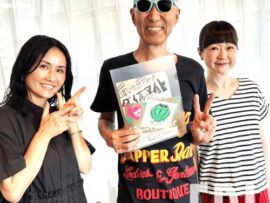長野県松代町は、戦国時代には武田信玄と上杉謙信の激戦地となり、江戸時代には真田氏十万石の城下町として栄えました。佐久間象山といった傑物を輩出し、かつては製糸業で活況を呈した歴史を持ちます。太平洋戦争末期には、大本営の移転候補地となるなど、日本の歴史の表舞台に現れては消える、しかし確かな足跡を残してきた特別な場所です。現在の松代には鉄道が通っておらず、長野駅から犀川と千曲川を越えバスで約30分を要する町です。上信越自動車道の長野インターチェンジを降りればすぐですが、公共交通の便が良いとは言えず、それがかえって古き良き独立国のような風情を保つ一因ともなっています。しかし、今からわずか10数年前まで、この松代には鉄道が存在していました。それが、長野電鉄屋代線です。屋代と須坂を結び、途中松代を通る私鉄のローカル線として、地域住民の足となっていました。
長野電鉄屋代線の軌跡:松代から須坂、そして湯田中へ
長野電鉄は現在、路線バスの運行に加え、長野から湯田中間に鉄道路線を保有しています。この路線の途中駅には須坂駅があり、他にも小布施や中野などの町を通り、終点の湯田中は志賀高原に近い温泉地として知られ、世界的に有名な地獄谷野猿公苑の最寄り駅でもあります。現在の長野電鉄にとって、この路線が唯一の鉄道事業ですが、2012年までは屋代線というもう一つの路線を運営しており、松代まで線路が繋がっていました。この廃止された路線は、地域にどのような足跡を残したのでしょうか。その歴史と現状を辿るため、私たちは屋代駅を起点に探訪を開始します。
屋代駅の現在:過去と未来が交差する廃線跡
屋代駅は、現在では第三セクター鉄道であるしなの鉄道線の駅として機能しています。かつては国鉄・JR信越本線の主要駅の一つであり、特急「あさま」の一部列車も停車していた時代がありました。そして、ほんの13年前まで、この屋代駅には長野電鉄屋代線の電車が乗り入れていたのです。長野電鉄屋代線のホームは、しなの鉄道のホームの東側に位置していました。現在もそのホーム自体は残されていますが、レールや跨線橋などは既に撤去されており、草に埋もれたホームの残骸が、13年という歳月の流れを物語っています。北側の踏切から屋代駅方面を望むと、使用されなくなった長野電鉄の架線柱がそのまま残り、かつての鉄道がそこに存在したことを静かに示しています。この廃線跡は、地域の交通史において重要な役割を担っていた屋代線の記憶を今に伝える貴重な場所となっています。
 屋代線の廃線跡に残るプラットフォームと草むした線路
屋代線の廃線跡に残るプラットフォームと草むした線路
かつて地域と人々を繋いだ長野電鉄屋代線は、惜しまれつつもその役割を終え、歴史の一頁となりました。しかし、その廃線跡に遺されたプラットフォームや架線柱といった痕跡は、松代をはじめとする沿線地域の歩みと深く結びついています。これらの遺構を辿ることは、単なる過去の探訪に留まらず、地域の歴史、文化、そして公共交通の重要性を再認識する機会となるでしょう。
参考文献:
- Yahoo!ニュース (2024年). 長野の里山から13年前に消えた「屋代線」廃線跡には何がある?. https://news.yahoo.co.jp/articles/f12c1bf5151d509ab7a68128477e74cddd0372bc