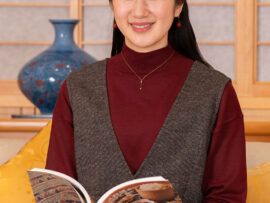長期的な衰退傾向にある日本の百貨店業界において、高島屋はその堅調な業績で際立った存在感を示している。総額営業収益(旧会計基準の売上高相当)は、2020年2月期の9191億円から、コロナ禍の影響で翌年度には6809億円まで減少したものの、その後見事に回復。2025年2月期には17年ぶりに1兆円の大台を突破し、特に新宿店では初の売上高1000億円を達成するなど、顕著な回復を見せている。一方で、西武などの電鉄系百貨店は、相次ぐ店舗閉鎖や規模縮小が続いており、小田急百貨店の新宿本店の跡地への再出店も未定とされるなど、業界内で「明暗」がはっきりと分かれている。この対照的な状況が生まれた背景には、どのような要因があるのだろうか。
 活気を取り戻す日本の百貨店業界の様子
活気を取り戻す日本の百貨店業界の様子
高島屋のV字回復と過去最高益の要因
高島屋の売上高は、ピーク時の1992年2月期に1兆3605億円を記録して以降減少傾向にあり、コロナ禍で大きく落ち込んだが、そこから再び1兆円台へと回復を遂げた。このV字回復の背景には、国内顧客の需要回復と、特にインバウンド消費の増加、そして富裕層による高額品の購買が挙げられる。2023年2月期には既にインバウンドを除く国内顧客売上が2019年度の水準まで戻っており、翌年度以降は高額品の売り上げとインバウンド売上が業績を力強く牽引した。
店舗別に見ると、2024年度の売上高は大阪店が1809億円で最も大きく、次いで日本橋店(1605億円)、横浜店(1424億円)、京都店(1115億円)、新宿店(1000億円)が続き、これら5店舗で全店売上高の約8割を占めている。特に大阪、京都、新宿の3店舗は前年比13%超のペースで増収を達成し、好調を維持した。顧客構成では、通常の来店客が全体の60%を占める一方、外商が25%、インバウンドが15%となっている。大阪店ではインバウンドが3割を占め、外商を上回る結果となった。全社売上高は1990年代の水準には及ばないものの、営業利益は575億円と過去最高を更新。これは、外商顧客やインバウンド客による富裕層需要の取り込み、および高額品の販売増による利益率の改善が大きく寄与したと考えられる。
電鉄系百貨店の苦境と明暗の分かれ目
百貨店業界は、高島屋のような呉服屋を祖業とする「呉服屋系百貨店」と、鉄道会社が運営する「電鉄系百貨店」に大別される。呉服屋系の代表格である三越伊勢丹ホールディングスも近年好調で、伊勢丹新宿本店の2024年度売上高は前年比12.1%増の4212億円となり、全国の百貨店でトップの規模を誇る。
一方で、電鉄系百貨店の業績は芳しくない状況が続いている。かつて日本を代表する百貨店の一つであった西武百貨店は、2003年にそごうと合併し、2009年から2023年までの間、セブン&アイ・ホールディングス傘下で営業を続けたが、規模は縮小の一途をたどり、地方や郊外で店舗閉鎖が相次いだ。電鉄系ではないが、そごうも同様に柏、八王子、川口、徳島店などを相次いで閉鎖。そごう・西武は現在、米ファンドのフォートレス傘下にあり、西武池袋本店の不動産はヨドバシホールディングスに売却されるなど、事業再編が加速している。
小田急百貨店は他社ほど多店舗展開はしていないものの、業績悪化は顕著だ。小田急電鉄の百貨店業売上高は2015年度の1537億円から2018年度には1428億円に減少。2020年度にはコロナ禍で863億円まで落ち込んだ。その後、会計基準変更により単純比較はできないものの、2022年10月に新宿店本館が閉店したことに伴い、大幅に売上高は減少している。新宿店本館の跡地には高さ260メートルの高層ビルが建設される予定だが、低層階に小田急百貨店が再出店するかは未定とされている。新宿では小田急百貨店の閉店後、顧客が高島屋や伊勢丹に流れており、仮に再出店したとしても顧客が戻ってくる見込みは小さいと見られている。同様に、東急百貨店も2023年に閉店した渋谷本店跡地に百貨店を再出店しない方針を打ち出しており、電鉄系百貨店が従来のビジネスモデルからの転換を迫られている現状が浮き彫りとなっている。
 小田急新宿本館跡地に建設予定の高層ビルイメージ
小田急新宿本館跡地に建設予定の高層ビルイメージ
百貨店業界の「明暗」は、単なる景気回復の差だけではなく、各社の事業戦略、特に富裕層やインバウンド需要への対応、そして立地特性と不動産戦略が大きく影響していることが伺える。呉服屋系百貨店は高額品販売や外商といった収益性の高い事業に注力し成功を収めている一方、電鉄系百貨店は駅ビルという立地特性を活かしつつも、百貨店事業そのものの再定義を迫られる局面に立たされていると言えるだろう。