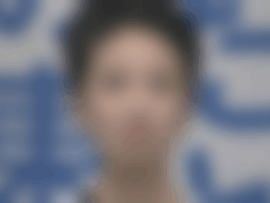登録者数12万超のYouTubeチャンネル『梅子の年金トーク!』が今回取り上げたのは、月額わずか3万5000円の年金で生活保護を申請せざるを得なくなった65歳男性の切実な事例です。また、若いころの散財を悔いる69歳女性のケースも紹介されています。年金だけでは生活が立ち行かないという彼らの告白からは、日本の年金制度に潜む潜在的な「落とし穴」が鮮明に見えてきます。本記事では、知らないと損をする可能性のある年金制度の仕組みと、高齢者の生活を支える社会保障の現実について深く掘り下げていきます。
 日本の年金制度と生活保護の現状を示す高齢者の手元
日本の年金制度と生活保護の現状を示す高齢者の手元
突然の脳梗塞が襲った元塗装職人:月額3.5万円年金繰り上げ受給の選択
この65歳の独身男性は、以前、塗装職人として生計を立て、特に高収入が見込める青森県の核燃料関連施設での作業に従事していました。厳しい入場試験をクリアするほどの専門性と高い給与を得ていましたが、一昨年、仕事中に突然脳梗塞を発症。一命は取り留めたものの、後遺症により立ちくらみなどの症状が残り、高所作業を伴う塗装の仕事は困難となり、長年の職を失い無職に追い込まれました。
本来であれば70歳頃まで働くことを望んでいましたが、病による収入途絶と差し迫った生活費の必要性から、やむを得ず年金受給を決断。63歳で特別支給の老齢厚生年金を、そして来月からは本格的な厚生年金を月額3万5000円で繰り上げ受給することとなりました。「ひょっとしたら来年あたり死ぬかもわからん。目の前にある金をまずもらうことが大事なのよ。少なくても」と語る彼の言葉は、経済的困窮に直面した高齢者が抱える切迫した心情と、老後資金の不安の深刻さを物語っています。
塗装の仕事は鉄骨に色を塗るだけでしたが、核燃料施設という特性上、入場のハードルは高く、その分、安定した高給を得ていました。しかし脳梗塞の後遺症で立つとふらつくため、足場の上で物を落としたり、ペンキをこぼしたりするリスクを考えると、他者を巻き込む危険性があり、仕事の継続は断念せざるを得ませんでした。彼の経験は、身体能力に依存する職業における不測の事態のリスクを浮き彫りにします。
無資産ゆえの迅速な承認:生活保護申請と医療費全額公費の現実
仕事ができなくなった男性は、生活維持が困難となり、最終的に生活保護を申請しました。驚くべきことに、彼が「車も土地もなぁんも持ってない」という全くの無資産であったため、申請は速やかに承認されました。役所の担当者による自宅訪問時もその事実が確認され、「ああ、なんもないですね」との言葉とともに、月約9万円の保護費(うち家賃2万円)が支給されたほか、初期生活の補助として3万円分の家財道具購入費も支給され、電子レンジや洗濯機などを購入することができました。
生活保護申請後、彼の親兄弟には扶養照会の連絡が入りましたが、彼は事前に「面倒みきれない」旨を電話で伝えていたため、滞りなく保護は継続されています。現在、男性は脳梗塞と高血圧の治療のため、一日600円から700円相当の高額な新薬(ジェネリック薬なし)を服用していますが、生活保護受給者であるため、これら全ての医療費は公費で賄われています。「自分で払わなきゃならないんならちょっと考えるけど」「申し訳ないからジェネリックにしようという考えはない。高い薬でも飲んで治ったら、また働けるもん」と本人は述べますが、残念ながら現時点では回復の見込みはないと話します。彼のケースは、病による経済的困窮を社会保障がどのように支えるか、そして人間が本能的に自己の利益を優先する側面をも示唆しています。
この65歳男性の事例は、予期せぬ病や老後の経済的困難が重なった際、年金だけでは生活が立ち行かず、生活保護に頼らざるを得ない日本の高齢者の厳しい現実を浮き彫りにします。自身の老後を安心して過ごすためにも、年金制度の仕組みや、社会保障制度が提供するセーフティネットの役割と限界について深く理解し、適切な老後資金計画と健康維持に努めることが、今まさに不可欠であると言えるでしょう。
参考文献
出典:梅子の年金トーク!『聞くのがこわい年金の話 年金、いくらですか?』(興陽館)