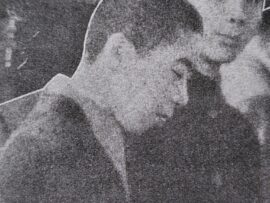日本が大型護衛艦「いずも」と「かが」から離発着可能なステルス戦闘機F-35Bの実戦配備を開始しました。公式には引き続き「護衛艦」と称されているものの、F-35B最大12機の搭載により、事実上「軽空母」としての役割を果たすことになります。これは、今年3隻目の航空母艦が就役した中国が南シナ海に留まらず太平洋への覇権拡大を図る中、日本が2隻の「航空母艦」でこれに対抗する動きであり、第二次世界大戦後約80年ぶりの「事実上の空母保有国」としての新たな一歩です。
 いずも型護衛艦の甲板に停泊するF-35Bステルス戦闘機。日本の事実上の空母運用の象徴。
いずも型護衛艦の甲板に停泊するF-35Bステルス戦闘機。日本の事実上の空母運用の象徴。
F-35Bの配備と「いずも」型護衛艦の空母化
航空自衛隊は8月7日、宮崎県に位置する新田原基地にF-35B戦闘機を配備しました。1機あたり220億円とされるF-35Bは、航続距離1,667キロメートル、優れたステルス機能を備えています。韓国空軍も保有するF-35Aとは異なり、短距離滑走での発進と垂直着艦を可能とするSTOVL(Short Take-Off and Vertical Landing)機能を有しており、艦艇への着艦運用に適しています。
海上自衛隊は、2010年代に就役した全長248メートル、幅38メートルの「いずも」と「かが」に対し、戦闘機の離着艦に対応できるよう甲板の耐熱塗装のやり直しや艦首部分の形状変更などの大規模な改修作業を実施し、事実上の航空母艦へと変身させました。昨年にはF-35Bの離着艦試験にも成功しており、今回の実戦配備開始により、航空母艦としての完全な運用能力を獲得したと言えます。日本は最終的にF-35Bを計42機実戦配備する計画であり、日本経済新聞も「F-35Bは飛行甲板を持つ『いずも』型護衛艦で空母搭載機として運用される」と報じています。
国際連携と日本の「護衛艦」呼称の背景
日本はまもなく「かが」を投入し、英国の空母「プリンス・オブ・ウェールズ」との合同訓練を開始する予定です。8月12日まで米・英・日・豪などが参加して行われる西太平洋海軍共同訓練では、英空母から発艦したF-35Bが「かが」に着艦するシナリオも含まれており、国際的な連携強化の姿勢も示されています。
第二次世界大戦当時、日本は正規空母10隻を保有する空母大国でした。1922年に建造された「鳳翔」は、商船や貨物船の改造型ではない純粋な空母としては世界で初めてのものです。1941年12月の真珠湾攻撃時にも空母6隻を投入しました。しかし、米国とのミッドウェー海戦で多数の空母が撃沈され、敗戦後は平和憲法に基づき空母のような「攻撃型の兵器」の保有が禁じられました。この歴史的・法的背景から、海上自衛隊は空母として改修された「いずも」型を依然として「護衛艦」と呼称し続けています。
今回のF-35Bの実戦配備と「いずも」型護衛艦の事実上の空母運用開始は、日本の防衛力強化における画期的な出来事です。これは、中国の海洋進出に対する地域安全保障のバランスを維持し、国際的な連携を深める上で重要な戦略的意味合いを持つと言えるでしょう。
参考文献:
- 朝鮮日報日本語版
- 日本経済新聞
- 海上自衛隊公式発表 (該当記事に直接リンクがないため、一般的な情報源として記載)