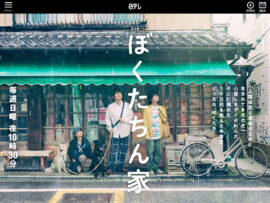東北地方を中心に、全国各地でクマによる人身被害が深刻化している。今年11月7日時点で死者数は過去最悪の13人に達し、特に被害が甚大な秋田県には自衛隊までが派遣される事態となった。東京都内でもクマの目撃情報が相次ぐなど、住民の間に緊張が高まる中、SNS上では「熊肉」がにわかに注目を集めている。果たして、食用としての熊肉の普及は、現在のクマ被害対策に一役買う可能性はあるのだろうか。
SNSで拡散する「熊肉」ブームとその背景
クマ肉への関心が高まるきっかけの一つとなったのは、10月29日にX(旧Twitter)でヤギ氏が投稿した画像だ。「青森県道の駅フェア&道の駅よこはま大感謝祭」で販売されていたツキノワグマの串焼きの画像は、そのワイルドな見た目と2本800円という価格で大きな話題を呼んだ。
ヤギ氏の食レポによると、「下処理が完璧だったのか、臭みなくホロホロ美味かった!焼肉のタレみたいなのに漬けられてたが、スパイス焼きも美味しそう」「羊肉に似てるかな?」とのことで、その意外な美味しさが8.7万件以上の「いいね」と1300万回を超える閲覧数を記録した。この投稿は、クマというタイムリーな話題と見た目のインパクト、そして味の評価が相まって大反響を呼び、中でも特に目立ったのは、昨今のクマ被害と結びつける声だった。
ネットユーザーからは、「もっと安く売って、個体数を減らせば、街中に出てくる問題解決するのでは?」「熊害酷いとこもこういうのやればいいと思う」「熊が美味い…って広まれば…鰻みたいに…こぞって捕獲するようになるかな…?」といった期待の声が上がり、「食べて駆除」という考え方が広く拡散された。しかし、この解決策はそれほど単純なものなのだろうか。
 炭火で焼かれた香ばしいツキノワグマの串焼き。相次ぐクマ被害の対策として注目される熊肉料理の可能性を示す。
炭火で焼かれた香ばしいツキノワグマの串焼き。相次ぐクマ被害の対策として注目される熊肉料理の可能性を示す。
「白神ジビエ」が語る熊肉利用の現状と挑戦
ヤギ氏が食した熊串焼きを販売していたのは、青森県中津軽郡西目屋村に拠点を置く一般財団法人・ブナの里白神公社だ。同公社は地元ホテル「ブナの里白神館」の運営や地場産品の開発などを手掛けており、その活動の一環として熊肉の加工・販売も行っている。
ブナの里白神公社の事務局長である角田克彦氏は、熊串焼きが誕生した経緯について次のように語った。「2020年11月、西目屋村が食肉処理施設『ジビエ工房白神』を開設し、翌年7月から『白神ジビエ』のブランド名で本格的にツキノワグマを使った料理の展開を始めました。その後、このブランドを宣伝し、ジビエという食文化を広めるために、県内外のイベントで熊鍋や熊串を出店・販売しています。」
この取り組みは、単に野生動物を駆除するだけでなく、その資源を有効活用し、地域経済に貢献するという側面も持っている。しかし、熊肉の流通には食肉処理の衛生管理や安定的な供給体制の確立、そして消費者への認知度向上など、様々な課題が存在する。野生動物の肉を食用として広めることは、狩猟の振興や食文化の多様化にもつながるが、それと同時に、生態系の保全や持続可能な野生生物管理という複雑な問題も視野に入れる必要があるだろう。

結論
全国各地で深刻化するクマ被害に対し、SNS上で話題となった「食べて駆除」という熊肉消費の動きは、短期的な解決策としてだけでなく、新たな食文化としての可能性を提示している。青森県のブナの里白神公社による「白神ジビエ」の取り組みは、野生動物の個体数管理と地域経済の活性化を両立させようとする試みだ。
しかし、クマ被害対策としての熊肉の普及には、衛生管理、安定供給、そして何よりも消費者の受容性の確保が不可欠である。単なる一過性のブームで終わらせることなく、持続可能なジビエ利用の仕組みを構築し、野生生物管理と食の多様性という観点から、その有効性を冷静に評価し、将来的な展望を模索していく必要がある。