「毒母」による支配が、一人の人生をどのように破壊しうるのか。連載記事「毒母に人生を破壊された息子たちの過酷な人生」の後編では、前編で描かれた塾経営者の母親による過度な教育と精神的・身体的虐待の後、一橋大学に合格したぼそっと池井多さん(63)がたどった「ひきこもり」の道と、その後の母親との複雑な関係に深く迫る。彼の経験は、現代社会における「ひきこもり」問題や親子の確執の根源を浮き彫りにするだろう。
合格後の「報酬なき人生」と精神的打撃
池井多さんは、母親の宿願であった一橋大学への合格を果たした。しかし、期待していた「おめでとう」や「よくやった」といった承認の言葉は一切なく、母親からは冷たく「おまえは明日から、英語の勉強をしなさい。一橋の英語のレベルは高いから」と突き放された。彼はこの時、「報酬なき人生でした。成功を成し遂げても、母親から肯定してもらえない。承認してもらえるという、報酬がない人生でした」と振り返る。
大学を卒業し、有名企業からの内定も得た矢先、池井多さんの身体は突然動かなくなった。彼は大学の寮にひきこもり始めた。「このまま就職してしまったら、母親の思う壺ではないか。“お母さん、虐待してくれてありがとう”って言わなきゃいけない人生になる。それだけは嫌だっていう無意識の引き止めが、身体が動かないという症状になったのかもしれません。間違いなく、うつを発症していたと思います」と、当時の精神状態を語っている。
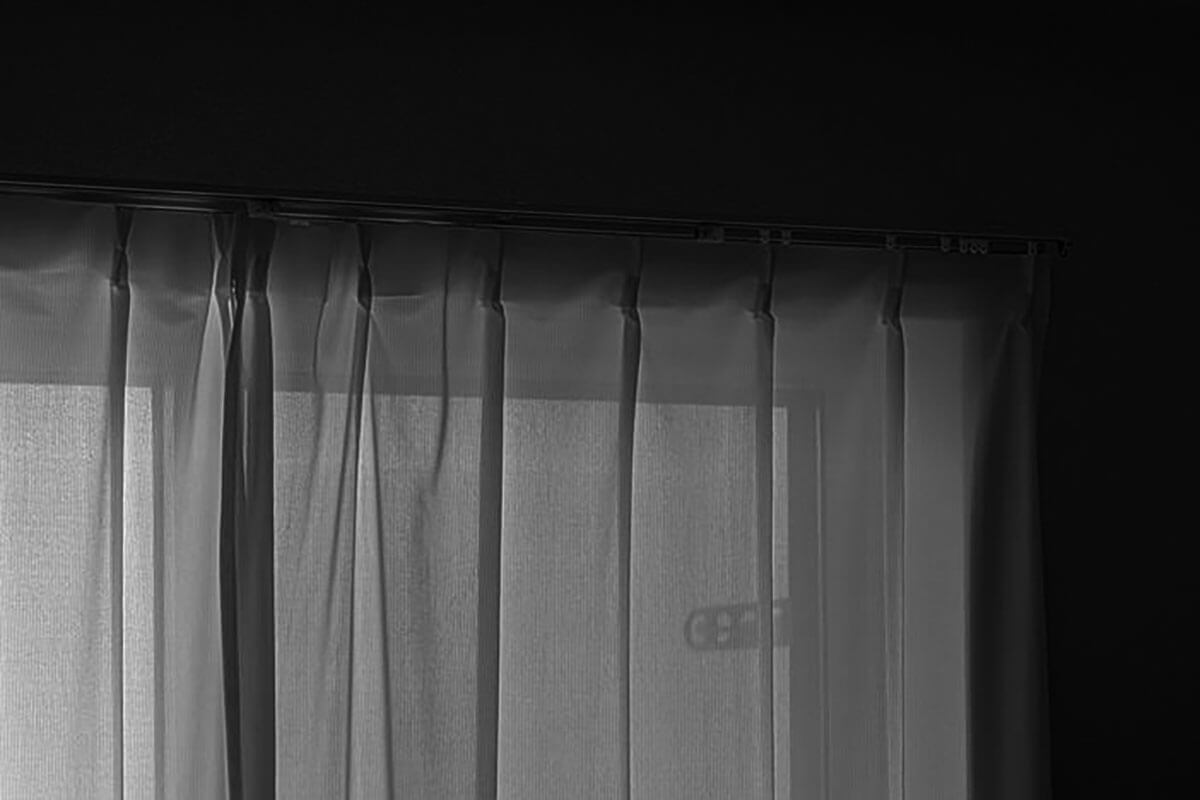 薄暗い部屋で座り込む人物のイメージ。毒母の重圧と人生への絶望からひきこもりに陥った若者の孤独を表す。
薄暗い部屋で座り込む人物のイメージ。毒母の重圧と人生への絶望からひきこもりに陥った若者の孤独を表す。
「死ねたらいいな」海外での「外こもり」生活
1980年代半ば、日本社会にはまだ「ひきこもり」という言葉自体が存在せず、その状態は極めて居心地の悪いものだった。池井多さんはその状況から逃れるべく、「海外に逃げた」と表現する。バックパッカーとして数カ国を渡り歩いたが、どこへ行っても安宿にこもり続ける「外こもり」を続けた。彼の心の奥底には深い絶望があった。「アフリカやアラブなど、どうせなら、死ねそうな国に行こう。そこで、自然に死ねたらいいなと考えました」と、当時の壮絶な心境を明かしている。
偽りの帰国と父との日々
20代のほとんどを海外で過ごした後、30代前半に差しかかった頃、池井多さんは母親から父親が病気であるとの知らせを受け、帰国を決意する。しかし、実際に帰国してみると、父親は健康そのものであり、病気というのは池井多さんを帰国させるための母親の嘘であったことが判明した。
この事実を知り、働く気にもなれなかった彼は、実家には戻らず、父親の単身赴任先の団地に身を寄せた。そこで、父親の食事を作る日々を過ごすことになる。母親からの精神的な支配と嘘によって、彼の人生は翻弄され続けてきたが、この父との静かな時間は、束の間の安らぎであったのかもしれない。
池井多さんの半生は、「毒母」との関係が個人の人生にどれほど深く、そして長く影を落とすかを痛切に示している。彼の「ひきこもり」は単なる社会からの孤立ではなく、母親からの承認が得られない「報酬なき人生」が生み出した、魂の叫びであったと言えるだろう。
参考文献
- 黒川祥子. (2025年8月17日). 塾経営者の毒母に人生を破壊された息子…一橋大合格も褒められず「ひきこもり」「外こもり」へ. デイリー新潮. https://www.dailyshincho.jp/article/2025/08170803/
- Yahoo!ニュース. (2025年8月17日). https://news.yahoo.co.jp/articles/f2b5dd7daba37a40f80470295fba0e76f14899d9




