少子高齢化が進む現代日本において、子や孫の教育費は年々増加の一途をたどり、親世代だけでの負担は困難な状況にあります。このような背景から、祖父母が教育資金の支援を行うケースは一般的になり、「喜ばれる贈り物」として多くの家庭で実践されています。しかし、この温かい支援の裏側には、時に思いがけない「贈与税」という落とし穴が潜んでいます。「年間110万円以内なら非課税」という一般的な認識だけでは不十分であり、制度の正しい理解と適切な手続きを怠ると、予期せぬ課税対象となるリスクがあるのです。
「青い封筒」が語る現実:誤解されがちな基礎控除のルール
都内に暮らす70代の佐々木誠一さん(仮名)は、郵便受けに届いた税務署からの「青い封筒」を見て凍りつきました。そこには、孫への贈与に関する詳細な記述を求める「お尋ね」の書面が同封されていたのです。佐々木さんには高校生と大学生の2人の孫がおり、7年前から長男夫婦の「教育費がかさむ」という相談を受け、毎年100万円ずつ現金を渡して支援を続けていました。総額は7年間で700万円に上り、その使い道は長男夫婦に任せていました。佐々木さんは「塾代や授業料、海外留学の準備金など、すべて孫のためなので、贈与税など考えたこともなかった」と語ります。
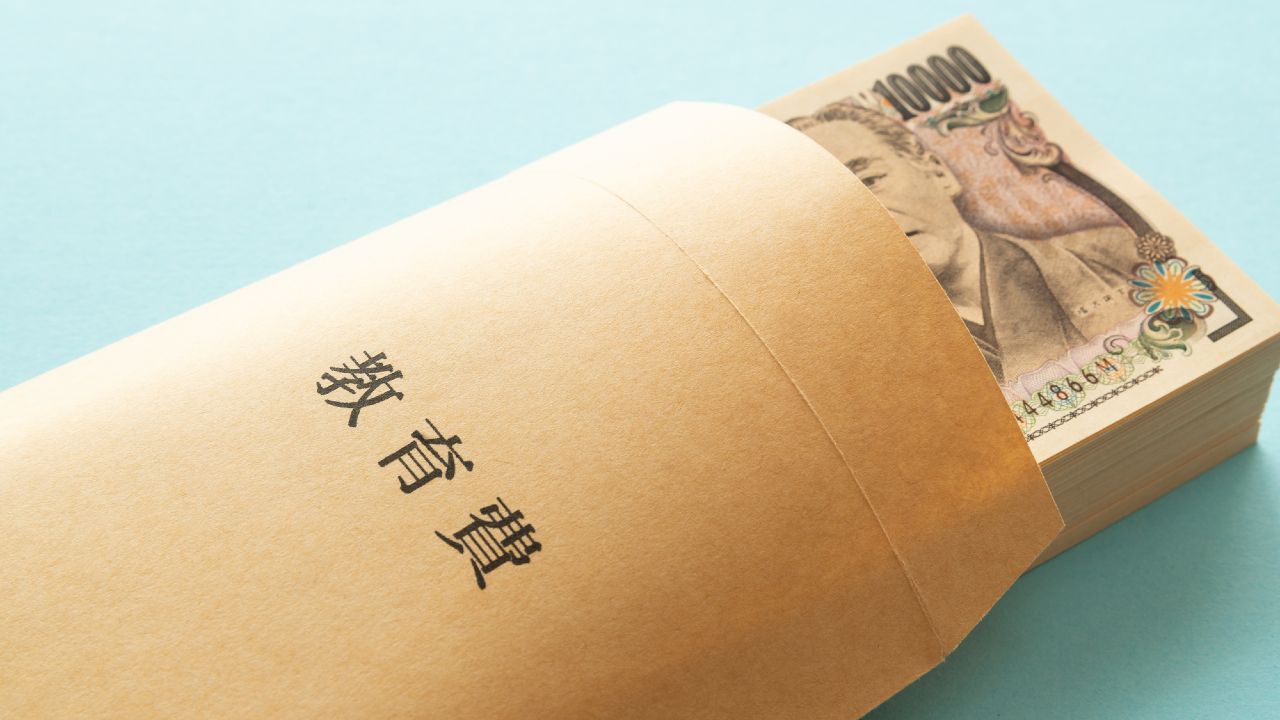 教育資金の贈与について考える祖父母と家族
教育資金の贈与について考える祖父母と家族
多くの方が「贈与税には年間110万円の基礎控除があり、100万円なら非課税」と考えていますが、実際にはいくつかの重要な注意点があります。まず、基礎控除の対象となるのは「1年間(1月1日〜12月31日)に受贈者が受け取った贈与の合計額」です。これには現金だけでなく、車、宝飾品、家電といった現物贈与も含まれます。さらに、祖父と祖母からそれぞれ50万円ずつ受け取った場合も、合計100万円として合算されます。また、記録が不十分な場合、年をまたいでいても過去の贈与が遡って課税される可能性も否定できません。
なぜ追徴課税に?教育資金贈与特例制度の重要性
佐々木さんの場合、孫への教育費支援以外にも、お祝い金や生活費の援助を行っていた年があり、それらを合計すると基礎控除額である110万円を超える年が複数ありました。加えて、孫への教育資金を非課税で贈与できる「教育資金の一括贈与非課税制度」を一切利用していなかったため、通常の贈与と見なされてしまったのです。
税務署が佐々木さんの贈与を把握したきっかけは、長男が確定申告で教育関連の控除を受けた際、その資金の出所が確認されたことでした。教育資金の一括贈与非課税制度を利用するには、金融機関での専用口座開設、教育機関からの領収書提出など、厳格な手続きが必須となりますが、佐々木さんはこれらの手続きを何も行っていませんでした。税務署とのやり取りの結果、過去5年分の贈与について申告漏れが指摘され、本税と加算税を合わせて約100万円の追徴課税を納めることになりました。佐々木さんは「孫のためにと善意で行ったことが、まさかこんな形で税金になるとは。もっと早く仕組みを知っていれば」と後悔の念をあらわにしました。
賢い教育資金支援のために知っておくべきこと
佐々木さんの事例が示すように、善意の教育資金援助も、税務上の知識が不足していると予期せぬ負担を招くことがあります。このような事態を避けるためにも、以下の点を実践することをお勧めします。
まず、家族間であっても金銭や品物の授受に関する記録を正確に残すことが極めて重要です。「いつ」「誰が」「誰に」「何を」「いくら」贈与したのかを明確にし、贈与契約書を作成するなど、証拠を残すようにしましょう。
次に、「教育資金の一括贈与非課税制度」の積極的な活用を検討してください。この制度は、祖父母などから孫などへ教育資金を一括で贈与した場合に、最大1,500万円までが非課税となる制度です。利用には金融機関での専用口座開設や、教育費の支払いの都度、領収書を提出する義務など、手続き上の制約がありますが、まとまった金額を贈与する場合には非常に有効な手段となります。
善意の支援を税金で無駄にしないために
子や孫への教育費支援は、家族の絆を深め、未来への投資となる尊い行為です。しかし、その善意が税金という思わぬ形で目減りしてしまうことは避けたいものです。今回紹介した佐々木さんの事例は、基礎控除の誤解や特例制度の不利用が招く現実を示しています。
賢い教育資金の支援を実現するためには、贈与税に関する正しい知識を身につけ、適切な制度を積極的に活用することが不可欠です。不安な場合は、税理士などの専門家への相談をためらわずに行い、適切なアドバイスを得るようにしましょう。これにより、心からの教育費支援を税金で無駄にすることなく、効果的に行うことができます。






