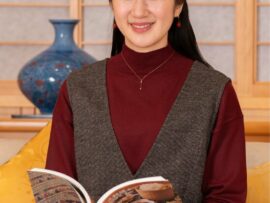現代において、子どもの「なりたい仕事」に過度に口を出す親が増える一方で、仕事に追われ、家庭で仕事の愚痴ばかりをこぼし、子どもと向き合う時間がない親も少なくありません。しかし、親の関わり方次第で、子どもの将来の職業・企業選択だけでなく、その後の収入にまで大きな差が生じる可能性が指摘されています。では、どのように子どもと関わることが、その将来の職業選択に良い影響を与えるのでしょうか。本記事では、具体的な事例を交えながら、家庭内での「仕事の話」が子どものキャリア形成に与える影響を深掘りします。
 子どもの将来の職業選択について考える親子
子どもの将来の職業選択について考える親子
「良い親」が子どものキャリアを妨げたケース:遠田郁美さんの失敗から学ぶ
遠田郁美さん(仮名・38歳)は、有名大学を卒業した優秀な人材でした。しかし、新卒で入社した大手メーカーでは業務内容が合わず、ストレスから退職。その後はフリーターや派遣社員を転々とし、現在の年収は300万円にとどまっています。一見、子どもに理解があると思われた遠田さんの両親の関わり方には、何が問題だったのでしょうか。
過保護な関与と現実との乖離
遠田さんは小学校受験を経験しており、両親は受験の妨げにならないよう、家庭に一切仕事の愚痴を持ち込みませんでした。また、遠田さんが将来の夢を語り始めると、その意思を尊重し、肯定も否定もせず、ただ受け止めるという姿勢を貫きました。一見、理想的な子育てに見えますが、これが遠田さんのキャリア形成に悪影響を及ぼした可能性が考えられます。
適性不明のまま就職・転職を繰り返し低年収に
社会に出てから、遠田さんは自身の適性や能力を理解できず、半年から1年で契約満了となる派遣社員の職を7回も繰り返しました。親が家庭で仕事のリアルな側面を見せず、子どもの意見を尊重しすぎた結果、遠田さんは社会の仕組みや仕事の多様性、そして自身の内面と外の世界とのつながりを深く考察する機会を逸したのかもしれません。親の勤務先は知っていても、そこでどのような業務が行われているか、具体的な仕事内容については全く説明できませんでした。このことが、職業・企業選択の失敗に繋がり、「自分探し」を永遠に続ける結果となりました。
早期の「職業意識」が成功に導いたケース:桜井公博さんの高収入の秘訣
遠田さんとは対照的に、桜井公博さん(仮名・28歳)は20代後半で年収1000万円を超える仕事に就いています。桜井さんの両親は、彼が小学5年生の時に不動産会社を開業。家庭内では、賃貸契約に関する顧客の不満や、夫婦間の仕事のやり方に関する衝突が日常的にありました。
家庭での「リアルな仕事の会話」が鍵
桜井さんは、両親の会社で時間を過ごしたり、取引先のリフォーム会社に同行したり、親戚の税理士事務所を訪れたりすることで、幼い頃から多種多様な職業とその業務内容を肌で感じてきました。仕事に関する愚痴も含め、リアルな会話に触れることで、彼は自然と社会における仕事の役割、大変さ、そしてやりがいについて詳しくなっていきました。
多様な職種への接触がキャリアを拓く
こうした環境の中で、桜井さんは早い段階で自分の将来の仕事を具体的にイメージし、適性分析を行うようになりました。新卒で入社したデザイン会社では、自然体で仕事を楽しむうちに社内外からの評価が高まり、入社5年目には社長直轄の経営戦略チームに配属されました。さらに、会計士の資格を取得しコンサルタントファームに転職。会計士としての専門知識に加え、経営戦略のスキルを活かして年収1000万円超を達成しました。彼は、幼い頃から「店員」「先生」といった身近な職業だけでなく、社会には様々な職種があり、それぞれに需要があることを意識するようになっていたのです。
親の関わり方で明暗が分かれる子どものキャリアパス
遠田さんと桜井さんのケースは、親の「仕事に対する姿勢」や「家庭での仕事に関するコミュニケーション」が、子どものキャリア形成に決定的な影響を与えることを示しています。仕事の愚痴を言う親と、全く仕事の話をしない親、この両極端な関わり方が、子どもの職業選択に大きな影響を与えているのです。
仕事の「良い面」も「悪い面」も共有する重要性
遠田さんの両親が仕事の愚痴を家庭に持ち込まなかったのは、子どもを心配する「良い親」としての配慮だったかもしれません。しかし、その結果、子どもは仕事の現実的な側面を知る機会を失い、社会に出てから直面する困難への免疫が不足した可能性があります。一方で、桜井さんの両親のように、仕事の悪口や夫婦間の衝突があったとしても、それが「仕事とは何か」というリアルな学びの場となり、子どもの早期の職業意識を育むことにつながりました。
「過保護」と「無関心」の間の理想的な距離感
大切なのは、過保護に子どもの職業選択に口を出しすぎたり、あるいは逆に全く無関心で放任したりするのではなく、適切なバランスで関与することです。家庭で仕事の楽しさ、難しさ、社会との繋がり、そして時には不満といった多角的な側面をオープンに話し合うことが、子どもが自分自身の適性を見つけ、将来のキャリアパスを主体的に設計する上で非常に重要です。親が具体的な仕事のイメージや社会での「働き方」を共有することで、子どもはより現実的な視点と、変化に対応できる柔軟なキャリア形成能力を養うことができるでしょう。
結論
子どもの将来の職業選択や年収は、親の家庭での「仕事の話題」に対する姿勢に大きく左右されることが明らかになりました。過保護に現実を隠したり、あるいは全く無関心でいたりすることは、子どものキャリア形成にとって必ずしも良い影響を与えません。むしろ、仕事の良い面も悪い面も、家庭でオープンに話し合うことで、子どもは社会の仕組みや多様な職種に早期から触れ、自身の適性や興味に基づいた「適職」を見つける力を育むことができます。親は、子どもが未来の社会で活躍できるよう、家庭を「キャリア教育」の場として捉え、積極的に関わっていくことが求められています。
参考文献
- 柏木理佳. 「親が子どもの将来の年収を下げている? 家庭で仕事の話をしない親の“罪”」. ダイヤモンド・オンライン. 2025年8月19日.
https://news.yahoo.co.jp/articles/4dad9cf9da122f849e67778ffec36bc78bd155af