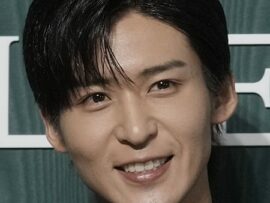海外から帰国した多くの人が日本の食の豊かさに安らぎを感じるでしょう。高品質で衛生管理の行き届いた食事が低価格で享受できる日本の外食産業は世界有数です。この豊かな食生活を支えているのは、豊富な人材を抱え、安価で高品質な食料を都市部に安定供給する日本の過疎地域、すなわち第一次産業です。しかし、個人農家の平均年収約350万円という数字の背後には、見えにくい厳しい現実が存在します。私たち消費者が安くて美味しい国産野菜を求め続ける中で、その要求は生産者にとってどのような負担となっているのでしょうか。
安定供給の裏に隠された生産者の犠牲
日本の食料品価格が安価に保たれるのは、社会全体の都合によるものです。食費は日々の生活に密接に関わり、食料価格の高騰は国民生活の悪化に直結します。そのため、生産者は凶作や不漁であっても販売価格を上げることが難しく、幸運にも豊作や大漁になっても薄利多売となるのが現状です。私たちは娯楽には高額を支払う一方で、食料の価格が高いと不満を述べ、海外で大量生産された安価な輸入品と同じ価格水準を求めてしまいます。生産者はその要求に応え、安くて美味しい食材を各家庭に届け続けているのです。この日本の食の安定供給は、生産者の見えざる努力と犠牲の上に成り立っています。
 日本の農家の平均年収と厳しい農業経営の現実
日本の農家の平均年収と厳しい農業経営の現実
見かけの年収と手取りの乖離:厳しい農業経営の実態
日本の農家の平均年収は、個人農家で約350万円、法人農家の役員で約560万円、その従業員で約240万円とされています。一見すると、地域によっては悪くない数字に見えるかもしれません。しかし、農業には種苗、肥料、飼料、機械、耕具、衛生、修繕、光熱費、荷造り、運賃、手数料、共済金など、多岐にわたる重い経費負担が伴います。これらの経費を差し引いた所得は、年収の約半分にまで減少すると言われ、手取りで約175万円というのが実態です。この厳しい状況から、生活破綻を防ぎ、農業を継続するために、経費の水増しによって節税を図る農家も少なくありません。
新規就農への道のりと中山間地域のハンディキャップ
新規就農者にとっても、農業への道は容易ではありません。例えば、ある調査地域ではピーマン栽培を行う移住者に支援金が給付されていますが、移住の動機が「支援金が一番高かったから」というケースもあります。ピーマン栽培には夏季に2ヶ月の休閑があるため、長期休暇が取れる魅力もありますが、熱帯地域の作物であるピーマンをビニールハウスで栽培するには多大な設備投資が必要です。支援金があっても、資材や機械などの初期投資により、新規農家は最初の3年間は赤字を強いられ、利益が出るまでに約4年かかると言われています。
本来、農業は広大な平野で行うのが最も効率的です。しかし、山岳国家である日本では平野の面積が限られており、かつて農地として利用されていた平野は、日本の近代化に伴い工場や住宅地に取って代わられました。結果として、多くの農業従事者は中山間地域の山林を切り開き、高低差があり農業に不向きな場所で新たな農地を確保せざるを得ませんでした。このような環境下では、広大な平野を持つ国々との国際競争に太刀打ちすることは極めて困難です。
北海道に見る「スマート農業」と地域格差の拡大
日本国内で広大な平野を持つ数少ない地域の一つが北海道です。北海道では農地の生産性が高く、先進的な農家はAIロボットやIoTといったスマート農業の導入にも積極的に取り組んでいます。その結果、北海道の農家とその他の地域、特に中山間地域の農家では平均年収に2倍近い差が生じています。中山間地域の農家が汗水垂らして懸命に働いても、収益は思うように上がらず、努力と対価のアンバランスが深刻な地域格差として現れているのです。
結論
日本の豊かな食卓を支える農業は、見かけの年収とは裏腹に、重い経費負担、社会からの低価格要求、不利な地理的条件、そして地域間の格差といった深い課題を抱えています。消費者が安価で高品質な食料を享受できる一方で、生産者は持続的な経営を維持するために多大な努力と犠牲を強いられています。日本の農業、特に過疎地域や中山間地域における第一次産業の現状を深く理解し、持続可能な食料供給体制と地域経済の活性化に向けた議論を深めることが、日本の未来にとって不可欠です。
参考文献:
- 書籍『田舎の思考を知らずして、地方を語ることなかれ 過疎地域から考える日本の未来』より一部を抜粋・再構成。