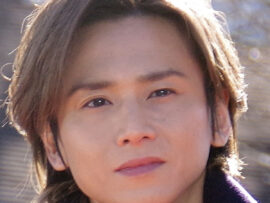海上自衛隊の護衛艦「もがみ型」(FFM)をベースとした艦艇の導入をオーストラリア政府が決定した。これは日本の大型防衛装備品として初の輸出事例となり、日豪両国間の協力深化と、海洋進出を強める中国への戦略的な対抗という点で歴史的な意義を持つ。2029年の納入開始を見込むこの合意は、日本の防衛産業の新たな幕開けを告げるものだ。
日本防衛装備品、初の大型輸出が実現
オーストラリア海軍が次期汎用フリゲートとして、三菱重工業が提案した「もがみ能力向上型」護衛艦の採用を今月発表した。日本は2015年に潜水艦「そうりゅう型」の売り込みを試みたものの、最終的にはフランス製(後に米英の原潜に変更)が採用されており、今回の成功は約10年越しの成果となる。この輸出は、日本の大型防衛装備品輸出において初のケースであり、歴史的な節目として注目されている。
フリゲートとは、もともと小型艦艇のカテゴリーを指すが、近年では大型化が進み、駆逐艦や巡洋艦クラスの能力を持つものも現れている。今回、オーストラリアが検討したライバル艦はドイツ、韓国、スペインなどから提案されたフリゲートであり、日本は最後までドイツ艦と競り合った結果、採用を勝ち取った。
 海上自衛隊の護衛艦「もがみ型」のイメージ。オーストラリア海軍が次期汎用フリゲートとして採用を決定した艦艇のベースとなる。
海上自衛隊の護衛艦「もがみ型」のイメージ。オーストラリア海軍が次期汎用フリゲートとして採用を決定した艦艇のベースとなる。
「もがみ型」選定の決め手は?専門家が分析
軍事評論家の毒島刀也氏は、今回の選定理由について次のように解説している。「候補にはドイツのMEKO A-200、スペインのAlfa3000、韓国の大邱級バッチII/IIIが挙がっていました。スペインと韓国はオーストラリアの要求する作戦期間やサポート体制に合致せず、早い段階で候補から外れました。ドイツ製は以前の艦艇での経験からサポート面での安心感があるものの、近年のヨーロッパ造船業界における納期や品質の不確実性が懸念され、欧州製コンポーネントで組まれた艦では米国製ミサイルの組み込みに時間がかかるという問題がありました。」
その上で、毒島氏は日本製の強みを強調する。「一方で日本製は建造費こそ高いものの、維持費は比較的低く抑えられます。装備や運用がアメリカ軍との親和性が高いため、将来的な装備変更のリスクが少ない点も評価されました。さらに、最初の3隻を日本国内で製造し、納期を確実に守るという約束が、最終的な採用の決め手となったのです。」
今回の計画では、10年間で100億オーストラリアドル(約9600億円)を投じ、合計11隻のフリゲートが建造される予定だ。前述の通り、最初の3隻は日本国内で建造され、そのうち1番艦は2029年に納入され、2030年には運用を開始する見込み。豪国防産業相のパット・コンロイ氏は、「コスト、性能、納期の遵守という点で『もがみ型』が明らかに優れていた」と述べ、今後の日豪関係のさらなる発展に期待を表明した。

日豪協力の深化と地域安全保障
今回のフリゲート輸出は、日豪間の防衛協力が新たな段階に入ったことを示している。両国はインド太平洋地域における主要な民主主義国として、法の支配に基づく自由で開かれた国際秩序の維持を共通の目標としている。特に、中国の急速な海洋進出と影響力拡大に対抗するため、日豪両国の連携は不可欠となっている。
日本の防衛装備移転三原則の下での大型装備品輸出は、日本の防衛産業に新たな活路を開くだけでなく、同盟国や友好国の防衛力強化に貢献することで、日本の安全保障環境を間接的に改善する効果も期待される。この歴史的な取引は、地域全体の安定と安全保障に寄与する重要な一歩となるだろう。
参考文献
- Yahoo!ニュース: 集英社オンライン「海上自衛隊の護衛艦「もがみ型」がオーストラリア海軍に採用!なぜ初の大型装備品輸出は実現したのか?」