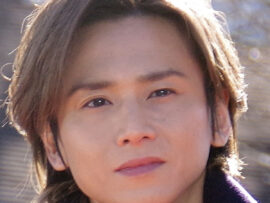2024年、ベトナム系アメリカ人歌手の「セイラー」が自身の楽曲をインターネット上で公開し、その音楽性のみならず、彼女の「特徴的な黒い歯」が大きな注目を集めました。香港紙「サウス・チャイナ・モーニング・ポスト」によると、セイラーのこの特徴的な「黒い笑顔」は、単なるファッションステートメントにとどまらない深い意味を持っています。彼女やモリー・サンタナ、クイ・ヤスカといったアジア系アーティスト(いずれも日系アメリカ人)は、公の場で歯を黒くする行為を通して、近年、文化的再生と故郷への回帰を試みているのです。現代社会では、均一に並んだ白い歯が美の基準として広く認識されていますが、あえて「歯を黒く見せる」という、異なる美的表現を追求するアジア系の若い女性たちが現れています。
 「黒いグリル」を装着したベトナム系アメリカ人歌手セイラー。伝統と現代ファッションを融合させた美的表現
「黒いグリル」を装着したベトナム系アメリカ人歌手セイラー。伝統と現代ファッションを融合させた美的表現
現代に甦る「歯の黒染め」文化:ルーツへの回帰
現代において、「黒い歯」は異質に映るかもしれません。しかし、これは単なる奇抜な流行ではなく、アジアの伝統文化に根ざした美的価値観の再評価と捉えられています。特にセイラーのようなアジア系アメリカ人アーティストたちが、自身のルーツである故郷の文化に立ち返り、それを現代のファッションや表現に取り入れることで、新たな美的基準を提示しているのです。これは、西洋中心の画一的な美意識に対する多様性の追求であり、自身の文化的なアイデンティティを再構築する試みとも言えます。Molly SantanaやQui Yasukaといった他のアジア系アーティストも同様の表現を見せており、この動向は個人の選択を超えた、より広範な文化的ムーブメントとして注目されています。
かつて世界に広まっていた歯の美容習慣
歯に装飾を施す行為自体は、古くから世界各地に存在します。比較的近年の例では、1980年代にヒップホップカルチャーと共にアメリカで流行した「グリル」(歯に被せるアクセサリー)が挙げられます。しかし、さらに遡ると、アジアを中心に世界各地で「歯を黒く染める」習慣が広く見られました。英国のカルチャー誌「デイズド」の解説によると、この習慣は何世紀にもわたり、中国、日本、タイ、ベトナム、さらにはペルー北部やエクアドルの一部といった多様な文化圏で受け継がれてきました。
特に日本では、鉄粉と酢を混ぜた液体で歯を黒く染める「お歯黒」が11世紀頃から存在し、高貴さや既婚女性の証とされました。ベトナムの「ヌーム・ザン・デン」(お歯黒)に至っては、紀元前2879年から258年の時代にまで遡るとされ、その歴史の深さがうかがえます。これらの歯を黒くする習慣は、単なる装飾だけでなく、虫歯予防や口腔衛生の観点からも実用的な意味合いを持っていたと考えられています。
西洋の美意識がもたらした伝統の衰退
しかし、こうした歴史ある歯の黒染め文化も、時代の流れの中で次第に廃れていきました。米ブランダイス大学の美術史教授であるアイダ・ユエン・ウォン博士は、「サウス・チャイナ・モーニング・ポスト」紙に、日本とベトナムの例を挙げて、歯を黒く染める文化が「どちらの場合も植民地時代に西洋の美の基準が押し付けられたことでほぼ消滅した」と語っています。
ベトナムでは、フランスの植民地支配が新たな美の基準をもたらし、伝統的な歯の黒染めは旧弊なものと見なされるようになりました。日本は植民地化されませんでしたが、近代化の波の中で政府当局が西洋の理想に合わせるよう奨励し、「野蛮な印象を与えたくない」という意図から、この習慣を禁止する動きが起こりました。これにより、数世紀にわたって続いてきた伝統的な歯の美容習慣は、社会から姿を消していったのです。
現代アーティストが問いかける美の多様性
現代社会で「白い歯」が普遍的な美の基準とされる中、セイラーをはじめとするアジア系アーティストたちが「黒い歯」を再び提示する行為は、単なるノスタルジーに留まりません。それは、画一化された美意識への問いかけであり、多様な文化に根ざした美の価値を再発見し、個々のアイデンティティを表現する力強いメッセージとなっています。この動きは、歴史の中で失われた文化的伝統を現代に甦らせる試みであり、グローバル化が進む現代において、自身のルーツを再評価し、未来へと繋げていく新たな潮流を示唆していると言えるでしょう。
参考文献
- サウス・チャイナ・モーニング・ポスト (South China Morning Post)
- デイズド (Dazed)
- クーリエ・ジャポン (COURRiER Japon)