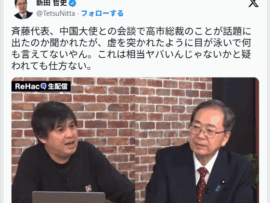1995年に順天堂大学で日本初の便秘外来を開設した小林弘幸医師は、体の老化を早める「活性酸素」を抑制する「サビない腸活」を提唱します。この画期的な腸活の鍵は、従来の「善玉菌」や「乳酸菌」「ビフィズス菌」といった菌群ではなく、意外にも腸内の「日和見菌」が持つ水素産生能力にあるとされています。知られざる日和見菌の力が、私たちの腸内環境と健康維持に新たな可能性をもたらすかもしれません。
「サビない腸活」実現への多角的アプローチ
多くの人が考えるように、食物繊維やお酢を摂取するだけでは、活性酸素の害を完全に防ぎ、体の「サビ」を落とすことはできません。日本人の食物繊維摂取量は全体的に不足しがちなため、日々の食事で野菜や海藻、きのこなどを意識して取り入れることは非常に重要です。しかし、「サビない腸活」を本当に実現するには、「どんな栄養バランスで食事をすればいいのか」「糖質制限はしたほうがいいのか、しないほうがいいのか」といった、まだクリアすべき複数の課題が存在します。腸内に「水素」を増やして活性酸素を減らしていくためには、単一の要素に頼るのではなく、これらのハードルを全てクリアし、生活習慣として定着させる総合的なアプローチが不可欠なのです。
 日和見菌が鍵を握る、加齢とともに気になる腸内環境と活性酸素
日和見菌が鍵を握る、加齢とともに気になる腸内環境と活性酸素
腸内細菌の基礎知識と「水素産生菌」への注目
では、具体的にどのような腸活が求められるのでしょうか。ここでまずスポットライトを当てるべき存在が「水素産生菌」です。腸内細菌は、善玉菌(有用菌)、悪玉菌(有害菌)、そして日和見菌の三つのグループに大別されます。一般的に、腸内環境をよくしていくには善玉菌を増やし、悪玉菌を減らすことが良いと広く知られています。しかし、小林医師が提唱する「サビない腸活」においては、特に日和見菌が持つ水素産生能力が、活性酸素対策の鍵を握るとされています。この日和見菌の働きを最大限に引き出すことが、次世代の腸活の中心となるでしょう。
結論
小林医師の提唱する「サビない腸活」は、食物繊維の摂取といった従来の腸活に加えて、日和見菌の水素産生能力に注目することで、活性酸素による体のサビを防ぎ、健康的な未来を築く新しいアプローチです。従来の腸活とは異なるこの視点を取り入れ、栄養バランスや生活習慣全体を見直した総合的な腸内環境ケアを実践することが、健康寿命を延ばす上で不可欠な鍵となるでしょう。