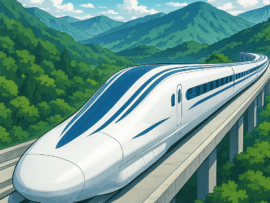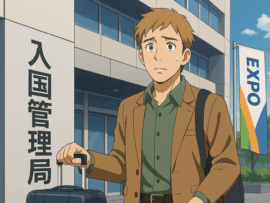自民党の稲田朋美衆院議員(66)は、2005年の初当選以来、防衛相や政調会長といった要職を歴任してきました。かつて森喜朗元首相の女性蔑視発言に対し、「私は『わきまえない女』でありたい」とSNSで発信した経験を持つ稲田氏は、現在の自民党における女性議員の状況、そして結党70周年を迎える党そのものについて、独自の視点から語ります。女性活躍が叫ばれる一方で、自民党内の女性衆院議員が直面する現実とは何でしょうか。
自民党衆院議員に女性が少ない現状と「女性議員飛躍の会」の提言
安倍晋三元首相が「女性活躍」を掲げたにもかかわらず、自民党の衆院議員における女性の割合は依然として低いのが現状です。参院議員では女性の比率が高いものの、衆院議員に限定すると、男性177人に対し女性はわずか19人と、野党と比較しても少ない数字にとどまっています。この状況を改善するため、自民党女性議員による議連「女性議員飛躍の会」が立ち上げられ、様々な提言を行ってきましたが、その多くは党内でなかなか受け入れられていないと稲田氏は指摘します。
具体的な提言の一つとして、衆院の比例ブロック(北海道や東北など全国11ブロック)のうち3つ程度に「純粋1位」の新人女性候補者を配置することで、新人女性議員を3人増やす案が挙げられました。また、党内の比例新人候補者選定時に、迷った際には女性候補者を選ぶといった方法も模索されています。しかし、これらの改革案の実現には高い壁が存在しているようです。
 稲田朋美衆議院議員、自民党内での女性活躍推進と直面する課題について語る
稲田朋美衆議院議員、自民党内での女性活躍推進と直面する課題について語る
小泉政権下の「刺客」当選から20年:増えない女性衆院議員の現実
小泉純一郎元首相による郵政解散後の総選挙では、稲田氏自身を含む26人の女性が衆院議員として初当選しました。これは、小泉元首相の明確な意向により、多くの女性候補者が当選確実な比例区の上位に登載されたためです。しかし、2009年に自民党が下野した際、多くの女性議員が落選し、その後の選挙でも数は回復していません。稲田氏が政界入りしてから20年が経った現在、自民党の女性衆院議員は増えるどころか、むしろ減少していると語ります。
女性が候補者として選ばれるのは、党が危機的な状況にあるか、あるいは「異常事態」と見なされるケースが多いと稲田氏は自身の経験を交えて分析します。彼女自身も小泉政権時、郵政民営化に反対した福井1区の松宮勲氏への「刺客」として選ばれました。もし「平時」であり、弁護士として活動しているだけであったならば、候補者に選ばれることはなかっただろうと述懐します。これは、男性中心の政治文化が、女性の新たな参入を阻む一因となっていることを示唆しています。
「男社会」で「わきまえない女」が直面する困難
一度当選した女性議員が政治の世界で生き残り続けることもまた困難を伴います。稲田氏は、「取って代わろう」とする勢力との闘いが常に始まることを指摘します。そもそも女性は「男社会」特有の「暗黙の空気」を汲み取ろうとしない傾向があり、稲田氏自身も「なぜそんな古いことを言っているのだろう」と感じ、それを口にしてしまうことが度々あったと言います。
突出した行動を取ったり、思ったことを率直に述べたりすると、「わきまえていない」と見なされ、「あいつはダメだ。取って代わろう」という動きに繋がってしまう現実があるのです。稲田氏は、「ようやく、自分の行動が男社会では受け入れられなかったとわかるようになった」と振り返りますが、それは時間が経たないと気づけないものであり、ほとんどの女性議員は、それに気づく前に落選してしまうと語り、自民党内の構造的な課題を浮き彫りにしています。
結論
稲田朋美氏の語りからは、自民党が女性議員の登用と定着において、未だ多くの課題を抱えている実態が明らかになりました。「女性活躍」のスローガンは掲げられつつも、その実現には党の体質や男性中心の文化を根本から変革する必要があることを強く示唆しています。比例候補者の選定基準の見直しや、女性議員が声を上げやすい環境の整備など、「女性議員飛躍の会」が提言する具体的な改革が、今後の自民党の未来、ひいては日本の政治の多様性を左右する重要な鍵となるでしょう。