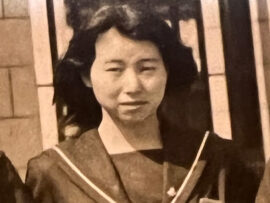愛知県豊明市で、スマートフォン(以下スマホ)の利用を「1日2時間まで」と呼びかける条例案が全国で初めて可決される動きを見せています。「豊明市スマートフォン等の適正使用の推進に関する条例」と名付けられたこの条例に対し、小浮正典市長は8月20日の記者会見で、「スマホ利用を社会問題として市民に考えてもらいたい」と発言しました。8月25日の議会で可決されれば、10月1日から施行予定ですが、罰則は設けられていません。この異例の条例案は、市民や教育関係者の間で困惑と議論を巻き起こしています。
豊明市、全国初のスマホ利用制限条例案を可決へ
豊明市が提案するこの条例案は、市民のスマートフォン利用時間について具体的な目安を設けるもので、特にその「1日2時間」という数字が注目を集めています。罰則がない理念条例であるものの、行政が市民の日常生活におけるデバイス利用に踏み込む姿勢は、多くの議論の的となっています。市は、単なる時間制限ではなく、市民がスマホとの向き合い方を改めて考えるきっかけを提供したいと考えているようです。
SNSでの反響と市の説明:「家庭での話し合いのきっかけに」
この条例案の報道を受け、X(旧Twitter)では「愛知県豊明市」「条例案提出」といったキーワードがトレンド入りし、さまざまな意見が飛び交いました。「今さら感がある」「子どもには良い条例かもしれない」「他に決めることないのか?」といった賛否に加え、「スマホは1日2時間って“高橋名人”かよ」という、かつてのゲーム時間制限を連想させるコメントも多く見られました。
 愛知県豊明市のスマートフォン利用制限条例案に関する議論で、高橋名人の名が挙がる背景
愛知県豊明市のスマートフォン利用制限条例案に関する議論で、高橋名人の名が挙がる背景
豊明市生涯学習課の担当者は、条例案提出の経緯について以下のように説明しています。今年7月から運営を開始した「重層支援センター」に、不登校や生活困窮といった福祉の狭間にいる人々からの相談で、スマホやタブレットに関する事例が数件寄せられたことが、小浮市長が提案するきっかけとなりました。
担当者は、反響の大きさに戸惑いつつも、条例の真意を解説しました。対象を子どもだけでなく市民全体としたのは、健康と睡眠への悪影響に関する注意喚起のためであると強調。また、「2時間」という数字は、厚生労働省の睡眠時間ガイドラインなどを参考に、日本人の1日の「余暇時間」が約2時間であることから、それ以上の時間をスマホに費やすと健康や睡眠に影響が出る場合がある、という目安として盛り込まれたとのことです。
教育機関での使用、家族や友人とのゲーム、仕事での使用は対象外であるとしつつ、担当者が最も伝えたいのは「2時間」という数字そのものではないと言います。「スマホとの向き合い方や使う時間を、家庭内で話し合うきっかけ作りになれば、ということが大きいのです。子どもが使い放題では学習や健康面でも影響が出ますし、それは大人においても同じです」と述べ、この発表以降、「よく出してくれた」という肯定的な意見もあれば、「家庭の領域にどこまで踏み込むのか」という批判的な意見も聞かれていることを明らかにしました。
教育現場からの視点:現実との乖離
豊明市内の小学校に勤務する男性教諭は、このニュースを見て「正直、行政が口出すことではないと感じました」と苦笑いを浮かべます。保護者からスマホに関するトラブルの相談を受けることはあるものの、タブレットは別として、スマホは学校ではなく家庭で与えられているものであるため、学校側が指導に深く入り込むことは難しいのが現状だと指摘。一律の指導はできない上、「使用ルールをしっかり約束しましょう」と言っても、すでに普及しきっている現状では「いまさら遅い」と感じているようです。市の単位で規制を呼びかけても大きな変化は期待しにくいとしながらも、家庭内でスマホを与える際に詳細なルール作りをすることの重要性は認めています。
また、豊明市内の学習塾講師は、この条例案を「時代錯誤だ」と評しています。現在、学校や塾では教材の配信や学習ツールとしてスマホやタブレットの利用が増加しており、進学校を目指す生徒たちは余暇時間を勉強に充てているため、この条例は「とても現実的ではない」と断言しました。生徒の保護者たちは、アプリごとに制限時間を設けるなど、各家庭で独自のルールを設けているのが実情であり、強制力のない条例を行政が制定することに「なんの意味があるのか疑問」を呈しています。
罰則なき条例の意義と課題
豊明市のスマートフォン利用制限条例案は、罰則がない理念条例という特性上、その実効性には疑問符が投げかけられています。一方で、行政が社会問題としてスマホの過度な利用に警鐘を鳴らし、市民、特に家庭内でこの問題について議論するきっかけを提供しようとする意図は理解できます。しかし、現代社会においてスマートフォンが生活のあらゆる側面に深く浸透している中で、一律の時間制限というアプローチがどれほどの共感と行動変容を促せるのかは大きな課題です。技術の進化とともに、デバイスとのより健全な共存方法を模索する中で、豊明市の試みは今後の地方自治体における政策議論に一石を投じることになるでしょう。