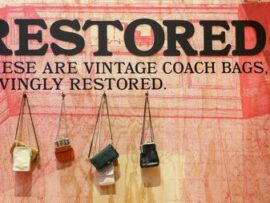LINEヤフー社が「出社回帰」の方針を打ち出したことで、在宅ワークが定着していた企業や従業員の間で波紋が広がっています。かつてリモートワークの推進を牽引してきた同社の方針転換は、日本の働き方の将来において、リモートワークが縮小していく可能性を示唆しているとも受け止められています。この動きは、従業員にどのような影響を与え、また法的な観点からはどのように評価されるのでしょうか。
リモートワーク先進企業からの方針転換
LINEヤフーの前身であるヤフー社が全社員を対象としたリモートワークに移行したのは2020年10月のことでした。この際、約95%の社員が「ほぼフルリモート」勤務となり、恒久的な制度として導入されたことで、同社はリモートワークの先進企業として注目を集めました。それまでの「原則出社」が常識だった日本の企業文化に、新たな働き方を提示した点で大きな意味を持ちました。
しかし、約5年の歳月を経て、同社は「出社回帰」を打ち出し、2024年4月からは従業員に対し「週1回」や「月1回」の出社を義務付け、事実上“フルリモート”を原則廃止しています。全社的にテレワークを推奨してきた企業の大幅な方針転換は、当然ながら社員からの反発を招き、労使間で軋轢が生じていると報じられています。
 「出社回帰」に直面し、リモートワーク継続を望むLINEヤフー社員の姿
「出社回帰」に直面し、リモートワーク継続を望むLINEヤフー社員の姿
「出社強制」は法的に問題ないのか?弁護士の見解
こうした状況において、企業が一方的に「出社強制」を行うことが法的に許されるのかという疑問が生じます。労働問題に詳しい向井蘭弁護士は、企業には労働契約に基づき従業員の勤務場所を決定する権利(業務命令権・配転命令権)があるため、原則として、労働契約や就業規則に勤務場所が特定の事業所と定められていれば、企業は従業員に出社を命じることができると説明しています。
ただし、向井弁護士は勤務場所の「限定合意」の有無によって対応が異なると補足しています。もし採用時に「勤務場所は自宅とする」「フルリモート勤務とする」といった明確な合意が労働契約書などに明記されている場合、これは「勤務場所の限定合意」と解釈され、企業が一方的に出社を義務付けることは契約違反となります。この場合、従業員の個別的な同意がなければ強制はできません。
一方で、コロナ禍のような事情により暫定的にテレワークが導入され、明確な合意がなかったケースでは、業務上の必要性があれば企業は出社を命じることが可能です。しかし、この場合でも、フルリモートを前提として発生した従業員の経済的負担(通勤費、転居費用など)を軽減するための補填が必要となる可能性があります。さらに、育児や介護など、出社が著しく困難な個別事情を持つ従業員に対しては、企業側に配慮が求められるとしています。
LINEヤフー社の子会社に勤務していた元社員のY氏の証言によると、「親会社がフルリモートの会社として知られていたために入社した人もいたと思うが、社員と会社側で“明確な合意”はなかった記憶」とのことです。現実的に、従業員が企業とフルリモートに関する「明確な合意」を個別に結ぶことは稀であり、多くの場合、会社の方針に従わざるを得ない状況にあると考えられます。
まとめ
LINEヤフー社の「出社回帰」は、リモートワークが定着した日本の企業文化において、働き方の未来を問い直す動きとして大きな注目を集めています。法的な観点からは、企業には従業員の勤務場所を決定する権利があるものの、「勤務場所の限定合意」の有無、および従業員の個別事情への配慮が重要となります。リモートワークから原則出社へのシフトは、労働市場における企業と従業員の関係性、そして新しい働き方のあり方をめぐる議論に一石を投じることになるでしょう。