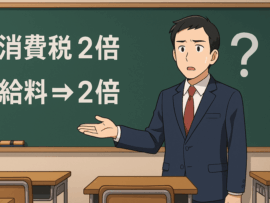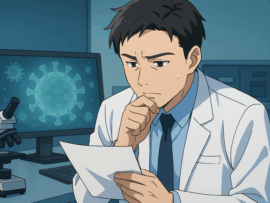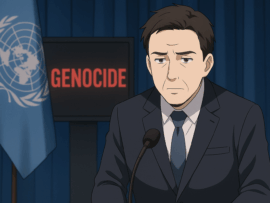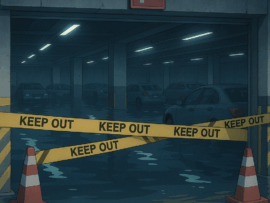日本の象徴である皇室に関する国家事務を一手に担う宮内庁。その最高責任者である宮内庁長官がどのような職務を遂行し、天皇とどのように向き合ってきたのかは、多くの人々の関心事です。特に、ジャーナリスト井上亮氏の著書『宮内庁長官 象徴天皇の盾として』(講談社現代新書)では、初代宮内庁長官を務めた田島道治氏が昭和天皇から直接聞き取った「生の言葉」が紹介されており、その歴史的価値が改めて注目されています。
天皇の真意を探る:側近の記録と情報伝達の困難さ
天皇陛下が普段どのような会話を交わし、どのような考えをお持ちであるのか。その真意に迫るためには、陛下に直接接した人々の証言が貴重な手がかりとなります。しかし、天皇という特別な立場への配慮から、その対話がそのまま外部に語られることは極めて稀であり、必然的に「公式答弁」に留まる傾向にあります。
天皇の「生の言葉」、すなわち包み隠さない「ホンネ」が表れるのは、聞いた本人が公表を意図せず正直に書き留めた日記、備忘録、メモなどの非公式な記録です。昭和天皇に関するそうした記録としては、戦前の侍従武官長・本庄繁、内大臣・木戸幸一、侍従・小倉庫次、そして戦後には侍従次長・木下道雄、侍従長・入江相政、侍従・卜部亮吾といった、多くの側近の日記が出版されており、私たちはそこから天皇の人間性や、さまざまな事象に対するお考えを知ることができます。これらの側近による日記類は、日本の近現代史において欠かせないキーパーソンである天皇の心の内を垣間見ることができる、第一級の歴史資料とされています。
 1969年、皇居新宮殿長和殿ベランダから一般参賀に臨む昭和天皇ご一家。象徴天皇としての活動の一場面。
1969年、皇居新宮殿長和殿ベランダから一般参賀に臨む昭和天皇ご一家。象徴天皇としての活動の一場面。
「オモテの長」宮内庁長官の記録:田島道治の『昭和天皇拝謁記』の衝撃
上記のような「オク(奥)」に仕える側近による記録が多い中、「オモテ(表)」の最高責任者である宮内庁長官の日記やメモ類で世に出ているものは、これまで初代の田島道治氏と昭和末期の富田朝彦氏の二例しかありませんでした。この事実は、日常的に天皇に接する「オク」の人間だからこそ聞き取れることがある、という先入観を抱かせがちでした。
しかし、2021年12月から岩波書店より全7巻で刊行が始まった田島道治氏の備忘録、日記、資料群『昭和天皇拝謁記』は、その先入観を大きく覆しました。この詳細な記録は、田島長官が昭和天皇と日々行った会話の内容を克明に記しており、天皇の真意や当時の時代背景、政治状況に対する見解が鮮明に浮かび上がります。長官という立場から聞き取られた天皇の「生の言葉」は、これまでの歴史認識を深め、象徴天皇制の確立期における皇室のあり方を多角的に理解するための、貴重な一次史料として、学術界のみならず一般の読者からも大きな注目を集めています。
結論
宮内庁長官の職務は、皇室の日常を支えるだけでなく、天皇の真意を理解し、適切に内外に伝えるという、極めて重要な役割を担っています。特に、初代宮内庁長官・田島道治氏が残した『昭和天皇拝謁記』は、これまでの側近による記録と並び、いやそれ以上に、昭和天皇の人間像や激動の時代における思慮を深く探る上で不可欠な歴史資料であることが明らかになりました。この記録は、日本の近現代史研究に新たな視点をもたらし、象徴天皇制の意義を再考する上で多大な貢献をすると言えるでしょう。
参考資料
- 井上亮『宮内庁長官 象徴天皇の盾として』講談社現代新書
- 『昭和天皇拝謁記』岩波書店
- Yahoo!ニュース (https://news.yahoo.co.jp/articles/097a6e4f6d274a870d00a9c2e5a59e556b51a815)