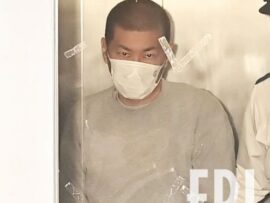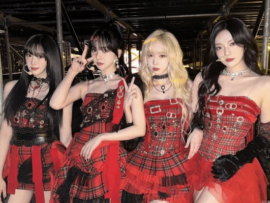米国の大学に在籍する一人の学生が、真面目に取り組んだ課題にもかかわらず、AI使用の疑いをかけられ0点という衝撃的な通知を受け取りました。この出来事は、教育現場における生成AIの急速な普及と、それに伴う新たな課題、特にAI検出ツールの信頼性という問題に光を当てています。本稿では、無実の学生が「AIを使っていない」ことを自ら証明しなければならない現状と、教育現場におけるAI利用の光と影について深掘りします。
誤検出された「AI生成」:リー・バーレルのケース
ヒューストン・ダウンタウン大学でコンピュータサイエンスを専攻するリー・バーレル(23)は、2年生の時、必修ライティング課題で0点を告げられ、心臓が止まるような思いをしました。教授からのメモには、課題の一部がAIによって書かれたものと判断された、と記されていました。しかし、この課題はAIチャットボットが生成したものではなく、米紙「ニューヨーク・タイムズ」が確認したGoogleドキュメントの履歴によれば、バーレルは2日間かけて下書きと修正を繰り返していました。彼女の課題をAIによるものと判断したのは、AI生成テキストを特定するサービス「ターニティン」でした。
バーレルはパニックに陥りながらも異議を申し立て、執筆過程のスクリーンショットやメモをまとめた15ページのPDFファイルを学科長に提出。その結果、彼女の成績は回復しましたが、この出来事を通じて、AIによる不正行為が問題視される学術界において、学生として直面する危険性を痛感したと言います。AI検出システムの誤検出は、真摯に学習に取り組む学生に不当な評価をもたらし、学業に深刻な影響を及ぼす可能性があります。
 AIによる課題の不正利用を疑われ困惑する学生
AIによる課題の不正利用を疑われ困惑する学生
生成AIが変える教育現場と教師の模索
ChatGPTに代表される生成AIは、教育環境を大きく変革しつつあります。ピュー・リサーチ・センターが2024年に行った調査によると、10代の若者の26%が学校の課題にChatGPTを使用した経験があり、これは前年比で2倍に増加しています。学生がAIを使ってエッセイ作成やプログラミング問題の解決を行うようになるにつれ、教師たちはその対策に頭を悩ませ、新たな教育方法や評価基準の模索を続けています。
一方で、AIによる不正行為を根絶するために導入されているAI検出システム自体がまだ不完全であり、ルールを遵守している学生にまで予期せぬ影響を与えかねないという問題が浮上しています。このような状況は、AI技術の発展と教育現場の対応との間に大きなギャップがあることを示唆しており、その解決が急務となっています。
「無実の証明」を迫られる学生たちの自衛策
ニューヨーク・タイムズのインタビューでは、高校生、大学生、大学院生たちが、自身で作成した課題であるにもかかわらずAIを使ったと指摘されることへの不安や、それが学業に重大な影響を与える可能性を懸念している実態が明らかになりました。こうした不安に対処するため、多くの学生が課題中の記録を残すという「自己防衛」策を講じています。課題に取り組むPC画面を何時間も録画する学生や、詳細な編集履歴が残るワープロソフトのみを使ってレポートを作成する学生も少なくありません。
実際に、AI使用を指摘されたライティング授業で別の課題を提出しなければならなかった際、バーレルは作業中のPC画面を記録した93分のYouTube動画をアップロードしました。彼女は「面倒でしたが、心の平穏のためには必要でした。無実の罪で成績が下がるのではないかと、とても不安でした」と語っています。これは、AI検出の不確実性が、学生に過度な負担と精神的なストレスを与えている現状を浮き彫りにしています。教育機関は、AIとの共存を模索しつつ、学生が安心して学べる環境を整備するため、より公正で信頼性の高い評価システムを確立する必要があるでしょう。
参考文献
- 米紙「ニューヨーク・タイムズ」
- ピュー・リサーチ・センター 2024年調査
Callie Holtermann