日本社会の未来を担う子どもたちの間で、深刻な危機が進行しています。2024年の小中高生の自殺者数は529人に達し、過去最多を記録しました。新型コロナウイルス感染症の流行下で一度は増加に転じた全体の自殺者数が減少する一方で、子どもの自殺者数は2020年以降、500人前後で高止まりしている状況です。長年にわたり自殺対策に尽力してきたNPO法人「自殺対策支援センターライフリンク」代表の清水康之氏は、「日本社会の未来そのものが危機に瀕している」と、この看過できない事態の深刻さを強く訴えています。
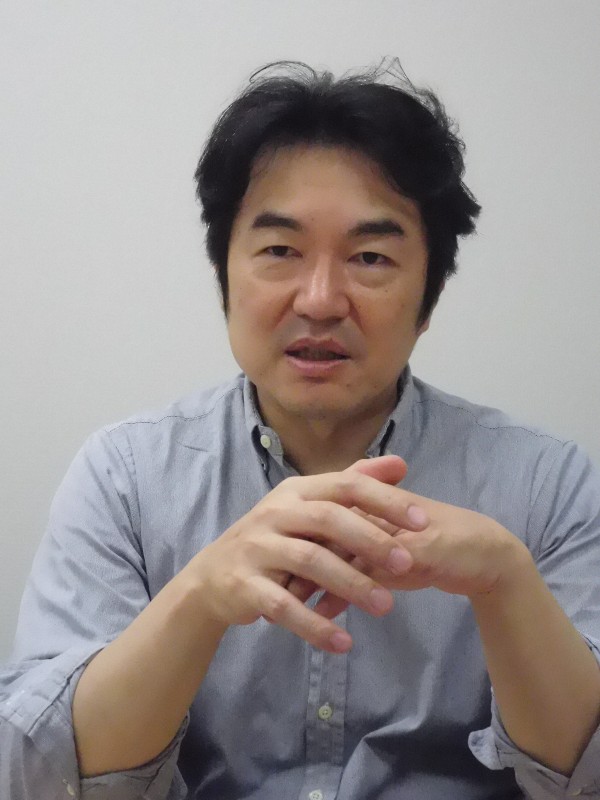 NPO法人ライフリンク代表、清水康之氏が子どもの自殺対策について語る様子
NPO法人ライフリンク代表、清水康之氏が子どもの自殺対策について語る様子
終わらない「子どもの自殺」の深刻な現状
清水代表は、年間500人という数字が「毎週10人の子どもが命を落としている」という事実を意味すると指摘し、その衝撃的な現実を強調します。亡くなる子どもたちだけでなく、「死にたい」「消えたい」と願う多くの子どもたちが存在するといいます。自殺者数は1990年代前半から増加傾向にありましたが、近年、そのペースは一気に加速しました。
自殺の要因は多岐にわたりますが、社会的な背景として特に注目されるのが、交流サイト(SNS)の普及です。SNSによって常に他者の目を意識せざるを得ない環境が生まれ、子どもたちが安心できる時間や人間関係が失われつつあります。これにより、子どもたちの危機感が一層加速している側面があると考えられます。子どもたちは社会の未来そのものであり、彼らの抱える危機は、まさに日本社会の未来の危機に直結する深刻な問題です。
不十分な国の対策と圧倒的な危機感の欠如
政府の自殺対策は進んでいるのでしょうか。2024年6月には自殺対策基本法が改正され、子どもの自殺対策が強化される方向へと舵が切られました。これまでの学校と地域社会の連携不足が大きな課題でしたが、今後はこども家庭庁、文部科学省、厚生労働省が緊密に連携協力し、問題解消を目指します。また、2026年度からは全国の自治体で、学校、児童相談所、医療機関、民間団体など子どもに関わる組織が守秘義務のもとで情報を共有し、連携する協議会の設置が可能になります。
しかし、清水代表は、「子どもが『死にたい』『消えたい』と思わずにすむ社会を作るという意味では、対策がまったく足りていない」と断言します。子どもの自殺対策を進めるための国や自治体の予算、人材が不足しているだけでなく、何よりもこの問題に対する社会全体の危機感が圧倒的に足りないと強く感じていると述べました。
「死を想え」をテーマにしたイベントで、子どもの命を支えることの重要性を訴える参加者たち
相談できない子どもたちのための新たな「居場所」:ライフリンクの試み
「死にたいくらいつらい気持ちになったらぜひ相談して」。ライフリンクはこれまで、子どもたちにそう呼びかけてきました。しかし、現実にはライフリンクを含む多くの自殺防止相談窓口が「パンク状態」にあり、相談したくても繋がれない子どもたちが大勢います。
そこで、相談できるか否かの二択にとどまらない新たな選択肢として、ライフリンクは昨年から「かくれてしまえばいいのです」というオンラインの居場所事業を始めました。これは、この世から消えたいと思った時に「消えてしまわなくても大丈夫、隠れてしまえばいいのです」と呼びかけるものです。絵本作家のヨシタケシンスケ氏の全面協力を得て立ち上げられたこのサイトは、相談すらしたくないと感じている子どもにとっても、安心できる「居場所」となることを目指しています。「この世」で生きるのが苦しいからといって「あの世」に行く必要はなく、自殺以外の具体的な選択肢として「その世」を創り出すという画期的な試みです。
見過ごされがちな「ノーマークの子」たちの現実
清水代表が代表理事を務める一般社団法人「いのち支える自殺対策推進センター」は、子どもの自殺の要因分析を行っています。その分析から明らかになったことの一つが、実は「ノーマークの子」が多く自殺で亡くなっているという衝撃的な事実です。
2023年度、こども家庭庁の委託事業として行われた分析では、過去5年間に自殺で亡くなった小中高生272人の学校の出席状況を調査。その結果、「以前と変わりなく出席」していた子どもが44%にも上ることが判明しました。「不登校または不登校傾向」の子どもが10%であることと比較すると、その4倍以上です。このデータは、自殺の多くが周囲にとって「まさか」という状況で発生していることを改めて浮き彫りにしています。表面的な兆候だけでは見えない、子どもたちの心の内に潜む苦しみに、社会全体が目を向ける必要性を示しています。
生きている子どもたちの声に耳を傾ける重要性
要因分析の報告書では、「生きている子どもたちの声を聞く意義」も指摘されています。亡くなった子どもの情報からは、その子が抱えていた幼少期の体験、自殺行動に至った時の感情、そしてどのような支援があれば生きる道を選べたのかといった、重要な情報が分からないことがあります。
対策や支援をより効果的なものにするためには、こうした情報が不可欠です。そのため、今回は亡くなった子どもだけでなく、ライフリンクに寄せられた子どもたちの相談内容なども分析されました。その結果、家庭に悩みを抱える子どもが多いことや、自己嫌悪や自責の念に苦しむ子どもが多いことなどが明らかになってきています。これは、多角的な視点から子どもの「生きづらさ」を理解し、より包括的な支援を構築するための重要な一歩となります。
大人たちに求められる行動:事実を知り、関心を持つこと
では、私たち大人はこの深刻な問題に対して何ができるのでしょうか。清水代表は、まず「子どもの自殺について事実を知ること」が重要だと訴えます。事実を知れば、私たちの社会でいま起きていることに驚き、何とかしなければという危機感を持つ人が増えるはずだと語ります。
逆に言えば、そうした危機感を持つ大人がもっと増えない限り、今の状況を改善するためのさらなる対策を進めることは困難です。子どもは社会の未来そのものであり、日本社会の未来が危機に瀕しているという認識が不可欠です。私たちの日常と子どもの自殺の問題は「地続き」であることを理解し、一人でも多くの大人がこの問題に関心を持つことが、社会的な対策を推し進める原動力となるでしょう。日本の未来を守るため、大人が事実を認識し、この問題に深く関心を持つことの喫緊の必要性が今、改めて問われています。
不安や悩みの主な相談窓口
- #いのちSOS
- 電話:0120-061-338
- 時間:24時間受け付け
- いのちの電話
- 電話:0120-783-556
- 時間:毎日午後4時~9時受け付け
- チャイルドライン
- ウェブサイト:https://childline.or.jp/chat
- 電話:0120-99-7777
- 時間:毎日午後4時~9時受け付け
- 生きづらびっと
- ウェブサイト:https://yorisoi-chat.jp/
- LINE:@yorisoi-chat
- 時間:毎日午前8時~午後10時受け付け
- あなたのいばしょチャット相談
- ウェブサイト:https://talkme.jp/
- 時間:24時間365日対応






