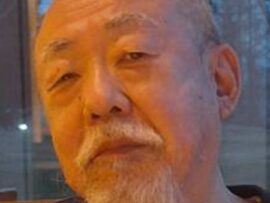2025年8月22日から25日にかけて、第9回アフリカ開発会議(TICAD 9)が横浜で開催されました。日本が主催し、国連や世界銀行が共催するこの重要な国際会議は、アフリカの経済発展と人類発祥の地としての重要性に注目が集まる中で、回を重ねるごとにその重みを増しています。会議期間中、皇居では天皇皇后両陛下がアフリカ各国の首脳夫妻らを招き茶会を催されました。この場には愛子内親王をはじめとする女性皇族方も出席され、皆さま和服姿でいらっしゃいました。特に、愛子内親王が各国の国王夫妻に対して膝を落として挨拶し、深い敬意を示された姿は印象深く報じられ、皇室の伝統的な装いが国際親善の舞台で果たす役割が改めて注目されています。皇室の正装には洋装と和装があり、その使い分けや歴史的背景、そして女性皇族の和装が持つ意味合いは多岐にわたります。
 第9回アフリカ開発会議(TICAD 9)における天皇皇后両陛下、愛子内親王、秋篠宮ご夫妻ら皇族方の茶会でのご歓談風景。
第9回アフリカ開発会議(TICAD 9)における天皇皇后両陛下、愛子内親王、秋篠宮ご夫妻ら皇族方の茶会でのご歓談風景。
皇室外交における和装の重要性
天皇や皇族による「皇室外交」は、日本の国際関係において極めて重要な役割を担っています。特にアフリカ各国とは密接な関係が築かれており、その歴史には多くの交流の記録があります。例えば、現在の天皇陛下は皇太子時代、2013年にネルソン・マンデラ元大統領が逝去した際には南アフリカを訪問し、追悼式に参列されました。翌年には、日本とザンビアの外交関係樹立50周年を記念し、秋篠宮ご夫妻がザンビアとタンザニアを訪問されています。愛子内親王も昨年2月にはケニア大統領夫妻を招いての昼食会に参加され、外国要人との国際親善の場への公式デビューを果たされました。
皇室外交の場において、女性皇族の着物姿は常に国内外の注目を集めます。皇族の皆さまは、それぞれの訪問先や状況に応じて、着物の柄や色選びに細心の注意を払われます。海外を訪問する際には、訪問国の国旗の色や、両国の友好関係を象徴する花をモチーフにした柄が選ばれることもあり、これは日本の文化を紹介しつつ、相手国への敬意を示す繊細な外交の手段となっています。着物が日本の美意識と伝統を体現する「外交の武器」として機能していると言えるでしょう。
皇族の装束:洋装と和装、そして十二単の歴史
皇室の礼装は、明治時代以降、西洋列強と肩を並べるために洋装が導入され、宮中の公式な場での正装として位置づけられました。しかし、現在でも「結婚の儀」や一部の伝統的な儀式においては、和装が揺るぎない正装として用いられています。特に、女性皇族がまとう「十二単(じゅうにひとえ)」は、その華麗さと歴史的重みから「別格」と評される伝統衣装です。宗教学者であり皇室史に詳しい島田裕巳氏は、この和装と洋装の使い分けについて言及し、日本の伝統が現代の皇室にも深く息づいていることを指摘しています。
 1993年、「結婚の儀」で伝統的な十二単を着用された皇太子妃雅子さま(現・皇后陛下)と皇太子徳仁親王(現・天皇陛下)。
1993年、「結婚の儀」で伝統的な十二単を着用された皇太子妃雅子さま(現・皇后陛下)と皇太子徳仁親王(現・天皇陛下)。
日本の伝統衣装「着物」のルーツ:古代中国からの影響
着物は、日本に独自の発展を遂げた衣装ですが、その起源をたどると古代中国からの影響が色濃く見られます。着物が「呉服(ごふく)」と呼ばれることにも、その歴史が示されています。「呉」とは古代中国の国名であり、そこから伝わった織り方の布帛(ふはく)、つまり織物のことを指していました。
中国の服装文化に関する情報は、遣隋使や遣唐使を通じて日本に伝えられました。当時の中国の服装は上衣と下衣に分かれており、袖もゆったりとしたデザインが特徴でした。奈良時代や平安時代の日本の貴族も、こうした中国風の服装を取り入れていました。その後、日本の気候や文化に合わせて独自の進化を遂げ、現代に通じる着物の形が確立されていきます。この長い歴史と文化的な背景が、今日の皇族の和装に深い意味を与えているのです。
結論
TICAD 9での女性皇族の和装は、単なる美しい衣装以上の意味を持っていました。それは、日本の豊かな歴史と文化、そして国際社会における皇室の役割を象徴するものであったと言えるでしょう。明治以降の洋装化の流れの中でも、伝統的な和装は「結婚の儀」などの重要な儀式や、今回のような国際親善の場で、日本のアイデンティティを示す強力な手段として受け継がれています。古代中国からの影響を受けつつ独自の発展を遂げた着物は、まさに「生きた文化遺産」として、世界中の人々を魅了し続けています。皇室外交における和装の存在は、日本の伝統が現代においていかに重要であり、未来に向けて受け継がれていくべきものであるかを、私たちに改めて教えてくれています。
参考文献:
- PRESIDENT Online:『皇室の正装「十二単」はなぜ別格なのか…歴史宗教学者が解説する「和装と洋装」の決定的な違い』 (https://president.jp/articles/-/101404)
- 共同通信社
- Yahoo!ニュース (https://news.yahoo.co.jp/articles/c28be1a168fa93e7468159c8e35b0f2f49c590d0)