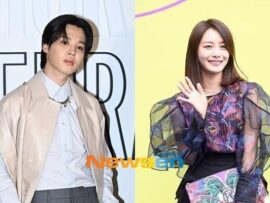ウクライナ侵攻が3年半を迎え、膠着状態が続く中、米アラスカ州アンカレジで実現したトランプ前米大統領とプーチン露大統領の会談は、新たな情勢展開の可能性を示唆している。共同通信=太田清の取材に応じた北海道大学スラブ・ユーラシア研究センターの服部倫卓教授は、この会談を機としたロシア側の和平条件提示や、ウクライナ側の反応、そして今後の見通しについて詳細な分析を行った。本稿では、この専門家の見解に基づき、ロシア・ウクライナ情勢の深層と、和平交渉における両国の思惑を紐解く。
ロシアが求めるドンバス割譲の戦略的狙い
報道によると、ロシア側は米国に対し、和平の条件としてウクライナ東部ドンバス地域からのウクライナ軍撤退とロシアへの割譲を要求したとされる。これは、ロシアが既にドンバスを含む東部・南部4州を「併合」し、ロシアの連邦構成主体として憲法に明記していることから、ロシアの論理では一貫した要求と言える。しかし、ロシア軍は多大な犠牲を払いながらも作戦を継続しているものの、特にドネツク州におけるウクライナの強固な抵抗により、いまだドンバス地域全域を掌握するには至っていないのが現状だ。プーチン大統領の計算としては、万が一ウクライナ側がこの要求を受け入れれば、苦労なく領土を獲得できるという思惑がある。
 米アラスカ州アンカレジで会談するロシアのプーチン大統領とトランプ前米大統領。両首脳の対話がウクライナ情勢に与える影響が注目される。
米アラスカ州アンカレジで会談するロシアのプーチン大統領とトランプ前米大統領。両首脳の対話がウクライナ情勢に与える影響が注目される。
ロシアの戦況優位と交渉長期化戦略
プーチン大統領がこの領土割譲要求がすぐに実現すると本気で考えているのかについては、別の側面も指摘されている。服部教授は、ウクライナや欧州が受け入れがたい要求を意図的に突きつけることで、停戦や和平への動きを長期化させようとするロシアの戦略がある可能性を示唆する。その背景には、現在、前線でロシアが有利な戦いを続けており、支配地域を徐々に拡大しているという現状がある。ロシアとしては、今の段階で停戦に応じるよりも、ある程度の勝利を確信できるまで戦いを続け、その後に有利な立場で交渉に入りたいと考えているのだろう。
 ウクライナ東部のドンバス地域(ルハンスク州、ドネツク州)、ザポリージャ州、ヘルソン州を示す地図。ロシアが併合を主張するこれらの地域の戦略的重要性は高い。
ウクライナ東部のドンバス地域(ルハンスク州、ドネツク州)、ザポリージャ州、ヘルソン州を示す地図。ロシアが併合を主張するこれらの地域の戦略的重要性は高い。
ウクライナが抱える領土問題と国民感情の葛藤
ウクライナ側がドンバス地域の領土割譲要求を断固として拒否する理由は複数存在する。軍事的な観点からは、強固な防衛ラインが敷かれたドネツク北部を引き渡せば、将来的にそこをロシア軍の新たな拠点とさせ、さらにウクライナ中央部への侵攻を許してしまう懸念がある。国民感情としても、これだけ多くの命を犠牲にして死守してきたドンバス地域を簡単に手放すことは、多くの国民の理解を得られないだろう。
一方で、ドンバス地域以外のウクライナ国民が同地域にどれほど強い執着を抱いているかと言えば、必ずしもそうではないという本音も存在する。同地域はロシア語話者が多く、ウクライナの他地域とは異なる文化や気風を持つと感じる住民も少なくない。住民の中には、一概に親ロシアとまでは言えずとも、ロシアと実務的な関係を築くことを容認する者も多い。
さらに、ドンバス地域では10年以上前から分離独立運動が続き、戦争で多くの都市などが廃墟と化した。莫大な再建費用の課題に加え、実質的にロシア領となった地域に留まり、ロシアのパスポートを取得した住民たちをどう扱うか(追放するのか、再びウクライナ国民として受け入れるのか)という大きな問題がある。こうした背景から、ドンバス地域の再統合は現実的に極めて困難な課題となっている。
 ウクライナ東部ドネツク州北部で、破壊された集合住宅の前に立つ住民。紛争による深刻な被害と住民の苦境が垣間見える。
ウクライナ東部ドネツク州北部で、破壊された集合住宅の前に立つ住民。紛争による深刻な被害と住民の苦境が垣間見える。
結論
トランプ・プーチン会談が浮き彫りにしたのは、ウクライナ紛争におけるロシアの揺るぎない領土要求と、それに対するウクライナの複雑な状況である。ロシアは戦況の優位を背景に交渉を有利に進めようとし、ウクライナは軍事的・国民感情的な理由から領土割譲を拒否せざるを得ない。しかし、長年の分離独立運動や戦後の再建困難、住民の国籍問題など、再統合の困難さという現実的な課題も抱えている。服部教授の分析は、ウクライナ・ロシア間の和平への道のりが依然として遠く、多層的な課題を抱えていることを示唆しており、国際社会の動向がこれまで以上に注目される。
参考文献
- 共同通信=太田清 (Yahoo!ニュース掲載記事に基づく)