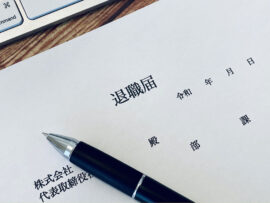かつて大学受験を経験した者なら、一度は目にしたことがあるかもしれない光景がある。それは、自分がほとんど関わりのなかった予備校の合格者一覧に、自身の名前が掲載されているという経験だ。記者の場合、30年ほど前の話だが、夏期講習を数日受けただけで第一志望校の合格者としてカウントされていたことに、当時首をかしげた記憶がある。このような合格実績の「水増し」は長年予備校業界に根強く存在し、受験生や保護者にとって情報判断を難しくしてきた。そして今、大手予備校である駿台が、2026年度の大学入試から合格者数の公表を中止するという重要な発表を行った。これは、予備校業界の透明性向上と、今後のあり方を問う大きな転換点となるだろう。
駿台の決断と「合格者水増し」の現状
2024年8月1日、駿台予備学校は、2026年度大学入試における合格者数の公表を停止すると発表した。その理由として、同校は「受験生が複数の塾や予備校、オンライン教材を併用して学ぶのが一般的となり、単一の教育機関の合格者数が本来の意味を持ちにくくなった」と説明している。この声明は、長年にわたり指摘されてきた予備校業界の慣行、すなわち合格実績の「水増し」問題に一石を投じるものだ。
実際のところ、各予備校が公表する合格者数と大学側の発表には大きな隔たりが見られる。例えば、今年の東京大学一般入試の合格者数は2997人であるのに対し、大手予備校4社(駿台、河合塾、東進ハイスクール、鉄緑会)が発表する合格者数の合計は約4500人に達する。この約1.5倍もの差は、予備校がどれだけ多くの生徒を自校の合格実績として計上しているかを示す具体的な証左と言えるだろう。
 駿台予備学校の看板が立つ街並み。2026年度からの大学入試合格者数公表中止の方針を示す。
駿台予備学校の看板が立つ街並み。2026年度からの大学入試合格者数公表中止の方針を示す。
繰り返される「水増し」の実態と背景
大学ジャーナリストの石渡嶺司氏によると、予備校における合格実績の「水増し」は、大学受験が激化し始めた1960年代から存在していたという。年間を通じて正規に受講する生徒だけでなく、夏期講習のような短期受講生や、さらには模試を受けただけの生徒までもが合格者数に加算され、予備校の実績として誇張されてきた経緯がある。このような慣行は、予備校が生徒獲得のために「合格実績」を最大の武器としてきた背景がある。
この「水増し」の横行を抑制するため、社団法人 全国学習塾協会は2024年7月に合格実績の自主基準を厳格化する動きを見せた。新基準では、合格者として計上できるのは「受験直前6ヵ月間に『在籍』があり、かつ同期間に受講契約に基づく30時間以上の『受講』の実態があるか」、あるいは「継続して3ヵ月以上の『受講』の実態がある」生徒に限定すると定めている。これは、実質的な学習貢献度を重視し、安易な水増しを防ぐための重要な試みである。
見極めが困難な合格実績:受験生と保護者の課題
しかし、全国学習塾協会の厳格化された基準も、すべての予備校に適用されるわけではない。石渡氏が指摘するように、同協会に所属していない学習塾や予備校は多数存在し、それらの機関には新たな基準が及ばない。また、受講契約に基づいていても、成績優秀者を特待生として受け入れ、実質的な受講実態がないにも関わらず合格実績に加えるケースも存在する。実績を少しでも高く見せたいという予備校側の思惑は依然として根強く、受験生や保護者にとっては、依然としてどの情報が信頼できるかを見極めるのが困難な状況が続いている。
信頼できる合格実績を見極める上で重要なのは、単なる合計数だけでなく、「年度別の合格実績」や「最終進学先」といった詳細かつ具体的な情報が公表されているかどうかだ。例えば、今年1月に経営破綻した老舗予備校のニチガクは、実績の表現が曖昧で、「多数の合格者」をアピールしながらもそれがいつの年度の実績なのかが分かりにくいという問題があった。不透明な情報開示は、結果として信頼を失い、経営破綻の一因ともなった事例である。
少子化と多様化する入試制度:予備校業界の未来
少子化が進む日本において、安易に合格者を「水増し」するような予備校は、今後淘汰されていく可能性が高い。特に都市部では中高一貫校の教育内容が充実し、学校内で質の高い学習指導が受けられるため、外部の塾や予備校の存在意義が相対的に低下している。生徒や保護者の予備校を見る目は年々厳しくなっており、表面的な実績だけでなく、実際の学習サポートや個別対応の質が重視される傾向にある。
近年、大学入試制度は指定校推薦や総合型選抜など、多岐にわたる形態に多様化している。画一的な100人単位の一斉授業という旧態依然としたスタイルでは、多様なニーズを持つ受験生に対応しきれない。予備校には、個々の受験生の学力レベル、志望校、学習スタイルに合わせたきめ細やかな指導法が求められている。合格実績の透明化と、生徒一人ひとりをより手厚くサポートする個別最適化された教育を提供できる予備校こそが、この変化の時代を生き残り、信頼を得られるだろう。
参考資料
- FRIDAYデジタル「駿台予備校が『合格者数公表』中止へ! 背景にあった大学受験『水増し』の歴史」(Yahoo!ニュース, 2024年8月4日配信)
- 社団法人 全国学習塾協会 (JACPA) 発表資料 (2024年7月)
- 東京大学入試情報 (2024年度一般選抜)