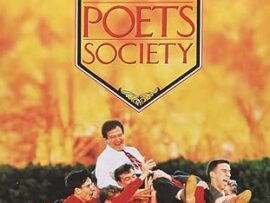ロシアのプーチン大統領は1日、中国・天津で開催された上海協力機構(SCO)首脳会議での演説において、SCOが「真の多国間主義」を体現していると強調しました。大統領は、この枠組みが「時代遅れの欧州中心モデル、欧州大西洋モデルに取って代わるものだ」と主張し、国際秩序における西側主導のあり方に異議を唱えました。また、ウクライナ侵略についても、危機を招いた責任は欧米側にあると改めて正当化する見解を示しました。
SCOと「真の多国間主義」:欧米モデルへの異議
プーチン大統領は、SCOが構築を目指す世界秩序について、「可能な限り多くの国の利益を考慮し、バランスがとれたものであり、他国の安全を犠牲にして自国の安全を図ろうとする試みを容認しない」と述べました。この発言は、ロシアが国際社会、特に欧米諸国に対して抱いている不信感の表れとみられます。大統領は、西側が自国の安全保障を優先するあまり、他国の懸念を無視していると批判し、多極化する世界においてSCOのような枠組みが重要であるとの認識を示唆しました。
 上海協力機構首脳会議で演説するロシアのプーチン大統領。国際秩序と多国間主義について言及。
上海協力機構首脳会議で演説するロシアのプーチン大統領。国際秩序と多国間主義について言及。
ウクライナ危機におけるロシアの主張とその背景
ウクライナでの「特別軍事作戦」に関しても、プーチン大統領はロシアが同様の理念を堅持していると強調しました。同氏の持説によれば、ウクライナ危機の責任は、2014年の「クーデター」を支援した欧米諸国と、その「クーデター」を支持しなかった親露派住民らを武力で鎮圧しようとしたウクライナ側にあるとされます。さらに、欧米がロシアの安全保障上の懸念を無視し、ウクライナを北大西洋条約機構(NATO)に加盟させようとしたことが、「危機の第2の要因」になったと指摘しました。これは、ロシアがウクライナ侵攻を正当化する上で繰り返し用いる主要な論点の一つです。
ロシアの主張に潜む論理の矛盾と歴史的経緯
しかし、プーチン大統領の主張には、歴史的な経緯との間に矛盾が指摘されています。2010年代、ウクライナのヤヌコビッチ政権は欧州連合(EU)との関係強化に向けた協定締結を進めていましたが、2013年11月に突如としてその署名を棚上げしました。この背景には、ウクライナとEUの接近を阻止しようとするロシアからの強い圧力があったとされています。この決定に反発したウクライナ国民は大規模な抗議デモを開始し、結果的に2014年2月にヤヌコビッチ政権は崩壊しました。
この政権崩壊を受けて、ロシアはウクライナ南部クリミア半島を併合し、ウクライナ東部で蜂起した親露派武装勢力への支援を開始。東部紛争が勃発し、ウクライナはロシアに対抗するため欧米への接近を一層強めました。プーチン大統領は2022年2月、東部紛争を終わらせるためと主張し、ウクライナに対する「特別軍事作戦」の開始を宣言しました。長年にわたり、プーチン氏はヤヌコビッチ政権崩壊時のデモを欧米が裏で糸を引いた「クーデター」と非難してきましたが、ロシアがEUとウクライナの協定締結を妨害していなければ、その後のデモや政権崩壊、東部紛争は起きなかった可能性が高いとの見方が有力です。この点が、ロシアのウクライナ危機責任論の不当性が指摘される大きな要因となっています。
参考資料
- Yahoo!ニュース: プーチン氏がSCO首脳会議で欧米中心モデルを批判、ウクライナ侵略を再び正当化 (https://news.yahoo.co.jp/articles/b741c59e5f8e0fdd5ce65449024c34faf5f1f37b)