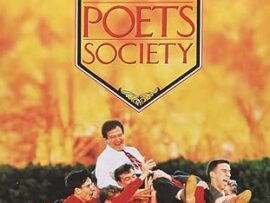元サッカー日本代表の本田圭佑氏が、過去の歴史認識に関する自身の発言を迅速に訂正した一件は、SNS上で大きな反響を呼びました。特に「一次資料などを詳しく調べたら、事実はほぼ歴史通りであると思いました」というコメントは、その素早い対応と誠実な姿勢から多くの賞賛を集めました。しかし、この一連の出来事は、現代社会において「情報リテラシー」や「一次資料」といったキーワードが持つ意味について、深く考えるきっかけを与えています。SNSの普及により誰もが情報の発信者となり得る時代に、私たちはどのように情報の真偽を見極め、信頼性の高い情報源と向き合うべきなのでしょうか。本記事では、この本田氏の事例を切り口に、SNSにおける「一次資料主義」の危うさと、より健全な情報との付き合い方について考察します。
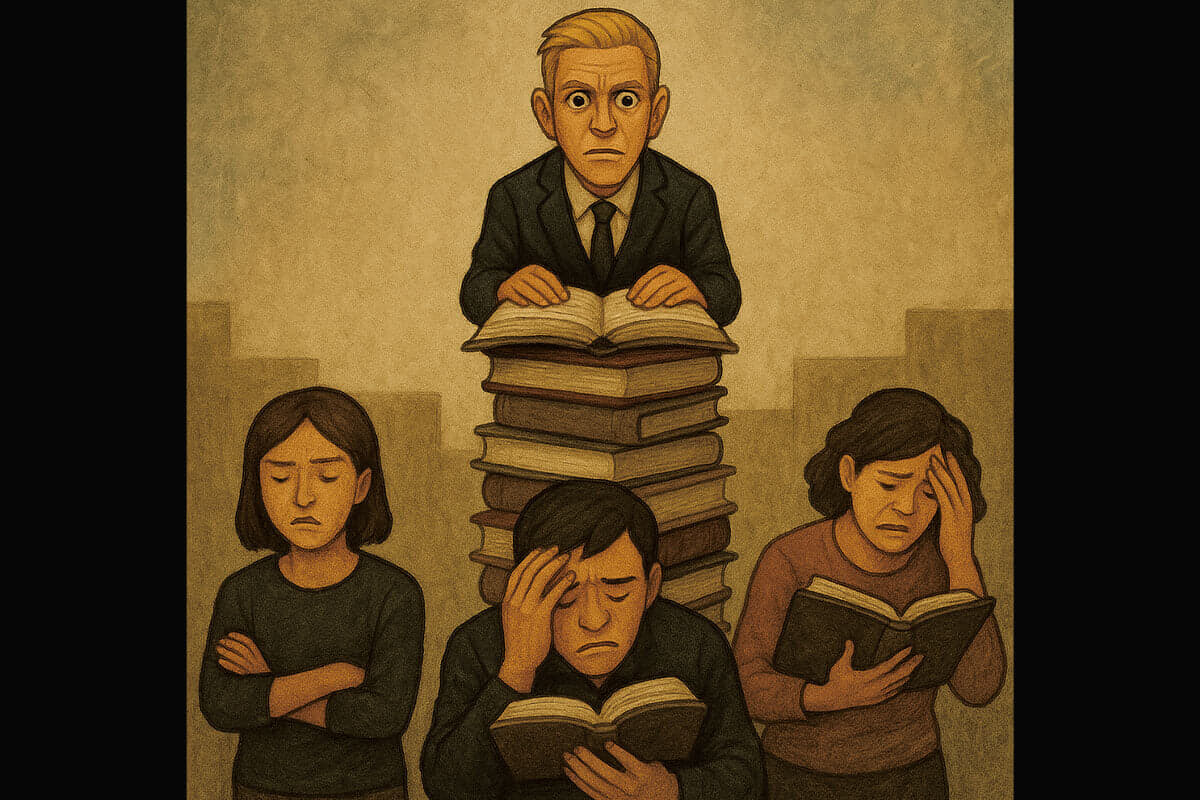 サッカーボールと資料の山を背景に、スマートフォンを操作する本田圭佑氏のイメージイラスト。SNSでの情報発信と、その後の迅速な情報修正の様子を示唆している。
サッカーボールと資料の山を背景に、スマートフォンを操作する本田圭佑氏のイメージイラスト。SNSでの情報発信と、その後の迅速な情報修正の様子を示唆している。
SNSで称賛された本田氏の「一次資料」発言、その裏に潜む危うさ
2023年8月9日、本田圭佑氏はX(旧ツイッター)に、「石原慎太郎さんのことが好きなこともあり、歴史のことは知ってたつもりだったものの、希望的コメントをしました。ただ一次資料などを詳しく調べたら、事実はほぼ歴史通りであると思いました。この点、僕の間違いでした」と投稿しました。これは戦時中の南京事件に関する自身の歴史認識が誤っていたことを認め、訂正する内容です。わずか1日で速やかに修正し、情報源として「一次資料」に当たったと明言した本田氏の姿勢は、SNS上で「さすが」「誠実だ」と絶賛されました。
しかし、時事芸人のプチ鹿島氏は、この「一次資料」というキーワードに対し、ある種の「モヤモヤ」を感じたと語っています。SNSでは近年、論争が起こるたびに「エビデンスは」「ソースは」「一次資料に当たったのか」といった言葉が飛び交うようになりました。まるで、これらが論争に勝つための「テクニック」であるかのように使われる風潮があります。本田氏が「一次資料などを~」と先に述べることで、多くの人がそれを「鉄壁の防御コメント」と受け止めた可能性は否定できません。この言葉は、情報の信頼性を担保する魔法の杖のように機能し、発言者を強く見せる効果を持っているかのようです。その背景には、一部で広がる「マスコミ不信」や「オールドメディア不信」といった感情も少なからず影響しているのではないでしょうか。メディアが報じる内容を「切り取り」「偏向」と捉え、信用しない風潮の中で、「一次資料に当たるべき」という主張が「意識の高い振る舞い」と見なされやすい側面があるのです。
専門家でも困難な「一次資料」読解:なぜ私たちはメディアに頼るのか
「一次資料」に当たることが情報の真偽を見極める上で重要であることは論を俟たない事実です。しかし、誰もが一次資料にすぐにアクセスできるわけではありません。ましてや、その膨大な情報を分析し、解釈するには専門的な知識と時間が必要不可欠です。例えば、歴史的事件に関する一次資料は古文書であったり、外国語で書かれていたり、文脈を理解するための幅広い教養が求められることがほとんどです。
だからこそ、私たちは専門家や研究者の知見を借り、その分析や解釈を通じて、物事の全体像を理解しようとします。また、日々の出来事を多角的に取材し、報道するメディアの存在も同様に重要です。プチ鹿島氏が指摘するように、私たちがメディアを利用する理由の一つは、まさにそうした専門的な情報収集や分析を「代理」してもらうためです。素人が限られた時間で一次資料に当たったところで、誤った解釈をしてしまう危険性も大いにあります。本田氏のように、知己やブレーンのサポートがあったからこそ迅速な対応が可能だった側面も否めず、一般の人がこれを真似するのは極めて困難な現実があります。
「急がず、多角的に」情報と向き合う:現代社会に求められる情報リテラシー
現代社会において、すべての人があらゆるニュースの現場に赴き、納得いくまで取材することは非現実的です。私たちが情報と適切に向き合うためには、何を重視すべきなのでしょうか。プチ鹿島氏は、専門家の知見や継続取材を担うプロの記者の存在を改めて評価し、「急がなくていい、時間をかけていい」と提言しています。
新聞の論調のように専門家にも主張やバックボーンの違いがあることを頭に入れつつ、様々な視点から提供される「二次情報」や「三次情報」を慎重に吟味する姿勢が求められます。単一のソースに依存せず、複数の情報をクロスチェックすることで、情報の偏りや誤りを是正し、より客観的な事実を把握することが可能になります。情報の信頼性を確認するための「ファクトチェック」の視点も不可欠です。
安易な「一次資料至上主義」に陥ることなく、情報源の多様性を尊重し、専門家の意見に耳を傾け、そして何よりも焦らず、時間をかけて情報を検証する。これこそが、情報過多の時代に私たちが身につけるべき真の情報リテラシーであり、信頼できる情報と健全に付き合うための有効な方法であると言えるでしょう。
参考文献
- プチ鹿島. (2025年9月1日). <歴史認識の「間違い」を素早く認め称賛された本田氏。「一次資料を詳しく調べた」という鉄壁の防御コメントに潜む危うさとは?プチ鹿島さんが考察します>. Newsweek Japan. https://news.yahoo.co.jp/articles/7b34566e54c945bf2d3b5fe548df46d0822c4e0f
- プチ鹿島. X (旧Twitter): @pkashima
- プチ鹿島. (著作一部). 『ヤラセと情熱 水曜スペシャル「川口浩探検隊」の真実』双葉社. 『お笑い公文書2022 こんな日本に誰がした!』文藝春秋. 『芸人式新聞の読み方』幻冬舎. 他.