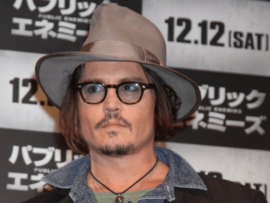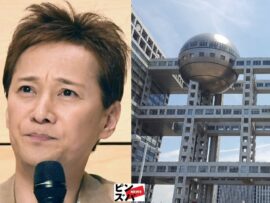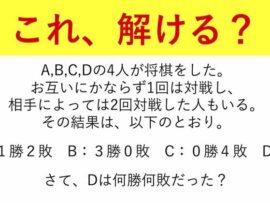人口減少と国内市場の縮小が深刻化する日本において、外国人材との共生は避けて通れない喫緊の課題となっています。しかし、言葉や文化が異なる人々が共に生きる道は、常に「きれいごと」だけでは済まされません。人材マッチングの専門家である中村大介氏の著書『日本人が知らない 外国人労働者のひみつ』は、現場で実際に起きている混乱や、外国人労働者との円滑な共生に向けたヒントを、忖度なくリアルに描き出しています。本稿では、同書からの抜粋連載第5回を基に、外国人の視点から見た日本人の独特なコミュニケーション様式、特に「曖昧な表現」と「拒否の仕方」に焦点を当て、その背景と解決策を探ります。
日本人の「曖昧表現」が引き起こす誤解
ベトナム出身で日本の大学院のMBAコースを修了し、日本語能力検定N1を持つ一人の女性社員は、日本人の「曖昧な表現」に困惑した経験を語っています。飲食店でのアルバイト中、「このお皿をお下げしていいですか?」と尋ねたところ、「いいですよ」と返答があったため皿を下げると、「そのままでいい」という意味だったと怒られたというのです。このエピソードは、日本人が悪気なく使う「いいですよ」や「大丈夫です」といった言葉が、外国人にとっては真逆の意味に捉えられかねないことを示しています。明確な許可と受け取るか、それとも現状維持を意味するか、文化的な背景が異なることでコミュニケーションの齟齬が生じやすいのです。外国人スタッフと接する際には、より具体的に、誤解の余地のない表現を心がけることが、円滑な関係構築に繋がります。
 異文化理解を深めるための日本人と外国人の対話風景
異文化理解を深めるための日本人と外国人の対話風景
ストレートな「ノー」を求める外国人
コミュニケーションにおけるもう一つの大きな違いは、日本人が「ノー」をはっきりと伝えない傾向にあることです。高校で観光ビジネスを学び、日本の旅行会社で研修を積んだインドネシア人女性は、「日本人は断る前に、いろいろと理由を言いますよね。すぐ断ればいいじゃないですか?」と疑問を呈します。職場で飲み会に誘われた際も、「今日はやめときます」と即答せず、「実は最近、仕事が立て込んでまして、ちょっと疲れが溜まってて……」と長々と理由を述べるのは、日本人によく見られる行動です。
ミャンマー人男性の意見はさらに明確です。「ストレートに言ってほしい。日本人の考えだと、ストレートに言ってしまうと、相手が傷つくと思っているのかもしれませんが、私たち外国人の考え方だと、ストレートに断るなら断ってくれていいんです。また次に頑張ればいいので」と語ります。「ストレートにノーと言われたからといって、なぜ傷つく必要があるのか? また次にトライすればいい」という彼らの前向きなマインドセットは、時に直接的な表現を避けがちな日本のビジネスパーソンが学ぶべき点があると言えるでしょう。
まとめ:共生社会へ向けた相互理解の重要性
外国人材との共生が深まる中で、日本人と外国人の間には、言葉の壁だけでなく、文化や慣習に根差したコミュニケーションのギャップが存在します。日本人の「曖昧な表現」や「ストレートな拒否を避ける傾向」は、相手を気遣う気持ちから来るものですが、異なる文化圏の出身者には誤解や不信感を生む原因となり得ます。外国人労働者の視点に立ち、彼らが求める明確な意思表示や直接的なコミュニケーションを理解し、実践することで、互いの信頼関係はより強固なものとなるでしょう。共生社会の実現には、一方的な理解だけでなく、相互の文化を尊重し、歩み寄ろうとする姿勢が不可欠です。
参考文献:
中村大介 (2023). 『日本人が知らない 外国人労働者のひみつ』. クーリエ・ジャポン掲載記事より抜粋.