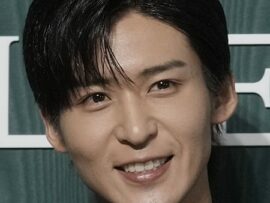全国の小中学校では新学期が始まり、2学期は遠足や校外学習など様々なイベントが催されます。その中でも特に注目されるのが「学芸会」、または「学習発表会」です。しかし、近年、一部の学校ではこの学芸会を巡って保護者の間で新たな「軋轢」が生まれていると報じられています。子供たちの習い事が多様化する現代において、学校行事である学芸会が変質しつつある現状と、それに伴う保護者の複雑な心境に迫ります。
 習い事が多様化する現代の小学校学芸会。プロ顔負けのレベルに達した子供たちのパフォーマンスの様子。
習い事が多様化する現代の小学校学芸会。プロ顔負けのレベルに達した子供たちのパフォーマンスの様子。
プロ顔負けのパフォーマンスと隠された「格差」
昨年11月、都内の公立小学校で行われた学芸会での出来事です。6年生の児童たちが披露した出し物は、スポットライトを浴びるバイオリンの音色とハイテンポなドラムのビートが響き渡り、そこへヒップホップダンスが加わります。さらにファルセットやシャウトを織り交ぜたボーカルが彩りを添え、まるでプロ顔負けのようなパフォーマンスが展開されました。会場の保護者席からは、割れんばかりの拍手喝采が上がったといいます。
しかし、その場にいた保護者の一人、直江久美子さん(仮名)は、周囲に合わせて手を叩きながらも、自分の息子の姿を探すのに苦労しました。「うちの子はステージ下の端っこの薄暗いところにいて、見つけるのに時間がかかりました」と直江さんは語ります。放課後にいつも一緒に遊ぶ、習い事をしていないグループの子たちがその場所に固められており、皆うつむき加減でカスタネットを叩いていたそうです。
直江さんは、そもそも息子の担当パートを知らなかったといいます。息子が学芸会の話を家でまったくせず、「参観にも来ないで」と話していたのには理由がありました。目立つパートではなかった息子は、おそらく劣等感を感じていたのでしょう。一方で、重要なパートを担当していたのは、普段からダンス教室や音楽教室に通っている、いわゆる「お金持ちの家の子たち」ばかりでした。彼らの両親は揃って参観に訪れ、望遠レンズでわが子の姿を追いかけながら熱い声援を送っていたといいます。直江さんは内心、「これは金持ちたちのお祭りじゃないか」と感じたそうです。
学芸会は「学校活動の成果」か、「習い事の発表の場」か
直江さんが抱いたこうした違和感は、単なるやっかみだけではないようです。都内の別の公立小学校の学芸会を参観した吉池幸太郎さん(仮名)も、同様の懸念を抱いています。
吉池さんは「小学校も高学年の出し物となると、昔の学芸会とはレベルが違います」と述べます。しかし、そうしたハイレベルな出し物を支えているのは、ダンスや楽器などの習い事をしている子どもたちです。吉池さんは、彼らが学芸会で重要なパートを勝ち取るのは、他の子どもたちが遊んでいる時間にも習い事に通い、努力した賜物であると認めつつも、疑問を呈します。「でも、学芸会や学習発表会は、学校活動の成果を発表する場。校外で培った技能を発表するのはちょっと違うとも思いました」。学校教育の場で得た知識や技能の発表の場であるはずの学芸会が、外部で身につけたスキルを披露する場へと変質している現状に、多くの保護者が複雑な思いを抱いています。
では、なぜ学芸会は、本来の「学習成果の発表の場」としての意義から離れてしまったのでしょうか。都内の公立小学校の現役教員は、その背景には現代社会の様々な要因があると明かします。
まとめ
現代の小学校における学芸会は、かつてないほどのパフォーマンスレベルに達している一方で、子供たちの習い事の有無が大きく影響し、「習い事格差」が如実に現れる場となりつつあります。保護者からは、学校活動の成果発表の場であるはずの学芸会が、一部の子供たちの「才能披露の場」へと変貌していることに対し、不満や疑問の声が上がっています。教育現場が直面するこの課題は、学校行事の本来の意義と、多様化する現代社会における子供たちの教育のあり方について、改めて深く考えるきっかけを与えています。
参考文献: