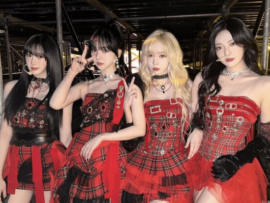“プロ経営者”として知られる新浪剛史氏がサントリーホールディングス会長を辞任するきっかけとなった、大麻成分を含むサプリメントの事例は、日本の大麻関連法規の厳格化を改めて浮き彫りにしました。昨年12月に施行された麻薬取締法と大麻取締法の改正により、大麻は「麻薬」と位置付けられ、特に有害成分であるTHC(テトラヒドロカンナビノール)の限度値を超過する製品の所持は、「麻薬所持罪」という重い罪に問われることになります。海外ではTHCに対する規制の基準が国や地域によって異なるため、海外で合法的に流通している製品であっても、日本の極めて厳しい基準の下では違法となる可能性が高く、日本の消費者は細心の注意を払う必要があります。
 サントリーホールディングス会長を辞任した新浪剛史氏が自身の経緯を説明
サントリーホールディングス会長を辞任した新浪剛史氏が自身の経緯を説明
合法的なCBD市場と日本の医療利用への道
大麻草由来の成分には、主に精神作用を持つTHCと、非精神作用のCBD(カンナビジオール)があります。このうちCBDには、リラックス効果や質の良い睡眠をサポートする効果が期待されており、日本では合法的に利用できる成分とされています。
CBDを含む製品は、欧米を中心にサプリメント、グミ、オイル、ベイプリキッド、化粧品など多岐にわたる形で開発され、その市場規模は現在約100億ドル(約1.47兆円)に達すると推計されています。日本国内でも、THCを含まないCBD製品が合法的に販売されており、健康志向の消費者から注目を集めています。
今回の75年ぶりの大麻取締法改正の目的の一つには、CBDを含む難治性てんかん治療薬が海外で薬事承認されていることを受け、日本でも大麻由来成分を医療用途に利用できるようにするという背景がありました。しかし、新浪氏が海外出張時の時差ぼけ対策として米国在住の知人から勧められたというCBDサプリメントは、日本では麻薬取締法に違反するレベルのTHCが含まれていた疑いがあることから問題視されたのです。
法改正の核心:THCの「麻薬」指定と厳罰化
THCは、CBDと同様に鎮痛や睡眠導入などの効果が指摘される一方で、いわゆる“ハイになる”精神作用があり、慢性的かつ高用量の使用は依存症や精神障害のリスクを高めるとされています。このため、改正法ではTHCが厳しく規制されることになりました。
これまでの大麻取締法は、大麻草の「部位」を規制対象としており、花や葉の所持が違法とされていました。このため、改正前はCBD製品に微量のTHCが含まれていても、「合法的な部位(茎など)を利用した」と主張することで、違法とみなされない曖昧なケースが存在していました。今回の法改正は、このような曖昧さを排除し、THCの含有量によって明確に合法か違法かを判断する基準を設けたものです。
法改正により、THCは法的に「麻薬」と定義され、規制値を超過する含有製品を所持しているだけで、その意図の有無にかかわらず「麻薬所持罪」という重大な刑事罰の対象となります。不正な所持に対する罰則は、従来の「5年以下の懲役」から「7年以下の懲役(拘禁刑)」へと引き上げられました。さらに、改正前にはなかった「使用罪」が新たに導入され、尿検査などでTHCが検出された場合、たとえ大麻製品自体が押収されなくても立件される可能性が高くなりました。これにより、国内外問わず、大麻成分を含む製品の取り扱いには一層の注意が必要となっています。
結論
新浪氏の件は、CBDを含むサプリメントであっても、日本の大麻関連法の改正によってTHC含有製品が厳しく取り締まられるようになった現状を社会に強く認識させる出来事となりました。THCは「麻薬」と位置付けられ、意図せずとも所持や使用が処罰の対象となるため、海外で販売されている大麻成分含有製品の利用には極めて高いリスクが伴います。日本の消費者は、製品が合法であるかどうかを判断する際に、海外の基準ではなく、日本の最新の法律に照らして慎重に確認し、不明な点があれば専門機関に相談するなど、最大限の注意を払うことが求められます。