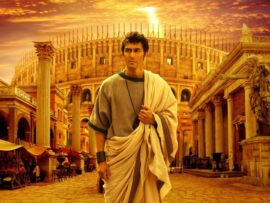日本初の女性宰相として注目を集める高市早苗首相は、現在開催中の大相撲九州場所で内閣総理大臣杯の授与を巡り、ある伝統的な問題に直面しています。それは、女性の土俵への立ち入りを禁じる「女人禁制」の慣習です。この歴史ある慣習は、多様性が叫ばれる現代社会において、その是非が改めて問われています。
物議を醸した「女性は土俵から降りて」
大相撲の土俵は「女人禁制」の場として長らく守られてきました。多くの人が覚えているのは、2001年夏場所に満身創痍で優勝を決めた貴乃花に対し、当時の小泉純一郎首相が土俵上で内閣総理大臣杯を授与した感動的なシーンでしょう。しかし、女性が土俵に上がる際には度々物議を醸しています。例えば、2018年には兵庫県宝塚市の中川智子市長が土俵上での挨拶を拒否され、「悔しい」と不満を表明しました。同年には、地方巡業の土俵上で倒れた舞鶴市長の手当てのために女性の看護師が土俵に上がった際、「女性は土俵から降りて」というアナウンスがなされ、大きな騒動となりました。
高市首相が内閣総理大臣杯を優勝者に手渡したいと望んだ場合、この慣習はどのように扱われるのでしょうか。相撲ライターの西尾克洋氏によると、「女性を土俵には上げない、という既存のスタイルを守っていくというスタンス」が相撲界にあるようです。その理由として、西尾氏は三つの点を挙げます。一つ目は相撲が神事であること、二つ目は伝統を守ること、そして三つ目は鍛錬を重ねた男性が上がる神聖な場所であるということです。
 高市早苗首相の就任後初の記者会見の様子 (2025年10月21日)
高市早苗首相の就任後初の記者会見の様子 (2025年10月21日)
伝統の「根幹」と柔軟性
多様性が重視される現代において、「女性だから」という理由だけで土俵に上がれないことに納得できないという声も存在します。時代に合わせて変化すべきではないかという問いに対し、相撲界はこれまで伝統を守ることでその価値を生み出してきたと説明します。髷やまわしなども江戸時代から受け継がれてきたものであり、そうした歴史の上に成り立っている世界観があるのです。
しかし、伝統的で保守的と思われがちな相撲界にも、意外な柔軟性を見せる側面があります。西尾氏は、世界で最初にビデオ判定を導入したスポーツが相撲であることを指摘します。1969年の横綱・大鵬と戸田の一番がきっかけとなり導入されました。また、土俵の上に柱で支えられていた屋根も、テレビ中継が始まってから見づらいという理由で現在の形に変わりました。
このように世の中や環境の変化に合わせて、相撲界はその形を変えてきました。しかし、女性の扱いについては、「相撲の“根幹”に当たる部分なのではないか」と西尾氏は見解を示しています。八角理事長も2018年の一件の際に、「女性が穢れているから上がらせないのではない」とはっきり否定し、上げないことが伝統なのだと説明しました。例えば、髷やまわしを「今の時代にそぐわない」と変えることは可能でしょうか。それはもはや相撲ではなくなってしまう、といった次元の話だというのです。
譲れるものと譲れないもの。そこで守られてきた歴史や文化を否定することはできないというこの問題は、「男女平等」という枠組みでは語り尽くせない複雑さを抱えています。高市首相のケースを通じて、この伝統と現代的価値観の狭間でどのような着地点が見いだされるのか、今後の動向が注目されます。