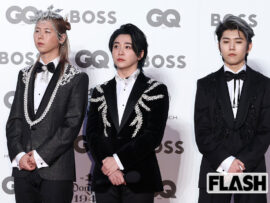大腸癌、肝臓転移、そしてステージ4という厳しい現実に直面し、11時間にも及ぶ大手術と57日間の入院を経て、ようやく日常の輪郭を取り戻しつつあった。体調は安定し、食欲も回復、夜は眠れ、朝夕の散歩では6000歩を超えるリハビリをこなす日々。しかし、その束の間の平穏は、新たな癌の転移という冷徹な事実によって脆くも崩れ去った。主治医の表情が硬直したその刹那、私は直感した。癌との闘いは、まだ終わっていなかったのだ。
束の間の日常と予期せぬ再発
退院からわずか1カ月、2カ月にわたる壮絶な闘病を終え、心身ともに回復の兆しが見えていた時期だった。毎日の散歩で体力を取り戻し、穏やかな日常が戻りつつあると感じていた。しかし、その回復は「生還」というよりも、「生き延びた」という表現がふさわしいものであったと、後に思い知らされることになる。
1カ月検診は、単なる節目確認に過ぎないと考えていた。血液検査、CTスキャン、そしていつもの診察室。しかし、主治医の表情が一瞬にして硬くなったのを目の当たりにし、長年、厳しい世界で修羅場をくぐり抜けてきた経験から、根拠のない確信が私の胸をよぎった。「肺の転移が増殖している。最後の癌手術をしましょう」。淡々とした声で告げられた内容は、あまりにも容赦ないものだった。終わったはずの闘いは、終わっていなかったのである。
 がん患者が自身の病と向き合い、医師の診断に耳を傾ける様子
がん患者が自身の病と向き合い、医師の診断に耳を傾ける様子
患者の弱音と医学の厳しさ
前回の闘病が想像以上に過酷であったため、私は正直に弱音を吐いた。「前回の闘病は、正直きつかった。少し休ませてほしい」。虚勢を張る気力もなかった。人間として、肝臓を削られ、腹部を切開され、体力は完全に底を打っていたのだ。温泉に浸かり、孫の顔を見て、静かに心身を立て直したいという欲求は、逃避ではなく、次に備える「整える時間」を求める自然な感情であった。
しかし、医学は個人の感情に寄り添いすぎることはない。主治医は一歩も引かず、冷徹な論理を突きつけた。「今、手術の時期を延ばすのはリスクがあります」。語調は穏やかであったが、その意志は鋼鉄のように固かった。医師は希望を語るのではなく、事実だけを提示する。肺転移は待ってはくれない。体力の回復を待つ間にも、癌は静かに、しかし確実に進行するのだ。この局面での判断は、「楽か苦か」ではなく、「今か、遅すぎるか」という二択であった。折れそうな心を奮い立たせ、私はその厳しい現実を正面から受け止めることを決意した。
もう一人の患者としての家族
肺転移の事実を家族全員に伝えた瞬間、部屋には深い沈黙が落ちた。誰も声を荒げず、誰も泣き出すことはなかった。しかし、その重苦しい沈黙こそが、何よりも家族の苦しみを物語っていた。その時、私は悟った。家族もまた、第二のがん患者なのだと。
がんは、本人だけを蝕む病ではない。治療に関する判断、決断、そして募る不安、結果を待つ長い時間――そのすべてが家族の人生に深い影を落とす。私の一手は、決して私一人の問題ではなかった。それは、共に闘う家族全員の未来を左右する、重い選択なのである。