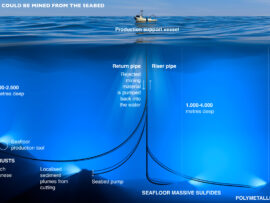朝ドラ「ばけばけ」で注目される小泉八雲の新たな側面
現在放送中のNHK朝ドラ『ばけばけ』は、小泉八雲(ラフカディオ・ハーン)とその妻セツの生涯を描き、好評を博しています。民俗学者である畑中章宏氏の著書『小泉八雲 「見えない日本を見た人」』(光文社新書)は、八雲を単なる怪談作家としてではなく、「ジャーナリストから民俗学者になった人」という新たな視点から捉え直した一冊です。畑中氏によれば、日本の民俗学が非合理的なものの中に庶民の思いが反映されていると見出すよりも早く、八雲は「妖怪など非合理なものにこそ日本らしさがある」と気づいていたといいます。
 畑中章宏氏のポートレート
畑中章宏氏のポートレート
怪談と民間伝承:八雲の関心の変遷
一般的に小泉八雲といえば、代表作『怪談』から怪談作家としてのイメージが強いですが、畑中氏は、八雲の関心の中心はむしろ民間伝承にあったと指摘します。初期の作品では旅先で出会った怖い話や怪異な伝承を扱っていましたが、特定の風土から切り離された怪談をまとめ始めるのは来日後半以降のことだったようです。八雲は来日後、ほぼ毎年日本論や旅行記・随筆を刊行しており、英語版の反響を見てから怪談のまとめに着手した可能性が高いとされています。実際、最も広く読まれている『怪談』は、八雲が54歳で死去した明治37年(1904年)に刊行されました。
八雲は来日前から民間伝承に深い興味を抱いていました。カリブ海のマルティニーク島では、その地を「魑魅魍魎の島」と呼び、伝説や昔話を著書にまとめました。また、それ以前のニューオーリンズ滞在時にも、フランス系アメリカ人とアフリカ文化の混合(クレオール文化)に魅せられ、諺や料理に関する著作を残しています。
視覚を超え、聴覚で捉えた日本文化
八雲の日本文化へのアプローチは、一般的な欧米人とは一線を画していました。多くの欧米人が町の清潔さや日本人の体格、家屋の貧弱さといった「視覚」情報に基づいて日本を評価するのに対し、八雲は「聴覚」を重視したのです。例えば、松江の朝を、米搗きの杵の音、寺の鐘、太鼓、物売りの声といった「音」だけで鮮やかに描写しています。
来日初日の横浜でも、人力車の音、下駄の音、女按摩の笛の音に注目するなど、八雲は「音」を通じて日本の情景を捉えようとしました。元新聞記者であった八雲は、近代化の進む横浜で失われつつある地方の「音」の風景を、ジャーナリストとしての鋭い感性で「予兆」として感じ取っていたのです。彼はキリスト教文明主導の近代化に染まっていない日本古来の民間伝承や民間信仰にこそ、真の日本らしさを見出し、深く魅せられていきました。
家族への渇望と日本への帰化
私生活において、八雲は来日翌年には松江藩の没落武家の娘セツを住み込み女中に雇い、ほどなく結婚しました。妻の懐妊を機に帰化を考え始め、来日6年目に手続きを整え「小泉八雲」と改名します。生涯で4人の子どもをもうけ、自分の家族を何よりも大切にしました。
幼い頃に両親と離別した経験から、八雲にはまともな家族への強い渇望があったと畑中氏は分析します。「自分の家族だけはこの国で大切に育てたい」という思いが強かったのでしょう。また、松江から移った熊本の五高では多くの生徒に慕われ、自身の授業内容が高く評価されたことから、日本人への信頼を深め、「この国で誠実に付き合っていきたい」と、日本文化に本格的に取り組む決意を固めていったのです。