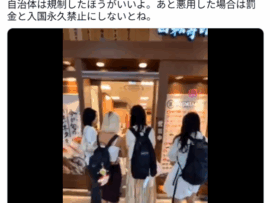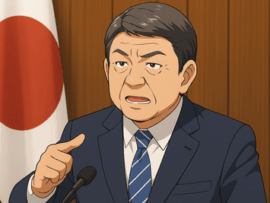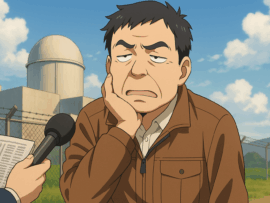[ad_1]
令和となって初めて迎えた建国記念の日を、心から祝いたい。連綿と続く日本の歴史を深く心に刻みたい。
初代神武天皇が即位したとされる日である。明治の初めに紀元節として祝日となった。
天皇を戴(いただ)き続けてきた世界でもまれな国柄である。その国に生を受けたことを感謝せずにいられない。
特に昨年は天皇陛下のご即位に伴い、即位礼正殿(せいでん)の儀や大嘗祭(だいじょうさい)など古式ゆかしい儀式、祭祀(さいし)が執り行われた。
それらを通じて、歴史が今に受け継がれていることを多くの国民が感じたはずである。
祝賀御列(おんれつ)の儀ではパレードの沿道に約12万人が集まり天皇、皇后両陛下を祝福した。
「天皇は、日本国の象徴であり日本国民統合の象徴」とする憲法第1条の意味を、実感した人も多かったに違いない。
わが国の物語は、はるかな昔にさかのぼっている。「古事記」「日本書紀」はまず、神話を記述する。やがて初代の神武天皇が大和の国、橿原で即位する様子を伝える。古代の「大化」から元号が始まった。明治から天皇お一方に一つの元号が用いられる「一世一元」の制となる。
2月11日は、このような日本の国柄や歴史的な連続性、現在の国民の統合を自覚する日として祝われるべきものであろう。
しかし戦後、この日に批判的な見方が出てきた。日本を占領した連合国軍総司令部(GHQ)は、昭和23年の祝日法でこの日を祝日とすることを認めなかった。
日本が独立した後も、建国を軍国主義と結び付けて警戒する風潮が残った。
建国記念の日ができたのは、戦後20年以上もたってである。いまだにこの日に反対する声がある。いいかげんにしたらどうか。
これは国として健全ではない。建国の物語はどの国も大切にすべきものだ。神話や伝承であってもよい。はるかな昔から先人が語り伝えてきた国民の貴重な財産にほかならない。
ご即位を率直に祝福する国民の姿は、このような風潮が過去のものになりつつあることをうかがわせる。それなのに建国記念の日を祝う国の式典は今年も開かれない。残念でならない。
政府は式典を主催し、堂々と祝うべきである。
[ad_2]
Source link