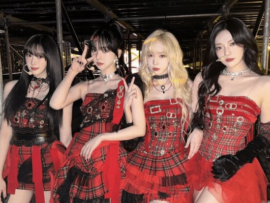2012年、岡山県立操山高校野球部のマネージャーだったA君(当時16歳)が自ら命を絶つという痛ましい事件がありました。野球部顧問による不適切指導が原因と認定されてから13年。遺族の深い悲しみは癒えることなく、再発防止策も遅々として進んでいません。jp24h.comでは、この事件の背景と現状、そして日本の「指導死」問題について改めて考えます。
遺族の苦しみと長い闘い
 亡くなったA君の遺影。ぬいぐるみがA君の無念さを物語っているかのようです。
亡くなったA君の遺影。ぬいぐるみがA君の無念さを物語っているかのようです。
A君の両親は、息子の死の真相を明らかにするため、県教育委員会に何度も働きかけました。しかし、第三者委員会が設置されたのは事件から6年後の2018年。顧問の叱責と自死の因果関係が認められたのはさらに3年後の2021年でした。それから再発防止策が発表されるまで、さらに4年もの歳月が流れました。
A君の父親は、「再発防止策の内容には納得していません。あまりに時間がかかりすぎている」と無念さをにじませます。13年という長い歳月の間、遺族はどれほどの苦しみを味わってきたのでしょうか。担当者も6人も変わり、遺族とのメールのやり取りは250ページにも及ぶといいます。
岡山県教育委員会の対応と再発防止策
2025年2月、岡山県教育委員会は再発防止策をまとめ、県立学校の校長向け説明会を開催しました。教職員向けハンドブックにハラスメント根絶に向けた取り組みを追記し、教育動画を制作・配布するなど、対策が進んでいるように見えます。
しかし、遺族にとっては納得のいくものではありませんでした。教育評論家の佐藤先生(仮名)も、「再発防止策は形骸化しているように感じる。本当に生徒を守りたいという強い意志が感じられない」と指摘しています。具体的な対策だけでなく、教職員の意識改革、学校全体の風土改革が不可欠です。

指導死問題の根深さと今後の課題
A君の事件は、日本の教育現場における「指導死」問題の深刻さを改めて浮き彫りにしました。勝利至上主義や行き過ぎた指導、生徒への適切なケアの不足など、様々な要因が絡み合っています。
文部科学省は、体罰や暴言などの不適切指導の根絶に向けて様々な取り組みを行っていますが、現場での意識改革は依然として課題となっています。生徒が安心して学校生活を送れるよう、教職員の研修体制の強化、相談窓口の設置、外部機関との連携など、多角的なアプローチが必要不可欠です。
未来への希望:二度と悲劇を繰り返さないために
A君の死を無駄にしないためには、私たち一人ひとりがこの問題について真剣に考え、行動していく必要があります。学校、教育委員会、地域社会が一体となって、子供たちの未来を守っていかなければなりません。二度とこのような悲劇が繰り返されないよう、jp24h.comは今後もこの問題を追っていきます。