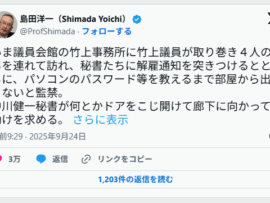[ad_1]
東武鉄道とモスバーガーがコラボ

東武鉄道とモスバーガーがコラボした「なりもす」駅(画像:東武鉄道)
東武鉄道は3月8日、東上線の成増駅(東京都板橋区)の駅名標や南口の駅名表示を「なりもす」駅へと改称した。成増駅は、大手ハンバーガーチェーン・モスバーガーの1号店が出店した(1972年6月)地として知られ、今回の取り組みは同店が開業50周年を迎えたことを記念したもの。駅名改称は東武鉄道とモスバーガーがタッグを組んだイベントで、駅名変更はあくまでも一時的な措置にすぎない。
【写真】50年前の「モスバーガー1号店」を見る
駅名を私企業に販売・貸与することはネーミングライツといわれる手法で、近年に目立ってきている。今回の“なりもす駅”は、これまでのネーミングライツと比べても格段に期間が短く、イベント的な色合いが強い。ネーミングライツは3~5年というサイクルで契約することが一般的だ。
ネーミングライツは駅名だけではなく、スポーツ施設などのスタジアムをはじめ図書館やイベントホールなどの公共施設や道路・橋梁といった交通インフラにも及ぶ。
国内初の導入は2003年

東京都調布市にある味の素スタジアム(画像:写真AC)
ネーミングライツの導入は小泉純一郎内閣(2001~2006年)の構造改革路線と連動した動きでもあり、小泉内閣が民間活力の導入を推奨したことで年を追うごとに増えていった。特に、その象徴とされたのが2001(平成13)年にオープンした味の素スタジアムだ。
東京都調布市に立地する同スタジアムは、2003年にネーミングライツを導入。大型公共施設では国内初のネーミングライツ導入ということで、その成り行きは全国の自治体関係者から注目された。
味の素スタジアムは5年契約で年間12億円のスポンサー契約を締結。2期目は6年間で14億円の更新となった。味の素スタジアムの名称は、導入から間もなく20年を迎える。それだけに、周辺住民やスポーツファンにも定着しているといっていいだろう。
ネーミングライツと住民感情

箱根ターンパイク(画像:写真AC)
ネーミングライツによるスポンサー契約は、スポーツ活動・文化活動を経済的に支えるという目的が含まれる。それには、長期的な支援が欠かせない。先ほど、ネーミングライツの契約期間は一般的に3~5年と書いたばかりだが、自治体関係者などに話を聞くと、本音では10年間という声が強い。
ネーミングライツは自社の知名度を広げる企業の広報戦略の一環といえるが、いくら企業が大金を投じているとはいえ、スポンサーが住民やファンの意向を無視して自社の宣伝活動を全面に打ち出せない。そんなことをすれば、周辺住民やファンからはそっぽを向かれる。大金を投じて、評価を下げる逆効果につながりかねない。
スタジアムや音楽ホールよりも、難しいとされるのが道路へのネーミングだ。国内における道路へのネーミングライツは、2007(平成19)年の箱根ターンパイクへの導入が発端とされる。
箱根ターンパイクは2007年に東洋ゴム工業とネーミングライツ契約を締結。新たに「TOYO TIRES」ターンパイクの愛称が付された。東洋ゴム工業とのネーミングライツ契約が切れた2014年には自動車メーカーのマツダと契約。道路名は「MAZDA ターンパイク箱根」となった。
そして、2018年には空気圧縮機・真空機器・塗装機器などメーカーであるアネスト岩田と契約。新たに「アネスト岩田 ターンパイク」となった。ネーミングライツの導入によって、箱根ターンパークの愛称は目まぐるしく変わっている。
箱根ターンパークは民間事業者が所有・管理する私道だったため、ネーミングライツ導入のハードルは低かった。箱根ターンパイクが契機となり、以降は道路へのネーミングライツ導入が相次いでいく。
スポーツ施設や文化施設といったハコモノでも、その名称が頻繁に変わることに住民やファンは違和感を覚え、嫌悪感を募らせる。それでもスタジアムやホールは、多くても月に1~2回程度しか足を運ばないから許容範囲といえるかもしれない。毎日のように使う道路は、そうはいかない。箱根ターンパイクでは5年に一度、スポンサー契約が更新され、そのたびに新しい名称が付与されてきた。
これではドライバーが道路名を覚えられないし、ナビや地図、道路標識や案内板などに旧名が残っていたりして混乱を起こしかねない。周辺住民にとっても、目まぐるしく名称が変わると愛着が湧きづらい。
道路は日常的に使用される交通インフラでもあるが、なによりもライフラインでもある。それだけに、周辺住民たちの視線はスタジアムやホールのそれよりもシビアになる。
[ad_2]
Source link