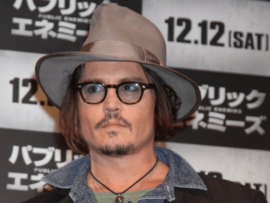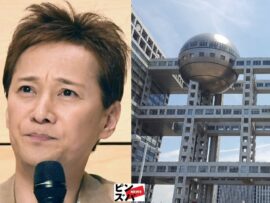マイナンバーカードと一体化したマイナ保険証。2024年12月2日をもって従来の健康保険証の新規発行が停止され、事実上、マイナ保険証への一本化が完了しました。しかし、利用率の低迷や医療機関窓口でのトラブル発生など、課題も多く山積しています。本当にマイナ保険証は必要なのか?従来の保険証との共存は不可能なのか?医療DXの未来はどうなるのか?この記事では、これらの疑問に真正面から向き合い、徹底的に解説していきます。
マイナ保険証一本化の背景にある医療DXとは?
政府は医療DX政策を推進しており、その中核を担うのがマイナ保険証です。全国民と医療機関の情報をプラットフォーム上で統合する医療DX基盤の構築には、マイナ保険証が不可欠とされています。
 alt: 医療DX構想の全体像を示すポンチ絵。マイナポータル、オンライン資格確認、電子処方箋、マイナ保険証、電子カルテ共有などの要素が描かれている。
alt: 医療DX構想の全体像を示すポンチ絵。マイナポータル、オンライン資格確認、電子処方箋、マイナ保険証、電子カルテ共有などの要素が描かれている。
しかし、国民の理解と支持は十分とは言えません。2024年9月のしゅふJOB総研の調査によると、マイナ保険証への完全移行に賛成する人はわずか13%、反対は45%に上ります。医療DX政策に対する抵抗感の根底には何があるのでしょうか?
基盤整備への理解不足が課題
九州大学大学院医学研究院医療情報学講座教授の中島直樹氏は、現在の医療DX政策は「DXのための基盤づくり」であり、基盤づくりには反対がつきものだと指摘します。
中島氏は、電線敷設の例を挙げ、新しい基盤整備には理解不足が伴うことを説明します。昭和初期、電線が整備された当時は、その必要性を理解する人は少なかったでしょう。スマートフォンもテレビもない時代に、「電気があると便利になるらしい」という説明では、人々の心を掴むことは難しかったはずです。
同様に、医療DX基盤の整備においても、そのメリットが国民に十分に伝わっていないことが課題です。基盤が完成する前に、その利便性を実感することは難しく、結果として反対意見が増えるのも無理はありません。
マイナ保険証のメリットと今後の展望
マイナ保険証は、医療情報の効率的な管理、医療サービスの向上、医療費削減など、多くのメリットが期待されています。例えば、過去の診療情報やアレルギー情報などを医療機関が共有することで、より適切な診断や治療が可能になります。また、重複投薬や検査の削減にもつながり、医療費の抑制も期待されます。「食生活アドバイザーの山田花子さん」は、「個人の健康管理意識の向上にも繋がるでしょう」と期待を寄せています。

しかし、システムの安定性や個人情報保護など、解決すべき課題も残されています。政府は、国民の声に耳を傾け、丁寧な説明と対策を講じる必要があります。国民も、医療DXの未来を見据え、積極的に議論に参加していくことが重要です。
まとめ:医療DXの成功に向けて
マイナ保険証の一本化は、医療DX実現に向けた大きな一歩です。しかし、国民の理解と協力なくして、真のDXは達成できません。政府と国民が共に未来を見据え、より良い医療システムを構築していくことが求められています。