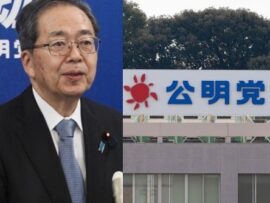出産を控えた喜びも束の間、迷信に固執する義両親の言動に悩まされているという30代女性の切実な訴えが韓国で話題になっています。今回は、JTBCの番組「事件班長」で取り上げられたこの事例を通して、現代社会における嫁姑問題、そして迷信との向き合い方について考えてみましょう。
義両親の行き過ぎた迷信、妊婦の負担に
結婚5年目、待望の第一子を出産予定の女性。しかし、春の出産を心待ちにする一方で、義両親の過干渉に悩まされているといいます。夫の実家を訪れる度に、浴室での衣服のお払い、足の組み方への注意など、迷信に基づいた奇妙なルールを強要されているとのこと。
 浴室でのお祓い
浴室でのお祓い
さらに、家系に「尊い孫」を迎えるためとして100万ウォン(約11万円)を要求され、そのお金で息子を授かるためのお守りを購入されたというエピソードも。不妊治療を経て妊娠に至ったにも関わらず、「私たちの祈りが天に届いた」と義両親が勝手に解釈するなど、行き過ぎた言動はエスカレートする一方です。
食生活への介入、そして娘への偏見
義両親の干渉は食生活にも及びます。女性が鶏の煮込みを食べたいと希望したところ、「鶏やアヒルを食べると子どもの肌が粗くなる」と却下。葬儀場や病院への接近禁止など、妊婦の行動を制限する様々な迷信が押し付けられているようです。
そして、生まれてくる子どもが女の子だと判明した時、姑は「霊能者に相談したが、娘を産むと息子の人生が破滅する。2人の女性が息子を食い尽くす」と発言。この言葉は、女性にとって大きな衝撃だったに違いありません。
現代社会における迷信との向き合い方
夫の抗議により義両親からの連絡は減ったものの、節句の挨拶で実家を訪れた際に、出産日や命名を霊能者に依頼したことが「贈り物」として伝えられ、女性の嫌悪感はさらに深まりました。
この事例は、現代社会においても根強く残る迷信や、それに基づいた過干渉が、いかに妊婦の精神的な負担となるかを示す一例と言えるでしょう。 妊娠・出産というデリケートな時期だからこそ、周囲の理解とサポートが不可欠です。
夫婦間のコミュニケーション、そして専門家のアドバイス
このような状況下で、夫婦間のコミュニケーションは非常に重要です。夫は妻の気持ちを理解し、義両親との間に入り、適切な距離感を保つための努力が必要です。また、必要に応じて、専門家(カウンセラーや医師など)のアドバイスを受けることも有効な手段と言えるでしょう。
出産は人生における大きなイベント。喜びに満ちた経験となるよう、周囲のサポート体制を整え、安心して出産に臨める環境づくりが大切です。