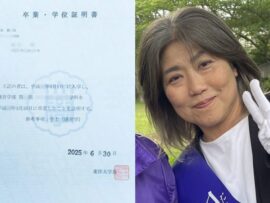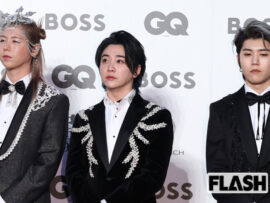対馬の美しい海が、磯焼けという深刻な問題に直面していることをご存知でしょうか? 海藻が消失し、魚が減り、漁業の未来が危ぶまれる中、一人の女性が立ち上がりました。今回は、磯焼け対策の切り札として注目を集める「そう介(イスズミ)」カツ誕生秘話と、その取り組みがもたらす希望に迫ります。
海の異変と「そう介」との出会い
かつて豊かな漁場として知られた対馬の海。しかし、1980年代頃から磯焼けと呼ばれる海藻の消失現象が深刻化し、水揚げ量は激減。地球温暖化やウニ、イスズミ、アイゴといった食害魚の増加など、様々な要因が絡み合っていると言われています。「このままでは島の未来が危ない…」そんな危機感の中、立ち上がったのが丸徳水産を経営する犬束ゆかりさんです。
 対馬の磯焼けの様子
対馬の磯焼けの様子
ある時、駆除されたイスズミやアイゴが焼却処分されている現状を知った犬束さんは、これらの魚を食用にできないかと考え始めます。イスズミは臭みが強く「猫も食べない」と言われる魚。しかし、「捕れるものを活用するしかない」という強い思いで、犬束さんは試行錯誤を重ねました。
女性の挑戦と「そう介プロジェクト」始動
2019年、犬束さんは地元の団体や市役所と協力し、「そう介プロジェクト」を立ち上げます。イスズミというネガティブなイメージを払拭するため、「そう介」という愛称を考案。海藻の「藻」、創意工夫の「創」、惣菜の「惣」など、様々な意味を込めて名付けられました。
 アイゴ MIT
アイゴ MIT
当初は周囲の理解を得られず苦労した犬束さんですが、諦めずに試作を続け、漁業者や水産関係者に試食を依頼。その熱意と努力が徐々に実を結び、賛同者が増えていきます。
丁寧な下処理で臭み解消!「そう介」カツ誕生
犬束さんは、イスズミを丁寧に血抜きし、何度も水を取り替えることで臭みが軽減できることを発見。さらに、すり身にして玉ねぎなどの野菜と混ぜ合わせることで、驚くほど美味しいカツが完成しました。玉ねぎの配合にもこだわり抜いた「そう介」カツは、2019年のFish-1グランプリで国産魚ファストフィッシュ部門グランプリを受賞。新たな水産資源の活用と加工技術が高く評価されました。
対馬の未来を照らす「そう介」カツ
現在、「そう介」カツやアイゴのフライは、犬束さんが経営する飲食店「肴や えん」の人気メニューとなっています。さらに、対馬の学校給食にも採用され、子どもたちの食育にも貢献。磯焼け対策と地域活性化の両面から、大きな注目を集めています。(対馬市水産課職員 山田一郎氏談)
「そう介プロジェクト」は、持続可能な漁業の実現と、地域経済の活性化に向けた希望の光となっています。食害魚を貴重な資源に変えることで、漁業者の収入増加、磯焼け対策、そして食卓の豊かさにも繋がります。ぜひ一度、「そう介」カツを味わってみてはいかがでしょうか?