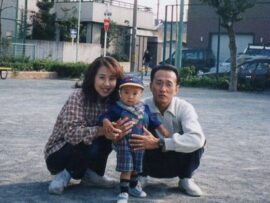(CNN) 南極で見つかったほぼ完全な頭骨の化石が、これまで知られた中で最も古い現生鳥類のものであることが分かった。マガモほどの大きさのこの鳥には、現在湖や海に暮らす水鳥との関連が認められる。新たな研究から明らかになった。
6800万年前のこの化石は、ベガビスとして知られる絶滅種のもの。種の生息年代は白亜紀の末で、間もなく巨大隕石(いんせき)の落下により恐竜が絶滅する時期に当たる。
恐竜と生息年代が重なる鳥類の多くは歯を有し、骨を含む尾が生えているなど、現代の鳥とは異なる特徴が見られる。
しかし米パシフィック大学で生物学を専攻するクリストファー・トーレス助教によれば、ベガビスはアヒルくらいの大きさでカイツブリなどの水鳥と同様の生態系に属していたと考えられる。トーレス氏が筆頭著者を務めた研究論文は5日刊行のネイチャー誌に掲載された。
トーレス氏は新たに見つかった頭骨から、ベガビスの顎(あご)の筋肉組織を直接分析できたと説明。その仕組みにより水中で素早く口を開閉し、魚を捕食していたと示唆した。こうした生態は現代のカイツブリなどに広く共通するという。
また従来のベガビスの化石では完全な頭骨が見つかっていなかったと、論文の共著者でオハイオ大学の解剖学教授、パトリック・オコーナー氏は指摘する。頭骨は歯の欠如や拡大した前上顎骨(ぜんじょうがくこつ)といった現生鳥類に最も顕著な特徴が確認できる部位だという。
論文によると当該の頭骨は、2011年に南極半島で行った発掘で、6840万~6920万年前の岩石から見つかった。CTスキャンを用いて立体的に再現した脳の形も、現生鳥類の特徴を備えたものだったという。
これらの特徴を総合すると、ベガビスは現在1万1000種で構成される現生鳥類の最古の部類に位置づけられると、オコーナー氏は述べた。同氏によると6900万年前の南極は現在と異なり森林で覆われていた。同氏らのモデリングの多くに基づけば、当時の気候帯は冷涼な温帯に区分されるという。
トーレス氏によれば、ベガビスの化石が発掘された近くからは、恐竜絶滅直後の年代に属する鳥類の化石も見つかっており、一部の動物がどのように隕石落下を生き延びたのかについて古生物学上の調査が可能になる見通しだという。