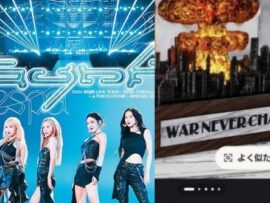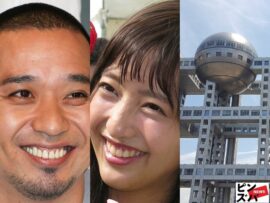日本のスポーツメディア業界は、大きな転換期を迎えています。新興勢力の台頭、海外動画配信サービスによるマネーゲームの激化など、従来のビジネスモデルが通用しない時代へと突入しています。このままでは、「世界のオオタニ」の活躍さえ、お茶の間に届かなくなる可能性も懸念されています。
スポーツ報道の現場:崩壊の危機
かつてスポーツ報道の中心を担っていたスポーツ新聞は、深刻な苦境に立たされています。駅売りやコンビニ販売を主体としたビジネスモデルは限界を迎え、経費削減の嵐が吹き荒れています。ネットでの先出し記事配信、PV至上主義の人事評価など、現場の記者たちは疲弊しています。30年のキャリアを持つベテラン記者A氏も、「取材体制は崩壊しつつある」と危機感を募らせています。若手記者の離職も相次ぎ、未来への展望は決して明るいとは言えません。
 alt_text
alt_text
老舗スポーツ紙の休刊も相次いでいます。2023年1月末には夕刊フジが休刊、東京中日スポーツも電子版への完全移行を決定しました。スポーツ報道の斜陽化は、もはや誰の目にも明らかです。スポーツジャーナリズムの専門家であるB教授は、「紙媒体の衰退は避けられないが、質の高いスポーツ報道は今後も必要とされる。新たなビジネスモデルの構築が急務だ」と指摘しています。
放映権高騰:お茶の間からスポーツが消える?
スポーツ中継を取り巻く環境も激変しています。放映権料の高騰により、日本のテレビ局は苦境に立たされています。五輪のような大型スポーツイベントでさえ、NHK頼みの状況が続いています。しかし、高騰する放映権料にはNHKでさえ太刀打ちできなくなってきています。
この高騰の背景には、DAZNなどの海外動画配信サービスの参入があります。2022年11月のサッカー日本代表のアジア最終予選では、DAZNが2試合を無料配信しました。これは日本のテレビ局にとって大きな衝撃でした。民放キー局社員C氏は、「海外勢の資金力には到底かなわない。このままでは、主要なスポーツ中継がお茶の間から消えてしまうかもしれない」と危機感を募らせています。

スポーツメディアの未来は、決して楽観視できるものではありません。しかし、スポーツへの情熱、質の高い報道への需要は決して消えることはありません。新たな時代に対応したビジネスモデルの構築、デジタル技術の活用など、様々な取り組みが求められています。スポーツの感動を未来へ繋ぐために、関係者たちの挑戦は続きます。