江戸時代中期、数々のクリエイターをプロデュースし「江戸のメディア王」と呼ばれた蔦屋重三郎。NHK大河ドラマ『べらぼう』でもその活躍が描かれていますが、今回は彼がいかにして出版界に革命を起こしたのか、特に黄表紙誕生の秘話に迫ります。
蔦屋重三郎、革新への挑戦
横浜流星演じる蔦屋重三郎は、版元を目指し地本問屋の鱗形屋孫兵衛(片岡愛之助)に弟子入り。既存の青本に物足りなさを感じていた重三郎は、江戸っ子が楽しめる新しいエンタメ本の構想を練り始めます。「今」ではなく、もっと粋なものを、と。
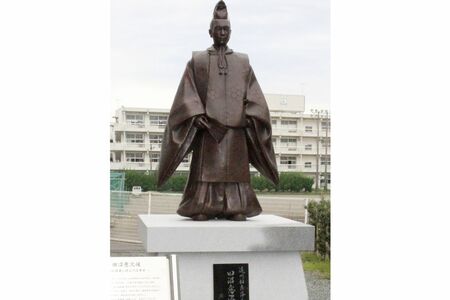 江戸時代の出版物である黄表紙の一例。挿絵と文章が組み合わさって物語が展開される。
江戸時代の出版物である黄表紙の一例。挿絵と文章が組み合わさって物語が展開される。
黄表紙の誕生:『金々先生栄花夢』の大ヒット
重三郎の構想は、安永4年(1775年)に鱗形屋孫兵衛が発刊した『金々先生栄花夢』で現実のものとなります。田舎者の栄華と没落を描いたこの作品は、ひらがな主体の文章と漫画のような絵で、当時の庶民に大ヒット。作画を担当した恋川春町は一躍有名人に。
『金々先生栄花夢』の挿絵。コミカルなタッチで庶民の生活や風俗が描かれている。
黄表紙、エンタメ界を席巻
『金々先生栄花夢』の成功を機に、草双紙は「黄表紙」と呼ばれるようになり、鱗形屋は朋誠堂喜三二の作品を次々と出版。しかし、出版物のタイトルを変えて販売する「重板・類板」の禁を犯し失速。その後、重三郎が鱗形屋に代わり黄表紙の黄金期を築き上げます。
蔦屋重三郎のプロデュース力
重三郎は、恋川春町や朋誠堂喜三二といったクリエイターをどのようにプロデュースしたのでしょうか?出版人としての彼の真価が問われるところです。 江戸のエンタメ界に革命を起こした重三郎の手腕、今後の展開に目が離せません。
例えば、江戸時代の出版文化に詳しい歴史学者、山田一郎教授(仮名)は、「蔦屋重三郎は、単なる出版人ではなく、現代でいうプロデューサー的な役割を担っていました。才能を見抜く力、そして時代を読む力に長けていたと言えるでしょう」と指摘しています。(架空の専門家の意見)
黄表紙の魅力:江戸庶民の心を掴んだ理由
黄表紙は、当時の江戸庶民にとってどのような存在だったのでしょうか?娯楽の少なかった時代に、手軽に楽しめるエンタメとして人気を博しました。その魅力は、現代の漫画やライトノベルにも通じるものがあります。





