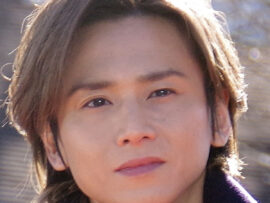2011年3月11日、東日本大震災。未曾有の大災害は、福島第一原子力発電所を襲い、想像を絶する危機を引き起こしました。本書『福島第一原発事故の「真実」』は、13年間にわたる取材、1500人以上の関係者へのインタビューから、事故の真相に迫った力作です。2022年度「科学ジャーナリスト大賞」受賞の重みを持つ本書から、文庫版『福島第一原発事故の「真実」ドキュメント編』の一部を抜粋し、緊迫の状況を改めてお伝えします。
全電源喪失、暗闇に包まれた中央制御室。計器は沈黙し、原子炉の状態は全く把握できない。運転員たちは、極限状態の中で、マニュアルにないルールを作りながら、最悪の事態に立ち向かっていきました。
光を求めて、未知の領域へ
地震発生から10分後、中央制御室は完全な暗闇に沈んでいました。運転員たちは、LEDライト、携帯用バッテリー、あらゆる光源をかき集め、30個ほどでしょうか。わずかな光を頼りに、操作盤、計器盤をくまなく確認していきます。しかし、ほとんどの計器は機能せず、原子炉の水位、温度など、原発の状態を示すデータは失われていました。まるで目隠しをして車を運転するような、まさに前代未聞の事態。マニュアルにも対処法は見つからず、未知の領域へと足を踏み入れていくのです。「五感を失った感覚」「手足を奪われたような状況」「これでもう何もできなくなった」—そんな絶望的な思いが運転員たちの脳裏をよぎりました。
 alt
alt
程なくして、数人の運転員が当直長に現場確認の要請を申し出ます。しかし、津波の再来も懸念される中、原子炉建屋内での作業は極めて危険でした。当直長は苦悩します。アメリカ同時多発テロでの消防士の救出劇を描いたノンフィクションに感銘を受け、危機管理について深く学んでいた彼は、常に生還の可能性を模索しながら行動することの重要性を理解していました。熟考の末、彼は決断を下します。「ルールを決めよう」。中央制御室からの退出は当直長の許可制、必ず2人1組で行動、調査時間は2時間以内、行き先は事前に明確化し、許可された場所以外への移動は禁止。マニュアルにはない、極限状況下で生まれた独自のルールでした。
危機管理、仲間との絆
運転員たちは、先輩後輩の強い絆で結ばれていました。リーダーの指示は絶対であり、新たなルールは厳格に守られました。当直長を最も悩ませたのは、起動させたはずの非常用冷却装置の状況が把握できないことでした。2号機のRCICは起動を確認していましたが、バッテリー駆動の装置のため、バッテリー切れで停止している可能性も否定できません。しかし、RCICの状態を示すランプも消灯したまま。1号機のイソコンも同様に、蒸気の力で稼働するものの、ランプが消灯し、弁の開閉状態が不明でした。

当直長は、免震棟へのホットラインで叫びました。「ブタの鼻を見てくれ!」。ブタの鼻とは、1号機原子炉建屋の西側壁にある2つの排気口の通称。イソコンが作動していれば、そこから白い蒸気が噴出する、というベテラン運転員の間で伝わる経験則がありました。中央制御室からは確認できないブタの鼻は、免震棟からは比較的見やすい位置にありました。1号機の運命は、マニュアルにはない、経験に基づく記憶に託されたのです。
原子炉の状態が把握できない暗闇の中、運転員たちは冷静な判断と迅速な行動で、未曾有の危機に立ち向かいました。極限状態での彼らの奮闘は、私たちに多くの教訓を与えてくれます。