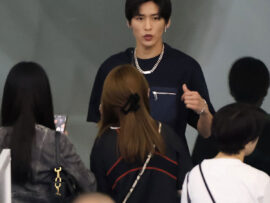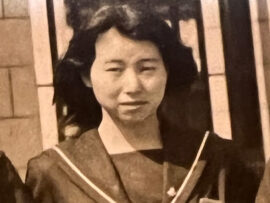日本列島は、東日本大震災以降、地震や火山噴火が頻発する「大地変動の時代」に突入しました。迫りくる巨大地震から身を守るためには、地学の知識が不可欠です。京都大学名誉教授 鎌田浩毅氏の著書『大人のための地学の教室』から、南海トラフ巨大地震の脅威と生き残るための知恵を分かりやすく解説します。
南海トラフ巨大地震とは?
南海トラフとは、静岡県から紀伊半島、四国、九州沖合に伸びる海底の窪地です。ここで発生する巨大地震は、東海地震、東南海地震、南海地震の3つが連動する可能性があり、さらに日向灘地震も加わると、甚大な被害が予想されます。
 南海トラフのイラスト
南海トラフのイラスト
2030年代、想定される被害規模
南海トラフ巨大地震は、2035年をピークとする前後5年、つまり2030年代に発生が予測されています。その被害は、東日本大震災の死者約2万人、被害総額約20兆円に対し、死者32万人、被害総額220兆円と、桁違いに大きいと想定されています。これは、南海トラフ沿岸地域の人口密度が高いことが要因です。人口集中地域における災害の恐ろしさを物語っています。
過去の南海トラフ巨大地震からの教訓
歴史を振り返ると、南海トラフ巨大地震は繰り返し発生し、甚大な被害をもたらしてきました。1707年の宝永地震、1854年の安政南海地震、1946年の昭和南海地震などがその例です。これらの地震発生間隔は約100年で、次の発生時期は2030年代と予測されています。
地震発生のパターン
過去の南海トラフ巨大地震では、複数の地震が連動するケースが見られます。宝永地震では東海、東南海、南海地震の3つが20秒以内に連動発生しました。安政南海地震では東南海地震と南海地震が32時間差で、昭和南海地震では昭和東南海地震と昭和南海地震が2年差で発生しています。
東海地震の危険性:静かなる脅威
注目すべきは東海地震です。安政南海地震以降、東海地震は発生しておらず、「東海地震は起きないのでは?」という声も聞かれます。しかし、過去の南海トラフ巨大地震では、約3回に1回の割合で3つの地震が連動しています。
エネルギー蓄積の危険性
東海地震が長期間発生していないことは、それだけエネルギーが蓄積されていることを意味します。東京大学教授 西成活裕氏も「知識は力なり」と述べ、地学の知識の重要性を強調しています。地震学者の間では、東海地震は「いつか必ず起きる」と考えられています。

備えあれば憂いなし:今できること
南海トラフ巨大地震は、私たちの生活に大きな影響を与える可能性があります。日頃から防災意識を高め、備えを怠らないことが大切です。ハザードマップの確認、非常食の備蓄、避難経路の確認など、できることから始めましょう。
まとめ
南海トラフ巨大地震は、決して他人事ではありません。地学の知識を深め、地震のメカニズムや過去の災害を学ぶことで、防災意識を高め、適切な行動をとることができるようになります。鎌田浩毅氏の『大人のための地学の教室』は、地震への理解を深め、備えを充実させるための貴重な一冊です。