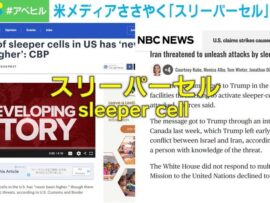米価高騰が社会問題となる中、政府は備蓄米の放出を決定しました。しかし、この対策は根本的な解決には程遠いのが現状です。肥料や燃料の高騰により、小規模農家にとっては米作りを続けるほど赤字が膨らむ悪循環に陥っています。今回は、茨城県筑西市の兼業米農家、岩見正道さん(75)の体験談を通して、米農家が抱える厳しい現実をお伝えします。
 茨城県筑西市の兼業米農家、岩見正道さん
茨城県筑西市の兼業米農家、岩見正道さん
サラリーマンの給料で農業の赤字を補填
岩見さんは、20年以上前に父親から農業を継承した兼業農家です。700俵(42トン)という比較的大規模な生産量にも関わらず、年間200万円もの赤字を抱えていました。
「親父の時代は専業農家でも生活できたが、今は到底無理。会社員の給料で米作りの赤字を補填していた」と岩見さんは語ります。サラリーマンの給与所得と農業の損失を損益通算することで、還付金を受け取り、なんとか経営を維持してきたのです。
米作りは道楽?継承への苦悩
なぜ、年間200万円もの赤字を出しながらも米作りを続けるのでしょうか?岩見さんは「道楽のようなもの。趣味のゴルフにお金をかけるのと同じ」と答えます。健康維持の側面もあるものの、儲けようとは思っていないと言います。

「先祖代々から受け継いできたという思いもある。しかし、息子に『コメ農家を継げ』とは言えない」と岩見さんは苦悩を吐露します。米作りへの情熱と現実の厳しさの間で揺れ動く、多くの農家の心情を代弁しているかのようです。
米価高騰の恩恵は届かず…小規模農家の苦境
米価が高騰しているにも関わらず、その恩恵は小規模農家に届いていません。流通過程の問題や、肥料、燃料費の高騰などが原因です。「農林中央金庫」の米穀経済の専門家である山田一郎氏(仮名)は、「生産コストの上昇分が米価に反映されにくい構造的な問題がある。小規模農家への支援策を強化する必要がある」と指摘します。
岩見さんのような兼業農家の存在は、日本の農業を支える上で重要な役割を果たしています。しかし、赤字経営を強いられる現状は、日本の農業の未来を危うくする深刻な問題です。政府の対策が待たれるところです。
未来への希望を繋ぐために
岩見さんのような農家の努力と、消費者の理解と協力が、日本の食卓を守る上で不可欠です。地産地消や、農家への直接支援など、私たち一人ひとりにできることから始めていくことが重要です。