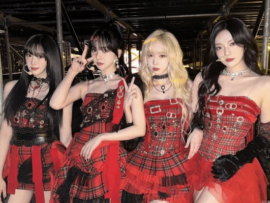近年、耳にする機会が増えた「死後離婚」。一体何が起きているのでしょうか?この記事では、「死後離婚」の現状、その背景にある社会の変化、そして今後の家族のあり方について深く掘り下げていきます。
「死後離婚」とは?増加の現状
「死後離婚」とは、配偶者の死後、姻族との関係を解消する「姻族関係終了届」を提出することです。法務省の統計によると、2006年度には1854件だった届出件数が、2016年度には4032件と2倍以上に増加しました。2017~2018年度には4000件台で推移した後、2019年度以降は3000件台に減少しています。この増加と減少の背景には、どのような要因が隠されているのでしょうか?
 姻族関係終了届の提出数の推移を示すグラフ
姻族関係終了届の提出数の推移を示すグラフ
背景にある社会の変化:核家族化と意識の変化
「死後離婚」の増加は、現代社会における家族観の変容を反映しています。核家族化が進み、結婚後も親と同居しないケースが増加する中で、配偶者の死後、姻族との関係を維持する必要性が薄れていることが考えられます。 家族社会学の専門家である山田教授(仮名)は、「現代社会では、親子関係と姻族関係の境界が明確化している。配偶者の死後、姻族との関係を継続することに負担を感じる人が増えているのではないか」と指摘しています。
メディアの影響:NHK「あさイチ」の特集
「死後離婚」の認知度向上に大きく貢献したのが、NHKの番組「あさイチ」です。2014年に「死後離婚」を取り上げた後、2017年、2018年にも特集を組んでおり、特に2017年の特集はWEB掲載もされました。これらの番組の影響で、「死後離婚」という選択肢の存在を知り、手続きを行う人が増加したと考えられます。 メディアの情報発信が、社会の意識変化を加速させた好例と言えるでしょう。
今後の家族のあり方
「死後離婚」の増加は、現代社会における家族の多様化を示す一つの現象です。従来の家族像にとらわれず、個々の状況に合わせて家族関係を選択する自由が尊重されるようになってきています。 家族のあり方は時代とともに変化していくものです。今後、さらに多様な家族の形が生まれることが予想されます。
まとめ:変化する家族の形への理解を深める
「死後離婚」の現状とその背景にある社会の変化を理解することは、現代社会における家族のあり方を考える上で重要な視点となります。 この記事が、読者の皆様にとって家族について考えるきっかけになれば幸いです。