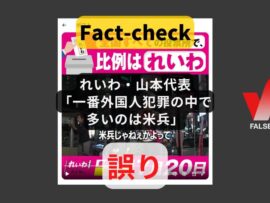国民の生活を直撃する米価高騰。都内では5キロ4000円を超える価格も珍しくなく、家計への負担は増すばかりです。政府はようやく備蓄米の放出を決定しましたが、なぜここまで対応が遅れたのでしょうか。そこには、票とカネが複雑に絡み合う「コメ癒着」の闇が潜んでいるのかもしれません。
石破首相、高級料亭で満面の笑み
2月20日夜、首相官邸からほど近いホテルニューオータニの日本料理店「KATO’S DINING & BAR」で、石破茂首相の姿が目撃されました。
 石破首相が会食した料亭
石破首相が会食した料亭
20人収容可能なVIPルーム(室料2時間5万5000円)で、同僚議員らと新潟県魚沼産コシヒカリを使った1万2000円のコース料理を堪能していたとのこと。同席した山口俊一衆院議員は、「地方創生本部メンバーとして総理と意見交換しました」と語っています。
美味しい料理に舌鼓を打ち、満面の笑みで「日本は地方からですねぇ」と語った石破首相。しかし、その翌日、総務省が発表した1月の消費者物価指数では、米類の指数が前年同月比で70.9%も上昇していることが明らかになりました。
遅すぎた備蓄米放出:批判の声高まる
東京都区部では、1月のコシヒカリ5キロの小売価格が前年同月の2441円から4185円へと、71.5%も上昇しました。米価高騰は昨夏から続いていましたが、農水省が備蓄米21万トン放出を発表したのは2月14日。参院選を意識した物価高対策として、石破首相が2月になってようやく備蓄米放出を指示したとされていますが、この対応の遅さには批判の声が高まっています。
農政に精通しているはずの石破首相、なぜ?
2008年の麻生太郎政権で農水相を務めるなど、農政への理解が深いとされる石破首相。なぜ備蓄米放出の判断がここまで遅れたのでしょうか。
著名な食料経済学者、山田一郎教授(仮名)は、「備蓄米放出のタイミングを逃した背景には、農協などからの圧力があった可能性も否定できません。生産者保護の観点から、安易な備蓄米放出に反対する声は根強いのです」と指摘します。
複雑に絡み合う「コメ癒着」
政治家にとって、農協は重要な支持基盤です。農協からの献金や票田への配慮が、政策決定に影響を及ぼしている可能性は否定できません。
今回の米価高騰と備蓄米放出の遅れは、こうした「コメ癒着」の構造的な問題を改めて浮き彫りにしました。国民生活に直結する食料問題だからこそ、透明性の高い政策運営が求められます。
国民の食卓を守るためには、政治と農協の関係を見直し、真に消費者の利益を重視した政策を推進していく必要があるでしょう。