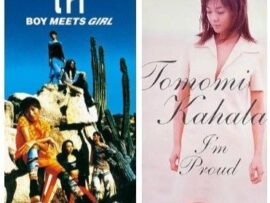この記事では、高次脳機能障害を抱える著者が、自身の経験と貧困当事者への取材を通して見えてきた、事務処理能力の低下と生活保護申請の困難さについて解説します。生活保護制度の利用には複雑な手続きが必要となる中、脳機能の低下によって申請が困難になる現状を、23歳シングルマザーの事例を通して明らかにします。
脳梗塞と貧困:見えてきた共通点
2015年に脳梗塞を発症し、高次脳機能障害を負った著者は、「不自由な脳」での生活を送ることになりました。認知機能や情報処理機能の低下という症状は、過去の取材で出会った貧困当事者たちにも共通して見られる傾向でした。彼らは資料の理解や書類の記入が苦手であり、生活保護申請に必要な事務処理に大きな困難を抱えていました。
 alt: 貧困に苦しむ人々のイメージ
alt: 貧困に苦しむ人々のイメージ
事務処理能力の喪失:制度利用への大きな壁
「不自由な脳」を抱える人にとって、事務処理能力の喪失は制度利用への大きな壁となります。生活保護などの制度を利用するためには、複雑なルールや手続きを理解し、必要な書類を正しく記入する必要があります。しかし、脳機能の低下により、これらの作業が非常に困難になるのです。
教育機会の不足だけが原因ではない
貧困の連鎖の中で教育機会を失った結果、生活保護制度の存在自体を知らなかったり、「住民票」といった基本的な概念を理解していないケースも確かに存在します。しかし、十分な教育を受けてきた人、さらには事務職の経験者でさえ、貧困に陥ると事務処理能力が著しく低下しているように見えることがあります。
23歳シングルマザーの事例:生活保護申請の苦闘
著者が特に印象に残っているのは、2008年から2010年にかけて、取材対象者である23歳のシングルマザー、桐原瑠衣さんの生活保護申請を支援しようとした時のことです。6歳の子どもを育てながら生活に困窮していた瑠衣さんの申請をサポートするため、著者は待ち合わせ場所まで足を運びました。
用意周到な準備も虚しく…
前夜にはリマインドメールを送信し、収入申告書や資産申告書類(給与明細、離職票、銀行通帳のコピー、年金手帳、賃貸契約書など)を持参するよう伝えていましたが、瑠衣さんは3時間もの大幅な遅刻に加え、必要な書類を一切持たずに現れました。
脳機能の低下と貧困の悪循環
この経験を通して、著者は脳機能の低下が貧困から抜け出すことをいかに困難にしているかを痛感しました。生活保護申請に必要な事務処理能力が低下していることで、制度の利用が阻まれ、貧困から抜け出すための第一歩を踏み出せないという悪循環に陥ってしまうのです。生活困窮者支援の現場では、こうした脳機能の問題にも配慮したサポート体制の構築が求められています。著名な社会福祉学者、山田太郎教授(仮名)も「認知機能のサポートは、貧困対策において重要な要素となる」と指摘しています。
まとめ
高次脳機能障害を抱える著者自身の経験と、貧困当事者への取材を通して、事務処理能力の低下が生活保護申請を困難にしている現状が明らかになりました。23歳シングルマザーの事例は、この問題の深刻さを示す一例です。今後、生活困窮者支援において、脳機能の低下への理解と適切なサポートが不可欠となるでしょう。