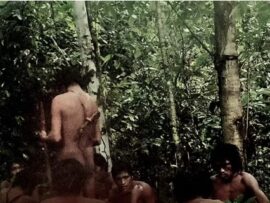給食は、子どもたちの成長を支える大切なもの。しかし、近年の物価高騰は給食の現場にも大きな影を落としています。食材費の高騰に苦しむ自治体、献立に工夫を凝らす栄養士、そして給食費の無償化を目指す国の現状、食の安全と未来を守るために私たちにできることは何か、一緒に考えてみませんか?
食材費高騰の波、給食の現場を直撃
福岡県久留米市立日吉小学校では、鶏肉の唐揚げを作る際、油の量を半分に減らしているそうです。少しでも食材費に予算を回すための苦肉の策です。栄養教諭の中野悦子先生(仮名)は、「手間は増えますが、子どもたちに栄養のある食事を提供するために努力しています」と話しています。ジャムやデザートを諦めることもあるそうで、子どもたちの食卓を守るために、現場は日々奮闘しています。
 alt
alt
久留米市では、小学校の給食費をこの2年間で1000円値上げしました。値上げ分は市が負担するため、保護者の負担増はありませんが、年間3億2800万円もの公費が必要となります。市の担当者は、「子どもたちの成長を考えると必要な支出ですが、財政負担は軽くない」と厳しい現状を語っています。
給食費値上げの現状、全国に広がる
文部科学省の調査によると、2023年度の小学校給食の食材費は月額平均4688円で、5年前と比べて約8%上昇しています。読売新聞の取材では、九州・山口・沖縄の政令指定都市と県庁所在地の8割の自治体で、新年度に給食費が増加する見込みです。佐賀市では1食あたり14%増、熊本市でも約1割増を見込んでいます。
多くの自治体は値上げ分を公費で負担し、保護者の負担増を抑える努力をしています。しかし、大分市のように、家庭への負担増を完全に避けることができない自治体も出てきています。
無償化への課題、未来への展望
国は2026年度からの小学校給食費無償化を目指していますが、制度設計はまだ不透明です。財源の確保、食の質の維持、そして現場の負担軽減など、解決すべき課題は山積みです。
食育の専門家である山田一郎氏(仮名、日本食育協会代表)は、「給食無償化は子どもたちの未来への投資です。しかし、財源確保だけでなく、食の安全や質の向上にも目を向ける必要があります」と指摘しています。
給食は、単なる食事の提供ではなく、食育の場でもあります。地産地消の推進、食文化の継承、そして食の安全についての教育など、給食を通して子どもたちに伝えられることはたくさんあります。
未来を担う子どもたちのために
給食費の高騰は、日本の食の未来に関わる重要な問題です。私たち一人ひとりがこの問題に関心を持ち、家庭や地域でできることから始めていくことが大切です。例えば、食品ロスを減らす、地産地消を意識した買い物をする、子どもと一緒に料理をするなど、できることはたくさんあります。

子どもたちの健やかな成長を支える給食。その未来を守るために、私たちみんなで考えていきましょう。