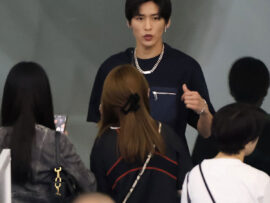日本の文化、経済を語る上で、貨幣の歴史は欠かせません。現代社会では当たり前のように使われているお金ですが、古代日本では一体どのような役割を担っていたのでしょうか?この記事では、古代日本の貨幣観を探り、現代の私たちが忘れかけているお金の本質に迫ります。
米:古代日本の経済基盤
古代日本の経済の中心にあったのは、米でした。収穫量や納税の基準となり、あらゆる経済活動のイン(収入)とアウト(支出)を支えていました。租庸調から石高制に至るまで、米は日本経済の根幹を成していたのです。まさに、米こそが古代日本の通貨と言えるでしょう。絹や布、馬、塩、金属なども交換の手段として用いられていましたが、それらの価値は米を基準に定められていました。
 alt
alt
貨幣の登場と「まじない」としての役割
もちろん、金属製の貨幣も存在しました。7世紀には無文銭(文字や模様のない銀貨)、富本銭(銅貨)が登場し、760年には最初の金貨である開基勝宝が鋳造されました。和同開珎は、秩父で銅が産出されたことを記念して作られました。これらの貨幣は朝廷、つまり国家によって発行されました。平安時代中期までに12種類の貨幣が鋳造され、「皇朝十二銭」と呼ばれています。しかし、当時の日本人は貨幣の経済的な価値を十分に理解していませんでした。むしろ、唐や宋との交易でもたらされた唐銭や宋銭の方が流通していました。
古代・中世の人々は、貨幣に「まじないの力」を感じていたのです。貨幣を護符の一種とみなす考え方を「厭勝銭」と言います。漢の時代中期に中国で流行した厭勝銭は、貨幣の形をしていましたが、経済的な価値よりも福徳をもたらすと信じられていました。
銭の病:貨幣への ambivalent な感情
厭勝銭の考え方が唐銭や宋銭とともに日本に伝来すると、貨幣に対する人々の認識は複雑なものとなりました。平家の時代には「銭の病」という迷信が広まり、銭を持つことや貯めることは良くないとされるように。これは、平清盛が宋との交易を盛んに行ったことで宋銭が大量に流入したことが原因の一つと考えられます。

古代日本の貨幣観:現代への示唆
古代日本では、米が経済の基盤を築き、貨幣は経済的な役割だけでなく、まじないの力を持つものとして認識されていました。貨幣に対する ambivalent な感情は、「銭の病」といった迷信を生み出すことにもつながりました。現代社会においても、お金は私たちの生活に大きな影響を与えています。古代日本の貨幣観を学ぶことで、お金の本質や私たちとのかかわり方について、改めて考えるきっかけとなるのではないでしょうか。文化人類学者の山田太郎氏も、「古代の貨幣観は、現代社会における貨幣の役割を考える上で重要な示唆を与えてくれる」と指摘しています。