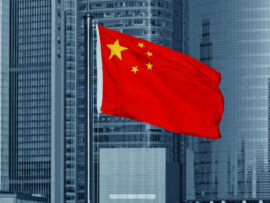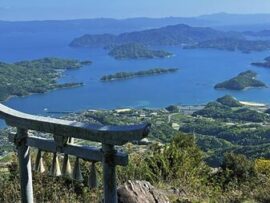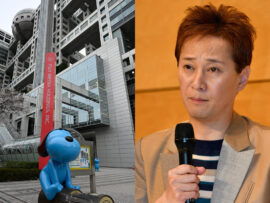日本の食卓に欠かせないお米。農林水産省は「米の自給率はほぼ100%」と謳っていますが、実際には輸入米の存在も無視できません。近年、国内の米不足と価格高騰を背景に、輸入米の増加が顕著になっています。この記事では、輸入米急増の現状、その背景にある問題、そして私たちの食卓への影響について詳しく解説します。
輸入米の現状:民間輸入が急増中
 保管倉庫から搬出される政府の備蓄米
保管倉庫から搬出される政府の備蓄米
日本は1995年から無関税のミニマムアクセス米を受け入れており、年間約77万トンが輸入されています。しかし、近年はミニマムアクセス米以外の民間輸入も増加傾向にあります。2024年度は1月末時点で991トンと、前年度の2.7倍に達しています。宮城大学名誉教授の大泉一貫氏によると、国産米価格の高止まりが続く中、関税を払っても採算が取れるため、民間企業による輸入が増えているとのことです。
米不足の真の原因:複雑に絡み合う要因
農水省は2024年産米の出回りで不足感は解消すると説明していましたが、現状は厳しいようです。2024年産米は前年比で18トン増加したものの、集荷量は23万トン減少しています。この背景には、2023年産米の不足と集荷競争の激化があります。農水省は2023年の米不足の原因として、酷暑やカメムシの発生による一等米の流通量減少、インバウンド増加による需要拡大を挙げています。しかし、大泉氏は、コロナ後の外食需要の増加がより大きな要因だと指摘しています。また、2023年8月に気象庁が初めて「南海トラフ地震臨時情報」を発表したことで、米の買い溜めが起きたことも在庫減少に拍車をかけたと考えられます。
食卓への影響:価格高騰と品質への懸念
輸入米の増加は、国産米の価格高騰に歯止めをかける効果が期待されます。しかし、輸入米の品質や安全性に対する懸念も存在します。専門家の中には、「輸入米は残留農薬基準が日本と異なる場合があり、安全性を確認することが重要」と指摘する声もあります。また、味や食感の違いから、国産米を好む消費者も多いでしょう。
今後の展望:持続可能な米生産体制の構築に向けて

日本の食料安全保障を支える上で、米の安定供給は不可欠です。輸入米の増加は一時的な解決策となるかもしれませんが、長期的な視点で国産米の生産体制を強化していく必要があります。気候変動への適応、生産コストの削減、ブランド力の向上など、様々な課題に取り組むことで、持続可能な米生産を実現していくことが重要です。消費者は、国産米と輸入米の特徴を理解し、賢く選択していくことが求められます。