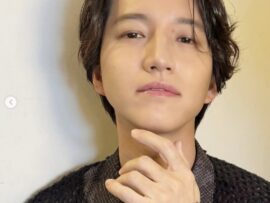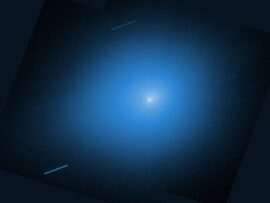あなたは「囚人のジレンマ」をご存知だろうか?これは、協力した方が全体にとって良い結果になるにも関わらず、個人の利益を追求した結果、全員が損をしてしまうというゲーム理論の有名なモデルだ。一見、理論上の話に思えるかもしれないが、実は私たちの日常生活にも、このジレンマが潜んでいる。本記事では、気鋭の哲学者ハンノ・ザウアー氏の著書『MORAL 善悪と道徳の人類史』(講談社)を参考に、人間同士がなぜ協力し合えないのか、その謎に迫っていく。
ゲーム理論:人間関係を数学で紐解く
20世紀に入り、人間同士の協力関係の条件や限界を探る学問、「ゲーム理論」が誕生した。ゲーム理論は、合理的な利害関係を持つ人々がどのように相互作用するかを分析し、協力行動を選択し、維持することが難しい理由を説明しようとするものだ。チェスやポーカーといったゲームの研究と誤解されがちだが、実際は、人間関係を数学モデルで表現し、協力が失敗する理由を解明することに主眼を置いている。
 囚人のジレンマの概念図
囚人のジレンマの概念図
例えば、共通の利益を優先する行動は「協力的」とみなされる。これは自己犠牲とは異なり、全員が協力の恩恵を受けるウィン・ウィンの状況、つまり「ポジティブサムゲーム」を生み出す。一方、ポーカーのように一方が勝てば一方が負けるのは「ゼロサムゲーム」だ。全員が損をする場合は「ネガティブサムゲーム」となる。
協力的行動は正義の重要な基準、「関係者全員が正当化できる」を満たす。それなのに、些細な事柄や感情によって協力が失敗すると、私たちは強い苛立ちを覚える。なぜだろうか?
囚人のジレンマ:協力の難しさを象徴する例
ゲーム理論の中でも特に有名なのが「囚人のジレンマ」だ。2人の犯罪者が警察に捕まり、銀行強盗の容疑で取り調べを受ける。証拠不十分のため、警察は2人を別々に尋問し、自白を促す取引を持ちかける。
ジレンマの構造:自白か、沈黙か
2人には2つの選択肢がある。「自白する」か「沈黙する」かだ。もし両方が沈黙を守れば、軽犯罪で済む。しかし、片方が自白し、もう片方が沈黙すれば、自白した方は釈放され、沈黙した方は重罪で長期間服役することになる。両方が自白すれば、2人ともそれなりの刑期を受けることになる。
個人にとって最良の選択は、相手がどう行動するかに関わらず、自白することだ。しかし、2人とも自白を選べば、両方が沈黙を守るよりも重い刑罰を受けることになる。これが「囚人のジレンマ」の核心だ。
日常生活への応用:環境問題、交通渋滞…
このジレンマは、私たちの生活にも様々な形で現れる。例えば、地球温暖化対策。各国が協力してCO2排出量を削減することが理想だが、自国だけの利益を優先して対策を怠れば、地球全体が深刻な被害を受ける。交通渋滞も同様だ。全員が公共交通機関を利用すれば渋滞は緩和されるが、個人の利便性を優先して車を使う人が増えれば、全員が時間ロスを被る。
専門家の見解:協力への道筋
著名なゲーム理論研究者、田中教授(仮名)は、「囚人のジレンマは、短期的な利益と長期的な利益のバランスをどう取るかという問題を提起している」と指摘する。「個人レベルでは自白が合理的でも、集団レベルでは沈黙が合理的となる。重要なのは、長期的な視点で物事を捉え、信頼関係を構築することだ。」
まとめ:未来への展望
囚人のジレンマは、人間社会における協力の難しさを浮き彫りにする。しかし、同時に、協力の重要性を改めて認識させてくれる。私たち一人ひとりが、長期的な視点と信頼関係を意識することで、より良い未来を築くことができるのではないだろうか。